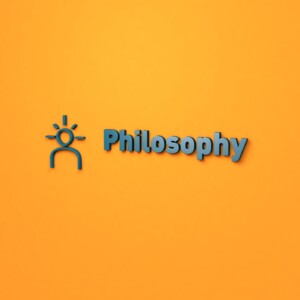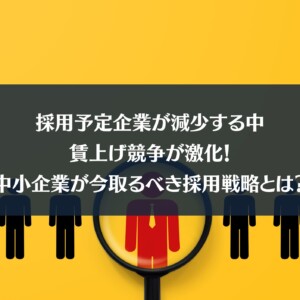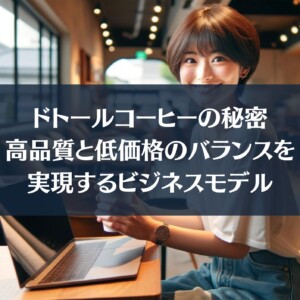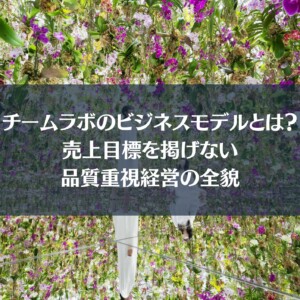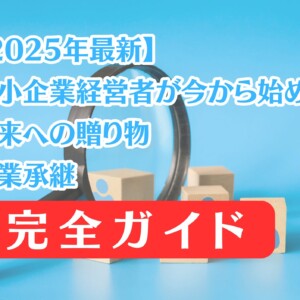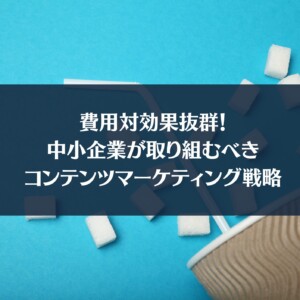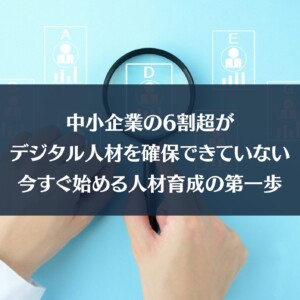経営者の退職金、準備できていますか?中小企業社長が知っておきたい老後資金づくりと家族を守る3つの方法
従業員の退職金制度は整えてきたけれど、自分自身の老後資金については後回しにしてきた。そんな想いを抱えている経営者の方は少なくないはずです。
会社の成長と従業員の幸せを第一に考えてきたからこそ、気づけば自分のことは置き去りに。でも、事業承継を考える年齢になってふと不安がよぎるのではないでしょうか。
「このまま引退して、本当に大丈夫だろうか」
経営者にも、退職金を受け取る権利があります。それは単なる老後資金ではなく、これまで会社に尽くしてきた功績への正当な対価であり、家族への責任を果たす大切な準備なのです。「退職金制度とは?|中小企業75%導入の理由と4種類の制度比較ガイド」で制度の全体像を理解することで、経営者自身の準備の方向性が明確になります。
本記事では、中小企業経営者が知っておくべき退職金の準備方法と、会社の資金繰りに影響を与えずに実現できる具体的な制度をご紹介します。明日からの一歩を踏み出すヒントを、ぜひ見つけていただければと思います。
目次
従業員のことは考えてきたけれど、自分の退職金は後回しに…経営者こそ準備が必要な理由
従業員の給料や福利厚生は整えてきたけれど、自分の老後資金は後回しに。本当に多くの経営者がこうした状況にあるのではないでしょうか。
あなたが築いてきた会社の価値を、自分自身と家族のために還元する。それは決してわがままではなく、責任ある経営判断です。退職金の準備は、事業承継と家族の安心のために欠かせない大切な経営課題といえます。
「会社を守ること」と「自分の将来」、どちらも大切にしていい
経営者として会社を守ることと、自分の老後を考えること。この二つは決して対立するものではありません。むしろ、「【2025年最新】事業承継完全ガイド|中小企業経営者が今から始める未来への贈り物」で解説している通り、経営者の将来設計は事業承継の成功に不可欠な要素なのです。
あなたが安心して引退できる準備ができていなければ、従業員も不安を感じてしまうかもしれない。経営者が自分の将来をしっかり設計することは、会社全体の安定にもつながるんです。事業承継を円滑に進めるためにも、後継者に負担をかけないためにも、経営者自身の退職金準備は必要不可欠なのです。
退職金準備が事業承継をスムーズにする
事業承継を考える年齢になると、「本当にこのまま引退して大丈夫だろうか」という不安を抱える経営者は多いものです。
創業者の退職金がきちんと準備されているかどうかが、承継の成否を大きく左右するケースは少なくありません。計画的に退職金を準備してきた経営者の場合、後継者は会社の資金繰りに余裕を持ってスタートできます。それは次世代への最高の贈り物になるはずです。実際に事業承継を成功させた経営者たちの実例は、「【事業承継 × 後継者の決断】後継者社長たちのリアルストーリー|コントリくんの学び」で詳しく紹介しています。
経営者の退職金は税制面で大きく優遇されている
役員退職金は、給与として受け取る場合と比べて税金が大幅に少なくなる仕組みになっています。この税制優遇の詳細については、「バレンタインショック完全対策!福利厚生型保険で節税と人材確保を両立【2024年最新】」でも触れている通り、法人保険活用との組み合わせでさらに効果を高めることが可能です。
退職所得控除は、勤続年数20年以下の場合「40万円×勤続年数」、20年超の場合「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算されます。さらに退職所得は控除後の金額の2分の1が課税対象となるため、給与と比べて手取り額が大きく増えるんですね。
適正な役員退職金は全額損金算入できるため、法人税の節税効果も期待できます。
給与と退職金の税負担比較
- 受取金額:3,000万円
- 勤続年数:30年
- 給与所得の場合は他の所得控除110万円を想定
| 項目 | 給与として 受け取る場合 |
退職金として 受け取る場合 |
|---|---|---|
| 受取金額 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 退職所得控除 | 対象外 | 1,500万円 |
| 給与所得控除等 | 195万円 | 対象外 |
| 所得控除 | 110万円 | 対象外 |
| 課税対象額 | 2,695万円 | 750万円 (1,500万円×1/2) |
| 所得税 (復興税含む) |
約825万円 | 約111万円 |
| 住民税 | 約270万円 | 約75万円 |
| 税金合計 | 約1,095万円 | 約186万円 |
| 手取り額 | 約1,905万円 | 約2,814万円 |
税負担の差額:約909万円
同じ3,000万円を受け取る場合でも、退職金として受け取ると給与として受け取る場合に比べて約909万円も税負担が軽減されます。
手取り額の差額:約909万円
退職金の場合、手取り額は約2,814万円(約93.8%)となり、給与の約1,905万円(約63.5%)と比較して大幅に多くの金額を受け取ることができます。
退職所得控除と2分の1課税により、長年の功労に対する退職金は税制面で大きく優遇されています。この優遇制度を活用することで、経営者の老後資金を効率的に準備することが可能です。
※ 計算は2025年の税制に基づいています。実際の税額は個別の状況により異なる場合があります。
※ 給与所得の場合の所得控除は基礎控除・社会保険料控除等の合計110万円を想定しています。
※ 役員等勤続年数5年以下の特定役員退職手当等には1/2課税が適用されない場合があります。
功績倍率法で見る、あなたの退職金の適正額とは
「自分の退職金って、いくらぐらいが妥当なんだろう?」
そんな疑問を持たれた経営者の方に、ぜひ知っていただきたいのが「功績倍率法」という計算方法です。
功績倍率法とは、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」で退職金額を算出する方法のこと。税務調査でも広く認められている、最も一般的な計算方式なんですね。適正な退職金額の算出は、「経営者必見!みなし退職と分掌変更による退職金の基礎知識」で解説している分掌変更時の退職金計算でも重要な役割を果たします。
功績倍率は役職によって目安が決まっており、社長で3.0倍、専務で2.4倍、常務で2.2倍が一般的とされています。
会社の資金繰りに影響を与えずに退職金を準備する具体的な方法
「会社のお金を圧迫しないか」という不安。その想い、本当によくわかります。
従業員の給与や設備投資、日々の運転資金を考えると、自分の退職金まで手が回らないと感じてしまうのは当然のことでしょう。
でも安心してください。実は、会社の資金繰りに大きな負担をかけることなく、計画的に退職金を準備できる方法がいくつも用意されているんです。月々の掛金を無理のない範囲で設定でき、しかも税制上のメリットも享受しながら、着実に老後資金を積み立てていくことができます。
ここでは、中小企業経営者が実際に活用できる具体的な制度をご紹介していきます。
小規模企業共済:経営者のための国の退職金制度
小規模企業共済という名前を聞いたことがあるでしょうか。これは、国が用意してくれている経営者専用の退職金制度なんですね。
個人事業主や小規模企業の経営者が、事業を廃業したり退任したりした際に、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取る仕組みです。
最大の魅力は、その柔軟性と税制優遇にあります。月々の掛金は1,000円から7万円まで、500円単位で自由に設定できるため、事業の状況に応じて無理なく続けられるんです。しかも、掛金全額が所得控除の対象となるため、毎年の所得税・住民税を軽減する効果も期待できます。
例えば、月額7万円を掛けた場合、年間84万円の所得控除となり、大きな節税メリットを実感できるでしょう。
受け取れる共済金は、退職の事由によって異なります。廃業や疾病・負傷による退任など正当な理由での退職(共済金A・B)の場合、比較的早い時期から掛金合計額を上回る金額を受け取れます。小規模企業共済以外の選択肢については、「【2025年最新】法人保険の賢い選び方と活用術|中小企業経営者のための完全ガイド」で包括的に比較検討できます。
一方、任意解約(解約手当金)の場合は、20年(240ヶ月)以上の加入で初めて掛金合計額と同等になります。長く事業を続けてこられた経営者の方にこそ、この制度の価値が輝くわけですね。
国が運営する安心感と、着実な資産形成を両立できる制度として、多くの経営者に選ばれているのも頷けます。
企業型確定拠出年金:会社の経費で積み立てられる仕組み
企業型確定拠出年金、略して企業型DCと呼ばれるこの制度も、経営者の退職金準備に活用できる強力な選択肢の一つです。
会社が掛金を拠出し、従業員や役員が自分で運用方法を選択して、将来の年金資産を形成していく仕組みになります。
経営者にとって嬉しいポイントは、会社が支払う掛金が全額損金算入できることです。つまり、法人税の節税効果を得ながら、自分自身の老後資金を準備できるというわけなんですね。さらに、従業員も一緒に加入できるため、優秀な人材の確保や定着にもつながる福利厚生制度として機能します。
運用の自由度が高いことも特徴的です。定期預金のような元本確保型の商品から、投資信託を使った積極運用まで、自分のリスク許容度に応じて選択できます。
ただし、元本保証がない商品を選んだ場合は、運用成績によって将来受け取れる金額が変動する点には注意が必要でしょう。それでも、長期的な視点で資産形成を考えるなら、検討する価値は十分にあるといえます。企業型DCを含む福利厚生制度の設計については、「福利厚生の種類と導入方法:企業が押さえるべきポイントを徹底解説」が参考になります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 会社負担で積立が可能 掛金全額を損金算入できる 運用方法の自由度が高い 従業員の福利厚生として機能 | 元本保証がない商品もある 原則60歳まで引き出し不可 運用に関する知識が必要 |
法人保険:万が一への備えと退職金準備を両立
法人保険を活用した退職金準備も、多くの経営者に選ばれている方法です。
生命保険という性質上、万が一のときには死亡保障として家族を守ることができ、無事に退職を迎えられたときには解約返戻金を退職金の原資として活用できるという、二つの安心を同時に手に入れられるんですね。
特に、まだ若い経営者の方や、家族への責任を強く感じておられる方にとっては、心強い選択肢となるでしょう。保険商品によっては、支払った保険料の一部または全額を損金算入できるものもあり、税制面でのメリットを享受しながら計画的な準備が可能になります。
ただし、法人保険にはさまざまな種類があり、それぞれ損金算入のルールや解約返戻金のピーク時期が異なります。自社の事業計画や退職予定時期、必要保障額などを総合的に考慮して、最適な商品を選択することが重要です。
信頼できる保険の専門家や税理士に相談しながら、慎重に検討していただきたいものですね。法人保険と退職金準備の関係については、「2024年版:法人向け保険商品の完全ガイド – メリット、デメリット、節税効果まで徹底解説」でより詳細に解説しています。
複数の制度を組み合わせて効果を最大化する
ここまでご紹介した三つの制度は、どれか一つを選ばなければならないわけではありません。むしろ、それぞれの特徴を活かして組み合わせることで、より安心で効果的な退職金準備が実現できるんです。
例えば、小規模企業共済で基礎的な退職金を確保しながら、企業型確定拠出年金で運用益を狙い、さらに法人保険で万が一への備えも万全にするという三本柱の戦略が考えられます。会社の規模や収益状況、経営者の年齢や家族構成によって、最適な組み合わせは異なってくるでしょう。
大切なのは、「いつか考えよう」と先延ばしにするのではなく、今日から一歩を踏み出すこと。
まずは自分の状況を整理し、どの制度が活用できそうか検討してみませんか。税理士やファイナンシャルプランナーといった専門家の力を借りながら、自社に合った退職金準備の設計図を描いていただければと思います。
あなたがこれまで築き上げてきた会社の価値を、しっかりと自分自身と家族のために還元していく。それは経営者としての当然の権利であり、同時に責任でもあるのです。
明日から始める退職金準備、あなたの会社と家族の未来のために
「従業員のことは一生懸命考えてきたけれど、自分の老後については…」
そんな想いを抱いている経営者の方は少なくないはずです。会社の成長と従業員の幸せを第一に考えてきたからこそ、気づけば自分のことは後回しになっていた。
でも、事業承継を考える年齢になってふと不安がよぎるのではないでしょうか。
経営者にも退職金を受け取る権利があり、それは家族への責任を果たす大切な準備です。ここでは、今日からできる具体的な退職金準備の方法をご紹介します。
年齢別に見る、今から始める退職金準備のスケジュール
「もう50代だし、今から準備しても遅いのでは」
そんな不安を抱えていませんか。実は、遅すぎるということはありません。年齢に応じた準備のスケジュールを立てることで、確実に老後資金を築いていくことは十分に可能なんですね。
40代の経営者であれば、まだ15年から20年という時間があります。この期間を活かして、小規模企業共済に月額7万円の掛金で加入すれば、退職時には1,500万円以上の共済金を受け取れる見込みです(基本共済金と付加共済金を含む概算。実際の受取額は運用状況により変動します)。
さらに、企業型確定拠出年金を併用することで、運用次第では2,000万円を超える資産形成も視野に入ってきます。この年代は、複数の制度を組み合わせて計画的に準備を進めていく最適な時期といえるのです。
50代に入ってからのスタートでも、決して諦める必要はありません。残り10年から15年という期間でも、小規模企業共済への加入は大きな効果を発揮します。月額5万円の掛金でも、10年間で600万円の積立てができますし、所得控除による節税効果を考えれば実質的な負担はさらに軽減されるわけです。
加えて、法人保険を活用した一時払い終身保険なども選択肢に入ってくるでしょう。
60代からの準備となると、時間的な制約はありますが、それでもできることはあります。すでに会社に蓄積された内部留保を活用した役員退職金の支給計画を立てることや、小規模企業共済に最短期間でも加入することで、わずかでも老後資金を増やせるんですね。
この年代では、事業承継と同時並行で進める退職金準備が現実的な選択肢となってきます。
どの年代からスタートしても、「今日が一番若い日」という事実は変わりません。年齢を理由に諦めるのではなく、今できることから始めていくという前向きな姿勢こそが、未来を変える力になるのです。
| 年代 | 準備期間 | 推奨する制度 | 期待できる金額目安 | 重視すべきポイント |
|---|---|---|---|---|
| 40代 | 15年~20年 |
小規模企業共済 + 企業型確定拠出年金 |
1,500万円~ 2,000万円超 (運用次第) |
複数制度の組み合わせで計画的に準備。長期運用を活かした積極的な資産形成が可能。 |
| 50代 | 10年~15年 |
小規模企業共済 + 法人保険の活用 |
600万円~ 1,000万円 (目安) |
所得控除による節税効果を最大化。一時払い終身保険なども選択肢に。 |
| 60代 | 5年~10年 |
内部留保の活用 + 役員退職金 |
数百万円~ (既存資産による) |
事業承継と同時並行で準備。会社の蓄積資産を活用した退職金設計が現実的。 |
まずは相談から、専門家に聞いてみるべき3つのこと
退職金準備を始めようと決意しても、「何を相談すればいいのかわからない」という壁にぶつかる経営者の方は少なくありません。
税理士やファイナンシャルプランナーに相談する際、具体的に何を聞けばいいのか。ここでは、初回相談で必ず確認しておきたい3つのポイントをお伝えします。
①自社の状況で受け取れる適正な役員退職金の額はどのくらいか
一般的な計算式として「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」があり、社長の功績倍率は2.0~3.0倍程度が目安とされています。
ただし、実際には業種や会社規模、地域性によって適正額は変わってくるものです。税務調査で否認されないための根拠づくりも含めて、専門家の意見を聞いておくことが重要なんですね。
②今の会社の財務状況で、どの退職金準備制度が最適か
小規模企業共済、企業型確定拠出年金、法人保険など、それぞれにメリットとデメリットがあるわけですが、会社の利益水準や資金繰りの状況によって、選ぶべき制度は異なってきます。
単に節税効果だけでなく、事業の安定性も考慮した総合的なアドバイスを求めましょう。
③退職金を受け取る際の税金対策
退職所得控除の仕組みを最大限に活用するためには、受け取り時期や方法の選択が重要になってきます。一括で受け取るのか、分割にするのか。他の所得との兼ね合いはどうか。
こうした具体的なシミュレーションを、数字を見ながら相談できると安心ですね。
相談のハードルを感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの税理士は初回相談を無料で受け付けています。「まず話を聞いてみよう」という軽い気持ちで、一歩を踏み出していただければと思うんです。
退職金準備チェックリスト:できているか確認しよう
さあ、ここまで読んでいただいた皆さまに、実際の準備状況を確認していただくためのチェックリストをご用意しました。
できていない項目があっても、決して焦る必要はありません。むしろ、今の自分の立ち位置を知ることが、次の一歩へとつながっていくんです。
このチェックリストは定期的に見直すことをおすすめします。半年後、1年後に再度確認すれば、着実に前進している状況を実感できます。
いくつチェックがつきましたか。
すべてに丸がついている方は、素晴らしい準備状況といえるでしょう。一方で、チェックがほとんどつかなかった方も、落ち込む必要はまったくありません。大切なのは、「気づいた今日から始める」という決意なんですね。
このチェックリストは、定期的に見直していただくことをおすすめします。半年後、1年後に再度確認すれば、着実に前進している自分の姿を実感できるはず。一つひとつクリアしていく達成感が、さらなる行動への原動力となっていくでしょう。
まとめ
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。経営者として会社を支え続けてこられたあなたが、ご自身の未来にも目を向けるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。この記事でお伝えした退職金準備の重要なポイントを、改めて整理してご紹介します。
- 経営者の退職金は税制面で大きく優遇されており、退職所得控除と2分の1課税により給与と比べて手取り額が大幅に増加する
- 小規模企業共済、企業型確定拠出年金、法人保険という3つの制度を組み合わせることで、会社の資金繰りに影響を与えずに計画的な準備が可能になる
- 年齢に応じた準備スケジュールを立てれば遅すぎることはなく、40代なら1,500万円以上、50代でも600万円以上の退職金準備が実現できる
あなたがこれまで築き上げてきた会社の価値を、しっかりと自分自身と家族のために還元していく。それは決してわがままではなく、経営者としての正当な権利であり、同時に家族への愛情表現でもあります。事業承継をスムーズに進めるためにも、後継者に余計な負担をかけないためにも、今日から一歩を踏み出していただきたいのです。税理士やファイナンシャルプランナーといった専門家の力を借りながら、まずは自分の状況を整理することから始めてみませんか。明日という日が、あなたの新しいスタートの日になりますように。そして、安心して次のステージへと進んでいけますように。心から応援しています。
あわせて読みたい関連記事
経営者の退職金準備をさらに深く理解するために、以下の記事も参考にしてください。