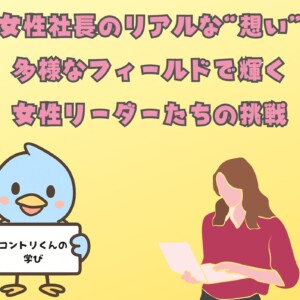若手社労士集団「士進会」初陣講演レポート:人事労務の最前線から見る、成長し続ける会社の共通点
CIC東京で開催されたイノベーション・コミュニティイベント「Venture Café Tokyo」に、若手社労士集団「士進会」が初登壇。
人事労務の専門家4名が語った「成長し続ける会社の共通点」とは?採用戦略から福利厚生、給与設計まで、中小企業経営者が明日から使える実践的な知見をレポートします。
新しい風を吹かせる社労士集団の誕生
2025年3月末、一つのX(旧Twitter)投稿から始まった物語がある。
「社会保険労務士の社会的地位を向上するための社労士団体を作りたいと密かに思っております」
【仲間募集中】
— 奥村 優希 \20代開業社労士、出版中/ (@yokumura0106) March 28, 2025
社労士の皆さんへ
社労士の社会的地位を向上するための社労士団体を作りたい…
と密かに思っております。
さまざまな方とお話しする中で、想いに共感してくださる方と取り組みをご一緒できたら嬉しいです!
一度、私とオンラインでお話ししてみませんか?…
この投稿をきっかけに、わずか数ヶ月で結成されたのが「士進会」だ。発起人の奥村優希氏の投稿に共感した30名もの社労士とオンラインで対話を重ね、特に思いの合う4名が集結した。
組織名の「士進会」には、温故知新の精神で社労士業界の地位向上をグイグイ進めていくという決意が込められている。まさに「士を背負う」覚悟で臨む、壮大なプロジェクトだ。
士進会が直視する業界課題は二つある。一つは社労士事務所職員の賃金の低さ。もう一つは、職人気質の伝統的な社労士と、ビジネス志向の社労士との分断だ。この二つの課題を解決し、社会保険労務士会と若手をつなぐ架け橋となることを目指している。
多様な専門性を持つ4人のプロフェッショナル

奥村優希氏:SAKURAOFFICE社会保険労務士法人 港オフィス 代表
子役から働き続け、芸能活動、酪農の営業、日本酒アンバサダーと多彩なキャリアを経て社労士に。「働く時間が人生の大半を占めるなら、それは苦しい時間ではなく楽しい時間であるべき」という信念のもと、IT関連、不動産、研究開発、東大発ベンチャーなど幅広い業種をサポート。士進会の発起人として、業界改革の先頭に立つ。

岡達己氏:経営労務事務所 たぬき屋 代表
スタジオジブリに7年間勤務し、制度設計や労務管理、採用を担当。「ジブリから嫌なニュースが出ないよう、裏でしっかりクローズしてきた」と語る実務力の持ち主。人事労務を網羅的にカバーし、特定業種に偏らない幅広い対応が強み。開業当初に、うっかり「たぬき屋」という屋号を選んだユニークな経歴の持ち主だ。

櫻井雄三氏:社会保険労務士法人 人事オフィス 代表
医療機関に特化した珍しいタイプの社労士。「医療×社労士」として独立することを決め、社労士法人での修行を積んだ上で、病院の人事部として現場経験を積むという計画的なキャリア設計で独立5年目を迎える。医療業界特有の課題に精通し、業種特化ならではの深い専門性を持つ。

中野真宏氏:SBPパートナー社会保険労務士事務所・行政書士許認可支援オフィス 代表
メガベンチャーやスタートアップでエンジニア、マーケティング、データアナリストなど幅広い職種を経験。7人から600人規模まで、組織の成長フェーズごとの壁を実体験している。PythonやGoogle Apps Scriptなどのプログラミングスキルを活かし、人事労務業務の効率化支援も得意とする、デジタルに強い社労士だ。
この4人に共通するのは、単なる手続き代行屋ではなく、経営者のビジネスパートナーとして伴走する姿勢だ。
成長し続ける会社の共通点:3つの視点
講演では「成長し続ける会社」を、社労士視点から三つの要素で定義した。
1. 採用力:カルチャーフィットかスキルフィットか
最初のテーマは採用における永遠の命題。会社に合いそうな人(カルチャーフィット)か、即戦力になる人(スキルフィット)か。
4人の意見は明確だった。30人規模まではカルチャーフィット重視である。
岡氏は「30人くらいまでは考え方が合うかを重視すべき。創業者と同じ温度感で不安や危機感を持って行動できる、いわゆる右腕のような人を採用することが大事」と語る。
奥村氏は「価値観をすり合わせていくことは、非常に難しいこと。技術や能力だけを基準に採用すれば、即戦力として活躍することはできるかもしれないが、会社の価値観や仕事に対する姿勢が一致しなければ、必ず違和感が残る。」と実感を語った。
カルチャーフィットを見抜く質問として、奥村氏が挙げたのが「最近何に怒りましたか?」だ。「怒りは大事にしている価値観を崩されたときに起こる。怒りのポイントが一緒だと気が合う」という洞察は、採用面接で即使える実践的アドバイスだ。
一方、岡氏は「現職の何が面白いか、いいと思っているか」を聞くという。「今の職場の良さを語れる人は、ネガティブではない。何に居心地の良さを感じているかが分かる」。
中野氏は客観性を重視し、適性検査の導入を推奨。「経営者自身がカルチャーを言語化できていないこともある。客観的な指標で可視化することが重要」と指摘する。

2. 従業員満足度:おすすめの福利厚生
従業員の定着率を上げるための制度について、興味深い提案が続いた。
社員旅行の復権
櫻井氏が推すのは、時代に逆行するようだが「社員旅行」だ。「社員旅行に一緒に行きたいような関係性を築く会社でありたい。」と語る。加えて奥村氏より「給与から月3,000円を控除して積み立て、会社負担と合わせて実施する仕組みを用いている会社などもある」
社長ランチ
中野氏は50人未満の企業に「社長ランチ」を提案する。「夜の飲み会ではなく1〜2時間のランチなら、社長の普段の一面やカルチャーを伝えられる。前職の社長は200人規模まで毎日のように実施していた」。
借り上げ社宅と寄付制度
岡氏は「借り上げ社宅」と「寄付制度」を挙げた。借り上げ社宅は家賃の実質半額補助により住環境が向上し、一度いい場所に住むと離職しにくくなる。寄付制度では、従業員が応援したい活動に月5,000円まで会社が寄付する。「従業員の自発的な社会貢献を会社が支援する。気分がいいし、会社としても多様な社会貢献ができる」。
3. 給与設計:固定残業代は「あり」か「なし」か
最後のテーマは固定残業代。賛否が分かれやすいこのテーマについて、士進会メンバーは全員「あり」の立場だ。
岡氏は「人件費が予算化しやすいのが最大のメリット。また、働き方に応じて固定残業の時間数を調整し、人件費を再配分することもできる」と経営視点での利点を説明。
ただし、奥村氏は重要な注意点を指摘する。「固定残業代を入れるなら、しっかり認められるように時間数や金額を明記し、明細に載せ、就業規則に規定する必要がある。制度設計が不十分なまま『固定残業代を導入しているつもり』になっている企業も多く、その場合は固定残業代として認められず、未払い残業が発生するリスクがある」。
さらに櫻井氏は、「これまでの従業員はそのままで、新規採用者だけに固定残業を付けるのは危険。固定残業がある人は早く帰りたがり、ない人からすると「なぜあの人は固定残業がついているのに残業せずに早く帰るのか」と不公平感を募らせ、退職につながるケースを何度も見てきた」と実務経験に基づく警鐘を鳴らした。

士進会に期待すること:新しい経営支援のかたち
講演を通じて見えてきたのは、経営者と同じ目線で成長を考える社労士の姿だ。
「私たちは手続き代行屋ではなく、一緒にビジネスをやっていくパートナーだと思ってほしい」という櫻井氏の言葉が、士進会の姿勢を象徴している。
士進会は今後、一般社団法人化し、書籍出版やセミナー活動を通じて、社労士業界全体の底上げを目指す。「士進会のメンバーであれば、私が顧問社労士を選ぶ立場でも誰でも超絶おすすめ」と奥村氏が胸を張るように、ここには相互に切磋琢磨し、尊敬し合える仲間が集っている。
若手専門家集団の挑戦は始まったばかりだ。彼らが目指すのは、社労士を選ぶときの新しい基準となるブランド。「士進会に相談すれば間違いない」――そう思ってもらえる存在を目指して、4人は今日も経営者に伴走し続ける。
人事労務の課題に直面している経営者の皆様、価格だけではなく、カルチャーへの理解や専門性の深さで社労士を選んでみてはいかがだろうか。士進会のような新しい選択肢が、あなたの会社の成長を加速させるかもしれない。
採用力を高め、従業員が定着する会社へ
経営者の想いを発信で届ける
カルチャーフィットする人材を惹きつけるには、会社の価値観を言語化し伝えることが不可欠。
月1回の取材で、あなたの経営哲学を「共感を呼ぶコンテンツ」に変えます。