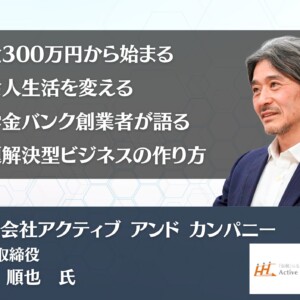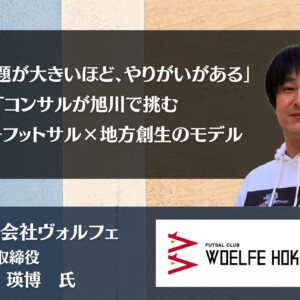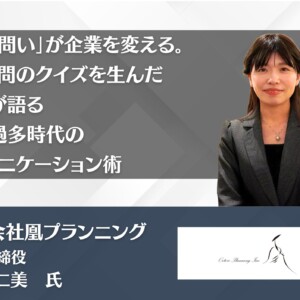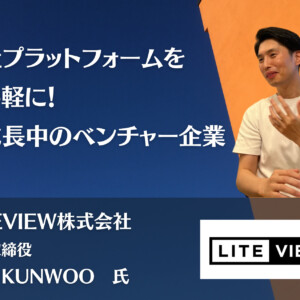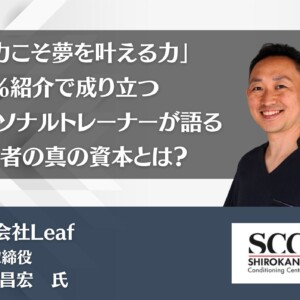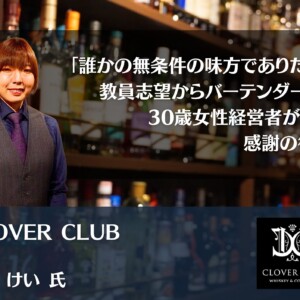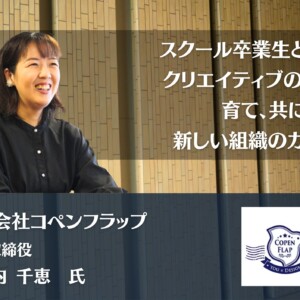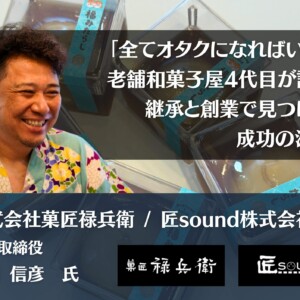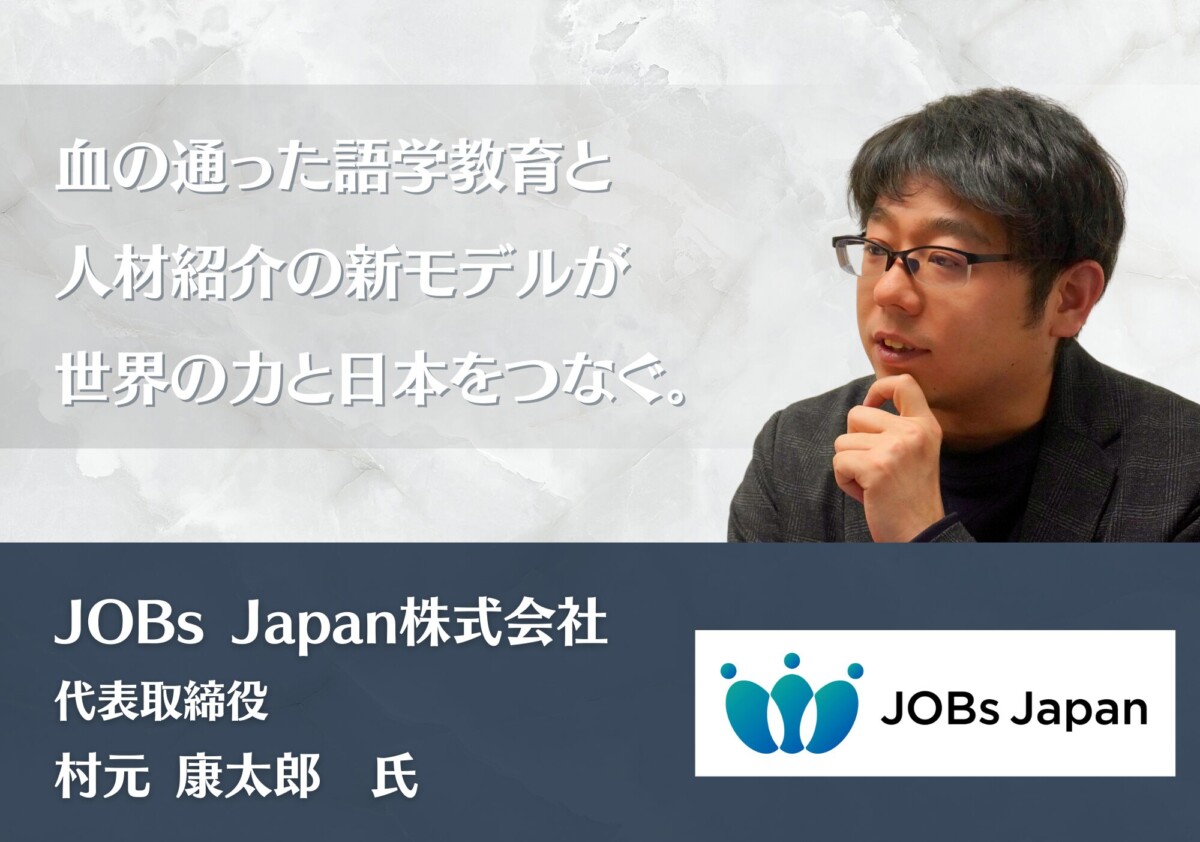
血の通った語学教育と人材紹介の新モデルが、世界の力と日本をつなぐ。|JOBs Japan株式会社
今回紹介するJOBs JAPAN株式会社様は、加速度的に増える国内の外国籍の方の言語習得と就労のサポートを牽引する企業。全世界の優秀な人材が、言葉の壁や文化の壁を乗り越えて活躍できることは、企業にとっても、日本にとっても、何よりその「個人」にとっての理想の姿です。コロナ禍を超えて一気に風景の変わる私たちの世界に、誰よりも早く目を向けて人と社会を繋ぐ、その想いがどこから動き始めたのか、同社代表の村元康太郎様の志に迫ります。
目次
語学と就労、地続きの支援を行う事業モデル

最初に御社の事業内容について教えてください。

事業内容は主に2つに分かれます。1つが、日本語を教えるオンライン型のスクールです。国内外の外国人日本語学習者や、外国人を採用している企業を対象にサービスを提供しています。
もう1つが、人材紹介業です。これも外国籍技術者をはじめとしたエンジニアの転職支援をメインに行っております。

まずはオンラインスクールについてうかがいます。
近年、語学オンラインスクールはニーズも参入企業も増えていると思いますが、御社が提供しているサービスはどのようなものでしょうか。

弊社ではマンツーマン、または1対複数名の少人数クラス制で、skypeなどのオンラインツールを使ってレッスンをしています。先生も生徒も世界中のどこからでもアクセスできます。週に2回、たとえば月曜と金曜の1時間のレッスンを半年続けると、およそ50時間の学習になります。先生とマンツーマンで50時間も話をすると、周囲から見ても語学の上達を感じられる成果が出てきます。50時間のタームで成長を実感して、そこからまた延長して次の50時間でステップアップを、といったような受講ケースが多いです。

かなり実践的に、会話の練習をするということですね。

そうです。中身は会話重視です。私たちの学生時代、特に中高は先生が一方的にしゃべり通しで文法を詰め込まれ、それで実際に話せるようになるのかと言われたら話せないですよね。そういう自分が受けた教育も振り返って、生徒の発話機会が大切だと感じました。そのため、あくまで生徒のアウトプットが主役になるように指導を構築しています。それを実現しようと思うと1対10などの多人数指導では無理があります。多くても生徒3名程にすることで、1人あたりの発話時間を増やし、会話力を伸ばしています。

人数が多いと、自主的に発言する機会もモチベーションも減りますからね。

そうなんです。TOEICのような試験が、日本語版でもあります。そこで高得点を取れる人でも、実際に話してみるとうまく話せないことも多く、それでは本来目指しているはずのゴールに到達できたとは言えません。皆さん、基礎的な文法や単語のインプットはできているのですが、それがアウトプットに繋がっていないんです。そこを何とかすべく、会話に重きを置くという軸を初期から重視しています。
また、企業からのニーズが強いのは、ビジネス現場を想定したカスタマイズレッスンです。一緒に現場で働いてみて、言ったことがうまく伝わっていないと感じる、という声が現場から人事にあがってくるそうです。そこで、人事の方が日本語研修ができるサービスを検索して、我々のような事業者に依頼するという流れが増えています。
ビジネス現場で使える日本語能力があることが、個人が現場で活躍したり、独り立ちしたりという際の鍵になってきます。そこに特化してサポートするという点が、企業の方が興味を持っていただけるポイントとなっています。

ビジネスに特化した語学教育サービスは、まだ少ないのでしょうか。

一般的な他のスクールは、「働く上で必要な会話」はあまり取り扱いません。それよりも、試験の点数を伸ばす支援が目立っていることが多いです。一方で、弊社はビジネス現場で活躍するための語学に焦点を当てています。実際にビジネス経験豊富な講師が教えることで、現場に必要な専門用語までフォローができます。
たとえば、金型メーカーで働くスタッフに求められる日本語と、ITのエンジニアに求められる日本語は全く違いますよね。それなのに、画一的なテキストで全員に指導をしているのが現状です。本来それらはカスタマイズされるべきです。そこで、こういうお客様ならこういうレッスンを入れた方が即効性ありますよね、といった提案をしています。教科書に載っていない、それぞれの職場で必要なことを教える。そこを評価していただいております。

オンライン型を選択された理由はありますか。

教室を持つと、それだけで固定費がかかるので、レッスン料金が高くなるからです。オンライン型にすることで、余分なコストを抑えて、受講していただきやすくしています。会話ができるようになるにはレッスン回数が肝ですが、回数を増やそうと思うとどうしても単価がネックになります。それなら、オンラインにして安価にすることで回数を増やせる方が良いですよね。

提案先は企業さんが相手で、実際に受講するのはそこの企業で働く社員の方という形ですね。

そうです。担当窓口は人事総務の方が多いですね。ただ、最近は現地リクルートも多くなっています。コロナ禍が落ち着いたことで、企業の方も優秀な人材を海外でヘッドハントしてくるようになりました。たとえばベトナムなど、しっかりと専門的な知識を学んだ製造業の方やITエンジニアの方はとても多いですからね。しかし、そうなると現地で働いている方ですから、当然日本語はうまくはありません。ビザの手続きなどで入国から就労まで半年から1年程時間があくので、その間に日本語を上達して来てもらえればベストだなということで、オンラインのスクールを検討する、というケースが増えてきています。
現地にも日本語を教える方はおられますが、ベトナム人がベトナム人に日本語を教えるよりも、日本人で経験と資格を持った人が指導する、という方が日本企業としても受け入れていただきやすいという手応えもあります。

どのような業種の企業からの依頼が多いでしょうか。

今のところ、製造業が1番多いです。国内で若手の技術者を多数採用することは難しくなってきています。次に建設系。施工管理領域や、電気系のエンジニアなど、現場の作業をする方というよりはエンジニア領域に携わる方の採用は各社苦戦しています。大手ならともかく、地域で頑張っている中小企業が、日本語ペラペラの経験あるエンジニアを採用できるかというと難しいことは想像に難くありません。そこで、まずは語学よりも専門知識や経験を優先して採用し、入社が決まってから語学をブラッシュアップできる環境をつくるという方向に舵を取る企業さんが増えています。
製造業はITとは違い、実際のモノや工場などがあるので、日本語の指示が伝わらないと何かあったときの物理的な危険が増加します。ですから、IT系よりも、より語学ニーズが強い傾向があります。

では次に、転職支援サポートについてうかがいます。
こちらも外国籍エンジニアの方を対象とした転職サポートということですね。

そうですね、外国籍ITエンジニアと、製造業エンジニアのご支援をしており、エリアで言うと東南アジアをメインに、欧米、たまにアフリカなど。アジアだとミャンマー・インドネシア・フィリピンなどが多いです。

その土地の方から、直接御社に連絡があるのでしょうか。

弊社の場合は、先の語学スクールの受講生さんでエンジニアをやっているという個人の方が、語学を学んだ先に求職活動をされるというケースがあります。 それから、LinkedInやSNSを使ってリクルーターが「今、こういった求人のポジションがありますが、興味があればぜひお話しましょう」とお声がけをするパターンもあります。

日本語学校は、法人向けの他、個人向けも実施しておられるのですね。

そうですね。先ほどお話ししたのは法人向けで、個人向けは「日本語が勉強したい」という方向けに開いており、そこに申し込みがあり、受講していただいております。

語学レッスンから、就業のサポートまでやられているのですね。
それは紹介する企業さんにとっても安心感がありますね。

そうですね、きちんと意欲的に学んでいて、ある程度基礎が出来上がっているという方が多いので、一般的なエージェントのように、とにかく問い合わせがあった人材をそのまま流すという形にはなりにくいです。スクールで言語を学び、日本文化の基礎理解ができている方、という期待を持ってご相談や紹介を受けていただいています。

外国籍の方を受け入れるのは、言葉が通じるのか、雇ったはいいがコミュニケーションができるのだろうか、と不安になりやすい部分です。そこを2つの事業がシームレスにアシストしているのが素晴らしいですね。

このマーケットはおそらく5年後くらいまでに一気に拡がっていくと思っているのですが、そこまでに弊社でひとつのモデルを確立したいなと思っています。初めは受講生も講師も、紹介のあてなんて何もないところから始まりましたが、チャレンジを重ねて形になってきているところです。
はじまりの一歩は語学交流から

次に、事業をスタートされたきっかけについてお伺いいたします。

2019年の3月、私は新卒で入った会社を辞めて、「これから何をしようかな…」というノープラン状態になっていました。当時25~6歳だった私は迷信的な印象による「とりあえずインドに行けば何かあるかも、一回行っておこうかな」という思い切りで、言語交換のマッチングサービスに登録しました。ヒンドゥー語を学びたい日本人と、日本語を学びたい現地人がマッチングして、会ってみましょうというようなコンセプトのものです。実際それで相手の話を聞くと、日本で働きたいなどの夢をみなさんが持ってらっしゃいました。
ですが、その当時はなかなか勉強ができる手段がありませんでした。ネットや動画で独学でやってみるものの、話せているのかわからない。誰もネイティブチェックをしてくれないのですから当然です。
日本人のネイティブの登録は少なかったようで、私はありがたくも重宝されまして、その代わり、インドを案内してもらいました。

そうして世界に飛び出したわけですね。

3年しか社会人経験もなく、何もわからない領域でしたが、日本人というアドバンテージを活かして何かできるのではと感じました。正直なところ、気合と根性と想いがあればなんとかなりそうだ!とふわっとした考えで最初はスタートしました。
そこから、インドで自分自身が講師となりskypeを使って日本語を教えるようになりました。インドは広く、デリー1都市を見ても広大です。そこに校舎を作って通ってもらうのは現実的ではないなと思い、オンラインを選びました。
ちょうどその頃、インドの通信インフラが地方にも運用され、ネットやスマホの利用者が増えた時期でもありました。

インドで人と出会ったことで、強い印象や、心の動きがあったのでしょうか。

そうですね、学びたくて、何か困っている人がいるなら、できることがあるなと思いました。ちょうど働いていた会社を辞める頃だったので、今の自分のスキルでできることだったら、なんでもやってみようかなと思っていたところに、これならできるかもしれないと思えるもので出会えた感じです。提供したものに対して対価をいただく形にできれば、ビジネスとして成立するな、と舵を切りました。

これをやっていきたいというよりも、「まずできることを提供していこう」と考えられたということですね。
当時の生徒数など、どのくらいの規模だったのでしょうか。

最初は10~20名程です。日本在住のインド人の方もいましたよ。口コミで広がっていく形で、こういう人がいるよと紹介いただいて繋がっていきました。当時はまだインフラができているさなかでしたから、停電でオンラインミーティングに入れないときもありました。日本だとクレームになるところだと思いますが、当時のインドの文化的にはそれでも成立していましたね。

直接ご自身で教えられていた期間はどのくらいでしょうか。

1年もなかったと思います。日本語教師の資格を持っている方に担当してもらうようになり、そのタイミングで自分は現場を離れました。そういう形の方が、専門知識を体系的に教えられるのは間違いなかったので。

業務委託のような形ですか。

そうです、時給で、1ヶ月間に何レッスンを担当いただいたか月末に報告していただいて、支払いをするという形でした。その頃はもう私は日本にいて、先生たちはインドに限らず世界中から参加してもらっていました。
その後会社を設立し、そうこうしている内に2020年の3月です。会社として動き出して半年後にコロナ禍が来ました。全世界がオンラインにシフトした時期です。そんな時期的なラッキーも重なり、企業からのお問い合わせも増えました。
そこで生き残れたことで、今は「オンライン研修」で検索すると、弊社の社名が上位に出てくるようになりました。
働くことの「自由」を目指して

次は社内の動きについてうかがいます。
まず、御社の働き方の特徴について教えてください。

オンライン化を推進することで可能にしている、正社員と複数の業務委託の方を中心としたチーム作りが特徴です。
もう1つ、外国籍人材の活躍する組織作り、という点は意識しています。

オンラインの働き方を構築される上で苦労された点や、工夫された点を教えてください。

元々サービスを創る段階で先ほどのようにオンラインの強みを感じてスタートしていました。そこから、どこにいても仕事ができる、場所に縛られないというのが、創業時のキーワードになりました。
完全に「出勤」という余分な時間をなくそうと思うと、お問い合わせから、受注・提供まで全てオンラインで完結する必要があります。語学スクールも人材紹介も、無形商材としてオンラインで提供できることにはこだわっています。事業内容を考える時に、常にそこを軸にしていました。

その軸が強くあるので、それに合わせて事業が選定できるのですね。

毎日会社に行かないと仕事ができない、という仕事の常識には大きな疑問がありました。前職はIT企業でスマホ向けのアプリを販売していたのですが、使う人たちはスマホ1つでサービスを受けられるのに、提供している私たち営業は毎日9時出社。このヘンテコ感というか、ITなのにアナログだな…という疑問がありました。

実際にご自身が働いて感じた疑問がビジネスモデルになった。

そうですね。基本的にオンラインでできないことには足は突っ込まないぞ、と言いますか、場所や時間に縛られてしまう働き方には興味が持てないですね。可能な限りオンラインで完結できるような組織体制であったりサービス提供ができるよう進めていきます。教材ひとつとっても、データで作ってPDF化して送信してと、全部オンラインで完結させています。
あとはご自身で好きなように印刷するなり使ってくださいねというオペレーションです。

オンラインと実際に出社してもらうのとでは伝わり方が変わってしまうという懸念もよく耳にします。
その点はいかがでしょう。

弊社では全く問題ないです。全世界にいる講師に対して、講師をマネジメントする人が1人福岡にて、リモートで働いてもらっています。
マニュアルが整備されているので、質を担保しやすいですし、定期的にZoomミーティングもしているので、直接会わないことによる問題は特にありません。生徒の指導記録もスプレッドシートで管理しています。もし指導講師が変わっても引継ぎがスムーズですし、マネージャーもそれを見て学習進捗を把握できますので、むしろ紙ではなくオンライン化している方が良いですね。

基本的には担任の先生は固定なのでしょうか?

そうです。 1人の講師がその生徒を最初から最後まで担当する専任制にしています。講師が毎回変わる仕組みだと、レッスンのたびに自己紹介の挨拶や次回継続勧誘のアナウンスで時間が削れてしまいます。最初にお伝えした会話力を伸ばすことにちゃんとコミットしようと思ったときに、そういう障害を取り除く必要があると感じ、専任制にしました。

初対面の人が相手だと言語の壁はもちろん、会話自体弾まないこともありえますよね。

その通りです。そこを超えて打ち解けられるのが「いつもの先生」の強みです。先生への信頼がすごいんですよ。プライベートの恋愛相談や会社の不満なんかをする方もいます。上司には言えない悩みがここで吐露されることもあります。もちろん、法人契約があっても、そこで聞いた受講者の個人的な情報は外に出すことはしません。個人の感情の部分は、信頼して話してくれていることですからね。

業務委託メンバーを中心としたチーム作りについて教えてください。

ポリシーとして、少数の正社員が外部のメンバーとうまく協働しながら、成果をあげていくということを掲げています。
弊社はITエンジニア分野は「IT JOBs inJapan」と、製造業エンジニアの紹介は「Monozukuri JP」と銘打ってサービスを展開しております。そこにそれぞれ、事業責任者兼マネージャーとして正社員がいます。そのチーム内に業務委託の方にメンバーとして入ってもらっていまして、その方達はLinkedInなどをを活用して主にエンジニア人材へのスカウトをしています。そして転職希望の人材がいた場合は、マネージャーが面談をするというフローです。このように、正社員であるマネージャーと業務委託メンバーの体制を組んでいます。そのため、チーム作りを目的とした業務委託メンバーの採用についても日々行なっています。これもフルリモート運営や、フリーランス時代だからこそできる働き方、チーム作りであると思っています。

なるほど。そういった希望のある方はすぐに見つかるものなのでしょうか。

業務委託メンバーの採用にしても試行錯誤の連続ですね。専門のSNSサービスを経由したり、現地在住の駐在コミュニティサイトなどの繋がりもあります。海外駐在の方のご家族で、バイリンガルの日本人の方などはたくさんおられます。そういった方にオファーする経路を探したときに、現地コミュニティの存在を知りました。あとは、主婦でパートを探している人向けのWEBメディアなどもありますね。情報を集めてアンテナを張っていると、今では求人の肌感覚のようなものも身につきました。こういう人材が欲しいなら、この媒体でこのくらいの期間掲載すれば、何人ぐらいの応募があって、何人の採用が見込めるな、というような。
自分たちのサービスをきちんと提供するために求人・採用ノウハウを積み上げてきましたが、今後はこういったものを外部にも提供できたらいいなと思っています。

このフリーランス時代に、そのようなニーズは確実に存在しますね!

自分自身、業務委託メンバーを探す際も、オンラインでのマッチングで良い人を見つけ出す力は磨いていきたいと思っています。フリーランスを募集するような匿名のサイトであっても画面の向こう側の人間をきちんと意識して関われる人は、実際に講師としても優秀ですし、逆にスキルや資格だけでジャッジすることは避けねばならないというのも実感としてあります。外側のことよりも、自分たちのサービスの理念への共感度合いなど、レジュメにでてこない部分を大切にしたいですね。
仕事を探しているエンジニアと英語で話すにしても、今の生活や本人の潜在的な希望を深掘りして未来を提示してあげられるような人は、信頼もおかれますし、その人間性の部分に資格の有無は関係ありません。
全世界の人がイキイキと活躍できる未来へ

ご自身のグローバルな視野や発想はどこにルーツがありますか。

海外やグローバルを意識したのは大学時代ですね。18歳で初めてオーストラリアに行って、グローバルな価値観って面白いと感じたのを覚えています。
事業を始めてからは、ニッチ市場で認知されることの重要性も強く感じるようになりました。ブランドもリソースもない自分がお客様に選ばれるには、広く浅くを狙うのではなく、10人中たった1人でも熱狂的なファンになってもらうことが重要だという意識がありました。
それらが繋がって、結果的に外国籍のエンジニアの方、というポイントが絞れたのだと思います。そこを軸に、また別の事業もやりたいとは思っています。アクセルの踏み方を間違えないように気を付けながら、慎重に挑戦していけたらいいですね。

4期目を迎える御社ですが、短期的にはどのようなビジョンを想定しておられますか。

まずは、業界内の日本トップというところは押さえたいですね。日本語オンラインスクールはニッチな分、日本語をオンラインで学びたい人や企業さんには少しずつ知名度が出てきましたが、外国籍エンジニアの人材紹介の方は今後の伸び代が非常に大きいと考えています。わかりやすい指標でいえば、キーワード検索で1件目に出てきてほしいでし、外国籍のエンジニアを採用したいという場合は、JOBs Japanに相談すれば、日本語教育も採用支援も一貫してやってもらえるという認知を作りたいです。
そして、グローバルニッチを押さえておきたいです。現在、他社さんで欧米圏からの留学生を受け入れて、日本語を教わったり文化観光体験が申し込めるようなスクール事業を運営しておられるところがあります。ニッチではありますが、スクールの歴史が長く知名度があり、そこと提携して学生さんが住むホストファミリーなどの受け入れ先との橋渡しをするような事業や、文化観光体験のニーズに対しても今後対応検討していきたいと考えているところです。
欧米圏の中でも特にフランスは全世界のアニメ消費量がアメリカに続き2位で、現地での日本の株が上がっているという背景もあります。また日本人が学びたい言語の TOP3にフランス語が入っているんです。パリのオリンピックもありますから、お互いに交流できるチャンスになると思っています。

次に、長期的に挑戦したいと考えておられることを教えてください。

正直、中長期的な見通しはまだはっきりしていない部分も多いです。2~3年以上先をどうやって生き残っていくかは、まだわかりません。とにかく目先のIT、製造業の外国籍エンジニアという人材紹介でのリーチトップを目指すことに尽力しながら、そこで見えてくる新しいニーズを吸い上げて運営していければと考えています。
どのような道を進むとしても、「日本人も外国人も関係なく、全世界の人々がイキイキと活躍できる」というミッションからは外れたくはありません。背景にもよりますが急に物販や不動産販売をしたりとか、そういうのは理念に反しますから、興味がないですね。
もし新しい事業を進めるとしても、教育を軸に、ビジョンに繋がる部分を形にしていきたいです。

新しい時代に、世界中の人のためになる事業をどんどん創り出していく。御社のそんなミッションをこれからも応援させていただきます。国内の就労環境に早くサポートが追いつき、外国の方も私たち日本人も、より良く協働できる未来を願っております。本日はありがとうございました!
コントリ編集部からひとこと
この度は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。創業当時からオンラインでのビジネスモデルに目をつけられ、今までに誰も経験したことのないコロナ禍さえも味方につけられた村元社長からは、外側からは見えない内側に燃えるような情熱を感じました。今後、日本で活躍する外国の方の数は増えていくと思います。そのような方々の活躍の裏には必ずJOBs Japanさんがいる。そんな状況をいち早く作っていただきたいと思いました。
今回の記事を通して、JOBs Japanさん、そして、村元さんの魅力がたくさんの方に伝わってくれたら嬉しいなと思っております。
ありがとうございました。
ギャラリー







プロフィール
JOBs Japan株式会社 代表取締役
村元 康太郎
石川県小松市出身。語学力向上のためフィリピンとアメリカにて留学を経験。その後、インターンシップや法人向けITサービスの営業などで経験を積み、退職後のインド訪問で日本語教育の需要を発見し、「日本語オンラインスクール合同会社」を2019年に創業。オンラインで日本語教育を提供し、1000名以上が受講。2021年からは「JOBs Japan株式会社」として、外国籍ITエンジニアの転職支援を展開し、15カ国以上の国籍のエンジニアを支援している。
【会社概要】JOBs Japan株式会社
| 設立 | 2019年9月3日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿2-11-7 第33宮庭ビル5階 |
| 従業員数 | 35名 |
| 事業内容 | ・個人・法人向け日本語オンライン教育サービス「日本語オンラインスクール」の運営 ・転職支援サービス「JOBs Japan」の運営 ・外国籍ITエンジニア特化の転職支援サービス「IT JOBs in Japan」の運営 (有料職業紹介免許番号 13-ユ-313374) |
| HP | https://nihongo-jobs.com |
御社の想いも、
このように語りませんか?
経営に対する熱い想いがある
この事業で成し遂げたいことがある
自分の経営哲学を言葉にしたい
そんな経営者の方を、コントリは探しています。
インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。
条件は「熱い想い」があることだけです。
経営者インタビューに応募する
御社の「想い」を聞かせてください。
- インタビュー・記事制作・公開すべて無料
- 3営業日以内に審査結果をご連絡
- 売上規模・業種・知名度は不問
※無理な営業は一切いたしません
発信を自社で続けられる
仕組みを作りたい方へ
発信を「外注」から「内製化」へ