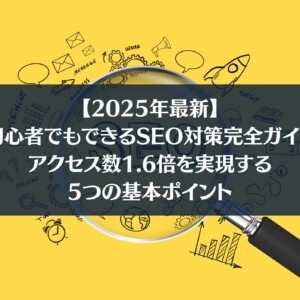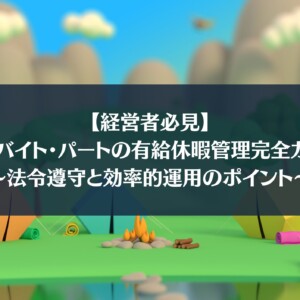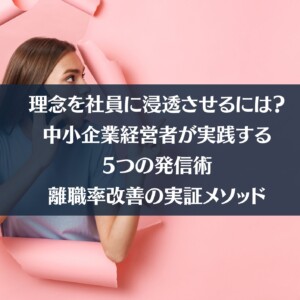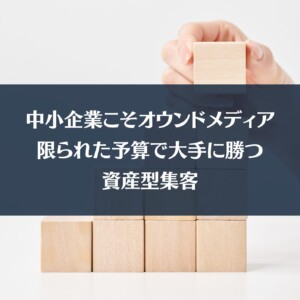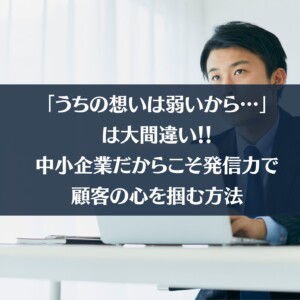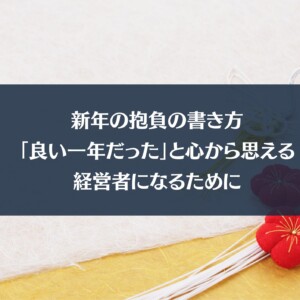【社労士監修】固定残業代のメリット・デメリットを正しく理解して賢い判断を
毎月の人件費が読めない、残業代の計算が煩雑で時間がかかる——そんな悩みを抱える中小企業の経営者の方は少なくないでしょう。固定残業代の導入を検討されている方も多いかもしれません。
しかし同時に、「ブラック企業と思われないだろうか」「労働基準監督署から指摘を受けるのでは」という不安もあるのではないでしょうか。従業員を大切にしたい想いと、経営の効率化を実現したいという願い。その狭間で悩まれる経営者の心情、よくわかります。
本記事では、固定残業代の基本的な仕組みから、企業側と従業員側それぞれのメリット・デメリット、適法に運用するための具体的なポイントまでを解説していきます。自社にとって最善の選択をするための判断材料として、ぜひお役立てください。
固定残業代の基本と自社への適用可能性
固定残業代という言葉を耳にしたことがある経営者の方は多いはず。しかし「自社で導入しても大丈夫なのだろうか」という不安を抱えていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。
ここでは固定残業代とは何かという基本的な仕組みから、みなし労働時間制との違い、適法に運用するための条件、そして導入に向いている企業と向いていない企業まで、実務的な視点で解説していきます。法律用語ではなく、日常的な言葉でお伝えしますので、「うちの会社ではどうなんだろう」と考えるきっかけにしていただければ幸いです。
固定残業代とは何か、仕組みを理解する
固定残業代とは、給与の中に残業代をあらかじめ含めておく仕組みのこと。みなし残業代や固定残業手当とも呼ばれており、実際の残業時間にかかわらず、毎月一定額の残業代を支給する制度なんですね。
具体的な例を見てみましょう。たとえば月給30万円の内訳を「基本給25万円+固定残業代5万円(月45時間分)」と設定したとします。この場合、実際の残業が30時間でも40時間でも、その月の残業代として支給されるのは5万円です。
ただし重要なのは、45時間を超えた分については別途追加で支払う義務があるという点。この制度を導入する企業側のメリットとしては、毎月の人件費が予測しやすくなることが挙げられます。給与計算の効率化にもつながるでしょう。
一方で従業員側から見れば、残業が少ない月でも一定額が保証されるという安心感がある反面、長時間労働を前提とした制度ではないかという不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
固定残業代は労働基準法で定められた制度ではなく、企業が任意で導入できる給与体系の一つ。だからこそ適切に運用しないと、後々大きなトラブルにつながる可能性もあるのです。従業員の働き方を守りながら、経営の効率化も実現する。そんなバランスの取れた制度運用を目指していただきたいと思います。
みなし労働時間制との違いを明確にする
固定残業代とみなし労働時間制は、よく混同されがちな制度。どちらも「残業代」に関わる仕組みという点では共通していますが、実は根本的に異なる制度なんですね。
みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間働いたものとみなす制度のこと。労働基準法第38条の2から38条の4に定められており、「事業場外みなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の3種類があります。導入には労使協定の締結や労働基準監督署への届出が必要となるケースもあるでしょう。
一方、固定残業代は給与の支払い方法の一つに過ぎません。実際の労働時間は通常どおり管理する必要がありますし、固定残業時間を超えた場合には必ず追加の支払いが求められます。つまり労働時間の把握を省略できる制度ではないということなんです。
実際の運用場面で考えてみましょう。みなし労働時間制を適用している従業員の場合、何時間働いても「みなし時間」分の給与のみとなります。対して固定残業代を適用している従業員は、タイムカードなどで労働時間を記録し、固定残業時間を超えたら追加支払いを行う必要があるのです。
この違いを理解せずに導入してしまうと、「勤怠管理をしなくてもいい」という誤った認識につながりかねません。経営者として、制度の本質をしっかり把握しておくことが大切だと思うのです。
従業員からも「残業代が固定だから、何時間働いても同じなのか」という疑問の声が上がることがあるかもしれませんね。そんなとき丁寧に説明できるよう、両制度の違いを明確に理解しておきましょう。
| 比較項目 | 固定残業代 | みなし労働時間制 |
|---|---|---|
| 法的根拠 |
法律上の特別な定めはなし
給与の支払い方法の一つとして運用
厚生労働省の指針に基づく
|
労働基準法第38条の2~第38条の4に規定
事業場外みなし労働時間制
専門業務型・企画業務型裁量労働制
|
| 労働時間管理 |
通常通り労働時間を管理する必要あり
タイムカード等で記録必須
労働時間の把握を省略できない
|
実際の労働時間の算定が困難な場合に適用
あらかじめ定めた時間労働したとみなす
労働時間管理が簡略化される
|
| 残業代計算 |
固定残業時間を超えた場合は追加支払い必須
最低保証として機能
実労働時間が少なくても固定額を支給
|
みなし時間分の給与のみ原則支給
実労働時間に関係なく一定額
深夜・休日労働は別途支給
|
| 導入手続き |
就業規則や雇用契約書への明記
従業員への周知徹底
労基署への届出は不要
|
労使協定の締結が必要
労働基準監督署への届出
種類により手続きが異なる
|
| 適用対象 |
適用業務に限定なし
全業種で導入可能
企業の判断で適用可
|
法定された業務に限定
事業場外労働・専門業務型(20業務)
企画業務型など厳格な要件あり
|
適法な運用に必要な3つの条件
固定残業代を適法に運用するためには、押さえておきたいポイントが3つあります。これらを守らないと、制度そのものが無効と判断され、未払い残業代の請求リスクにつながることも。
1つ目は、就業規則や雇用契約書への明記です。 「固定残業代として月○○円を支給する」「これは月○○時間分の時間外労働に相当する」という内容を、誰が見ても理解できる形で記載しなければなりません。曖昧な表現では、後々「聞いていなかった」というトラブルの原因になるでしょう。労働基準法第15条では、賃金に関する事項を書面で明示することが義務付けられています。
2つ目のポイントは、基本給との明確な区別。 給与明細を見たときに、基本給と固定残業代がそれぞれいくらなのか、はっきりわかる状態にしておくことが求められます。「月給30万円(固定残業代含む)」だけでは不十分で、「基本給25万円、固定残業代5万円」と分けて表示する必要があるのです。
そして3つ目が、超過分の支払い義務。 これが最も重要といっても過言ではありません。固定残業時間を超えて働いた場合は、必ずその分の追加残業代を支払うこと。この義務を怠ると、固定残業代制度全体が労働基準法違反と判断される可能性が高くなります。
実際の現場では、毎月の勤怠管理をしっかり行い、固定残業時間と実際の残業時間を比較する作業が欠かせません。タイムカードや勤怠管理システムを活用して、正確な記録を残していくことが大切ですね。
従業員を大切にする想いがあるからこそ、きちんとしたルールに基づいた運用を。それが経営者としての責任であり、会社と従業員双方を守ることにつながるのではないでしょうか。
導入に向いている企業と向いていない企業
固定残業代は、すべての企業に適した制度というわけではありません。自社の業務実態や従業員の働き方を見極めて、導入の是非を判断することが重要なんですね。
導入に向いているのは、残業時間が比較的安定している企業です。 たとえば月によって多少の変動はあっても、おおむね一定の範囲内に収まっているような職場。こうした企業では人件費の予測がしやすくなり、給与計算の効率化というメリットを実感しやすいでしょう。IT企業のエンジニア職や、企画・マーケティング部門など、プロジェクトベースで業務を進める職種で活用されているケースも多く見られます。
なお、労働基準法第36条では、時間外労働の上限を原則として月45時間・年360時間と定めていますので、固定残業時間もこの範囲内に設定するのが安全です。
一方、注意が必要なのは繁閑差が激しい企業。 飲食業や小売業、イベント関連業など、季節や曜日によって業務量が大きく変動する業種では、固定残業代の設定が難しくなります。繁忙期に固定残業時間を大幅に超えてしまうと、結局は追加の残業代支払いが発生し、制度のメリットが薄れてしまうことも。
また従業員が10名以下の小規模企業の場合、一人ひとりの業務内容や労働時間が大きく異なることが多いもの。そうした状況では、固定残業代を一律に適用するより、個別に対応した方が適切かもしれませんね。
導入を検討する際は、過去半年から1年分の残業時間データを分析してみることをおすすめします。毎月の残業時間の平均値や変動幅を把握すれば、固定残業時間をどう設定すべきか、そもそも導入すべきかどうかが見えてくるはずです。
「うちの会社には合わないかもしれない」そう感じたら、無理に導入する必要はありません。従業員の働き方に合った、最適な給与体系を選択していただきたいと思います。
企業と従業員それぞれのメリット・デメリット
固定残業代の導入を検討する際、経営効率だけを優先するわけにはいきません。働く人たちの生活や気持ちに寄り添いながら判断を下したい。そんな想いを抱く経営者の方々にこそ、読んでいただきたい内容です。
企業側と従業員側、双方の視点からメリットとデメリットを整理していきます。制度導入の判断材料として、ぜひお役立てください。
人件費管理と給与計算がシンプルになる利点
毎月変動する残業代の計算に追われる日々。労務担当者の負担を、少しでも軽くしてあげたいと考える経営者の方は多いのではないでしょうか。
固定残業代を導入すれば、実際の残業時間にかかわらず毎月一定額を支給するため、人件費の予測が格段に立てやすくなるんです。資金繰りの計画も組みやすく、経営の安定化につながるでしょう。給与計算の手間も大幅に削減できます。
特に小規模企業では、限られた人員で多くの業務をこなしているという現実がある。毎月細かく残業時間を集計し、割増率を計算する作業から解放されれば、より戦略的な業務に時間を使えるようになる。これは経営にとって、決して小さくない価値といえるのではないでしょうか。
全従業員分集計
割増率を計算
(通常25%・深夜50%等)
残業代を算出
反映・確認作業
定額支給
超過した分のみ確認
追加分のみ計算
従業員の給与が安定し生活設計しやすくなる
一方、従業員の立場から見るとどうでしょう。毎月の収入が安定するという点は、大きな安心材料になります。残業の多い月も少ない月も、一定額が確実に支給されるからです。
この収入の安定性は、住宅ローンを組む際の審査でもプラスに働くことがあるんですね。金融機関は安定した収入を重視しますから、変動の少ない給与体系は評価されやすいものです。生活設計も立てやすくなり、将来への不安も和らぐでしょう。
ただし、これはあくまで制度が適切に運用されている場合の話。固定残業時間を大幅に超える長時間労働が常態化していたり、追加の残業代が支払われなかったりすれば、従業員にとってのメリットは失われてしまう。経営者として、そこは忘れてはならない視点ですね。
人件費増加や長時間労働を招くリスク
メリットがある一方で、率直にお伝えしなければならないリスクも存在します。
固定残業時間内であれば追加の残業代が発生しないため、管理職の中には「この範囲内なら働かせても問題ない」という意識が生まれてしまう危険性がある。結果として長時間労働を助長し、従業員の健康や職場の雰囲気を損なう恐れがあるのです。
また繁忙期以外は残業がほとんどないという職場では、固定残業代分の人件費が常に発生し続けるため、かえってコスト負担になってしまうことも。業務の波が大きい業種では特に、導入前に年間を通じた残業の実態をしっかり把握しておく必要があるでしょう。
「人件費の削減」を目的とした安易な導入は、長期的には企業にとってもマイナスになりかねません。
求人時の印象と従業員のモチベーションへの影響
求人票に「固定残業代込み」と記載すると、どうしても一定数の求職者から敬遠されてしまう現実があります。「残業が前提の職場なのでは」「ブラック企業かもしれない」といった懸念を抱かれやすいんですね。
優秀な人材を確保したいと考えている経営者の方にとって、これは見過ごせない問題でしょう。
さらに、すでに働いている従業員のモチベーションにも影響しうる点には注意が必要です。制度の趣旨が正しく理解されないまま導入すると、「会社は残業代を抑えたいだけなのでは」という不信感を生んでしまいかねません。
イメージ面でのデメリットは、数字では測れないものの、企業の持続的な成長には大きく関わってくる要素。丁寧な説明と誠実な運用によって、従業員との信頼関係を保つ努力が欠かせないのです。
こうした双方の視点を踏まえながら、自社にとって本当に固定残業代が適しているのか。従業員の幸せと企業の成長、その両立を目指す判断をしていただきたいと願っています。
トラブルを防ぐ導入手順と運用のポイント
毎月の人件費が読めない、残業代の計算が煩雑で時間がかかる——固定残業代の導入を検討されている経営者の方は、こうした課題を抱えておられるのではないでしょうか。効率化を図りたい一方で、「労働基準監督署から指摘を受けるのでは」「従業員に誤解されないだろうか」という不安もあるはず。
そんな経営者の想いに寄り添いながら、ここではトラブルを未然に防ぐための具体的な手順と、長く安定して運用していくためのポイントを整理していきます。正しい手順を踏めば、従業員との信頼関係を保ちながら、制度の恩恵を受けることができるのです。
導入プロセスは、現状把握から制度設計、従業員への説明、そして運用後の継続的な見直しまで、いくつもの重要な段階があります。一つひとつ丁寧に進めていくことで、安心して制度を運用できる体制が整うでしょう。
現状の残業実態を把握し適切な時間数を設定する
「まず何から始めればいいのか」——そんな疑問をお持ちの経営者も多いはず。導入の第一歩は、自社の残業実態を正確に把握することから始まります。
過去3〜6ヶ月程度の残業時間データを集計してみてください。部署ごと、職種ごとに平均値や最大値を確認することで、実態が見えてきます。この作業を怠ると、後々大きなトラブルの種となりかねません。
たとえば実際の残業が月60時間なのに30時間で設定すれば、毎月追加支払いが発生してコスト削減になりません。逆に10時間程度なのに45時間で設定すれば、過剰な人件費負担を背負うことに。データに基づいた冷静な判断こそが、制度成功への第一歩となるのです。
就業規則への明記と従業員への丁寧な説明
データ分析が終われば、次は制度の土台づくり。就業規則と雇用契約書への明確な記載が欠かせません。
「基本給20万円、固定残業代5万円(月30時間分)」という形で、誰が見ても理解できる表現を心がけましょう。曖昧な記載は、後のトラブルの元凶となります。
しかし、書類を整えるだけでは不十分です。従業員への丁寧な説明こそが、制度成功の鍵を握っています。なぜこの制度を導入するのか、従業員にとってどんなメリットがあるのか、固定時間を超えた場合はどう対応するのか——こうした点を誠実に伝えていく姿勢が求められます。
説明会の開催や個別の質問対応など、コミュニケーションに時間をかける価値は十分にあるでしょう。従業員の理解と納得があってこそ、制度は健全に機能していくものです。
-
基本給額の明記必須
(固定残業代を除いた額) -
固定残業代の金額必須
(月額〇万円と明確に記載) -
対象時間数の明示必須
(月〇時間分と具体的に記載) -
超過時の取扱い明記必須
(超過分は別途支給する旨) -
制度の有効期間
(見直し時期の設定)
-
制度導入の目的・背景説明
(なぜ導入するのか) -
従業員のメリット説明
(収入安定化など) -
固定時間内でも減額なし
(残業が少なくても支給) -
超過分の支給方法説明
(計算方法と支払時期) -
質問・相談窓口の案内
(個別相談の受付体制)
- 固定残業時間は月45時間以内に設定することが推奨されます(36協定の限度時間)
- 基本給と固定残業代を明確に区分して表示することが法的要件です
- 給与明細にも固定残業代の金額と時間数を明記する必要があります
- 従業員説明会の開催記録や質疑応答の内容を文書化しておくことを推奨します
固定時間を超えた分の残業代を確実に支払う
制度を運用し始めてからが、本当の勝負です。固定残業時間を超えて働いた場合、追加の残業代支払いは絶対に欠かせない原則。この点を怠れば、制度全体が違法と判断されるリスクが生じてしまいます。
タイムカードや勤怠管理システムを活用し、正確な労働時間を記録してください。毎月の集計を確実に行い、固定時間を超過した従業員には翌月の給与で漏れなく追加支払いを実施することが重要です。
給与明細にも配慮が必要となります。基本給と固定残業代を分けて表示し、当月の実労働時間も記載する。こうした透明性の高い運用が、従業員の信頼感を高め、長期的な信頼関係の構築につながっていくのではないでしょうか。
違法と判断される主要なケースを知っておく
「気づかないうちに法律違反をしていた」——そんな事態を避けるため、違法とされる代表的なパターンを押さえておきましょう。経営者としての大切なリスク管理です。
まず「基本給との区別が不明確」なケース。給与明細で分けて表示せず、総額のみ記載している状態は危険です。次に「就業規則や契約書への記載がない」場合。口頭での合意だけでは、法的に有効とは認められません。
三つ目は「固定時間を超えた分の未払い」。これは最も深刻な違反といえるでしょう。さらに「最低賃金を下回る設定」も要注意です。固定残業代を除いた基本給部分が、地域の最低賃金を下回っていれば違法となってしまいます。
こうした主要なケースを頭に入れておくだけでも、大きなトラブルを避けられるはず。知識は最大の防衛策なのです。
| 違法パターン | 具体例 | 発生リスク |
|---|---|---|
|
1
基本給との区別不明確
|
よくある違反例
給与明細に「月給25万円(固定残業代含む)」とだけ記載し、内訳が不明な状態
|
想定されるリスク
固定残業代が無効と判断
全額が基本給とみなされる 未払い残業代の請求対象 |
|
2
就業規則・契約書への記載なし
|
よくある違反例
口頭で「残業代込みで」と説明するだけで、書面による明確な合意がない状態
|
想定されるリスク
労働契約として無効
労基署からの是正勧告 従業員とのトラブル発生 |
|
3
固定時間超過分の未払い
|
よくある違反例
月20時間分の固定残業代を設定しているが、実際は月30時間働かせて追加支払いなし
|
想定されるリスク
労働基準法37条違反
最大3年分の遡及請求 刑事罰の可能性 |
|
4
最低賃金違反
|
よくある違反例
固定残業代を除いた基本給部分が、地域の最低賃金×所定労働時間を下回っている状態
|
想定されるリスク
最低賃金法違反
差額の支払い義務 企業イメージの悪化 |
定期的な見直しで制度を実態に合わせる
「導入したら終わり」ではありません。制度は生き物のようなもの。環境の変化に応じて、柔軟に調整していく必要があるのです。
年に1回程度は残業実態を確認し、固定時間の設定が適切かどうかを見直してください。事業環境の変化や業務内容の変更によって、当初の想定とは状況が変わっているかもしれません。
実際の残業が固定時間を大きく上回る状態が続いているなら、業務効率化や人員配置の見直しを検討する時期でしょう。逆に大幅に下回っているなら、固定時間数の調整も視野に入れてよいはずです。
柔軟に制度を調整していく姿勢こそが、従業員を大切にする経営者の証。定期的な見直しを通じて、自社に本当にフィットした制度へと育てていっていただきたい——そう願っています。
まとめ
ここまで固定残業代の仕組みやメリット・デメリット、適法な運用方法について詳しく解説してきました。最後までお読みいただき、ありがとうございます。経営の効率化と従業員への想い、その両立を目指す経営者の皆様にとって、この記事が判断の一助となれば幸いです。改めて、本記事の重要なポイントを3つにまとめてご紹介します。
- 固定残業代は人件費の予測可能性を高め給与計算を効率化できる一方で、適法な運用には基本給との明確な区別、就業規則への明記、超過分の確実な支払いという3つの条件を満たす必要がある
- 企業側には業務効率化のメリットがあり従業員側には収入安定のメリットがあるが、長時間労働の助長や求人時のマイナスイメージというデメリットも存在するため、自社の残業実態を分析し導入の適否を慎重に判断することが重要である
- 制度導入後も定期的な見直しを行い実態に合わせて調整していく姿勢が、従業員との信頼関係を保ちながら制度を健全に運用していくための鍵となる
固定残業代は、すべての企業に適した万能な制度ではありません。しかし正しい知識に基づいて適切に運用すれば、経営の効率化と従業員の生活安定の両立を実現できる有効な選択肢となります。大切なのは、法律を守ることはもちろん、従業員一人ひとりの働き方や生活に真摯に向き合う姿勢です。もし導入に不安を感じたら、社労士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。あなたの会社と従業員の皆様にとって、最善の選択ができることを心から願っています。
●● この記事の監修者 ●●

田渕花純 – Kasumi Tabuchi –
KT社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士。国内・外資系航空会社を経て、化粧品販売業に従事。その後、大手社会保険労務士法人にてキャリアを積み、スタートアップ企業や建設業向けの労務手続きを専門的に担当。現在は「ヒトの力で企業の未来を切り開く」という理念のもと、会社設立時の労働保険・社会保険申請業務、建設業の労災保険手続きなど、事業主が安心して本業に専念できるよう丁寧かつスピーディなサポートを提供している。社会保険手続き、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングなど幅広い業務に精通。