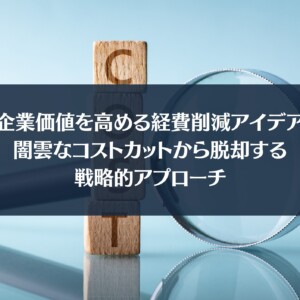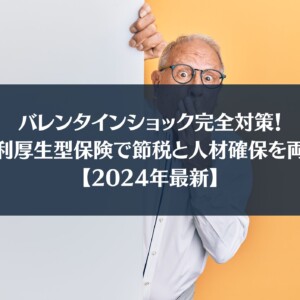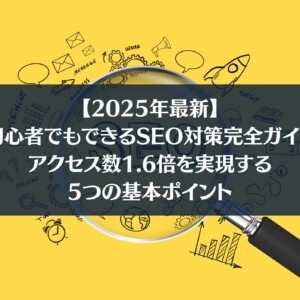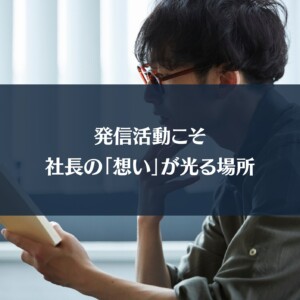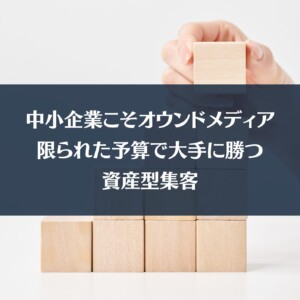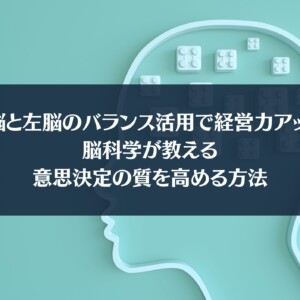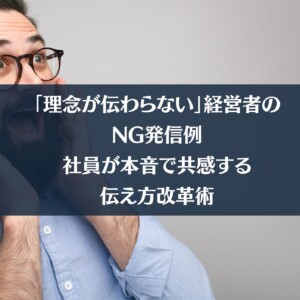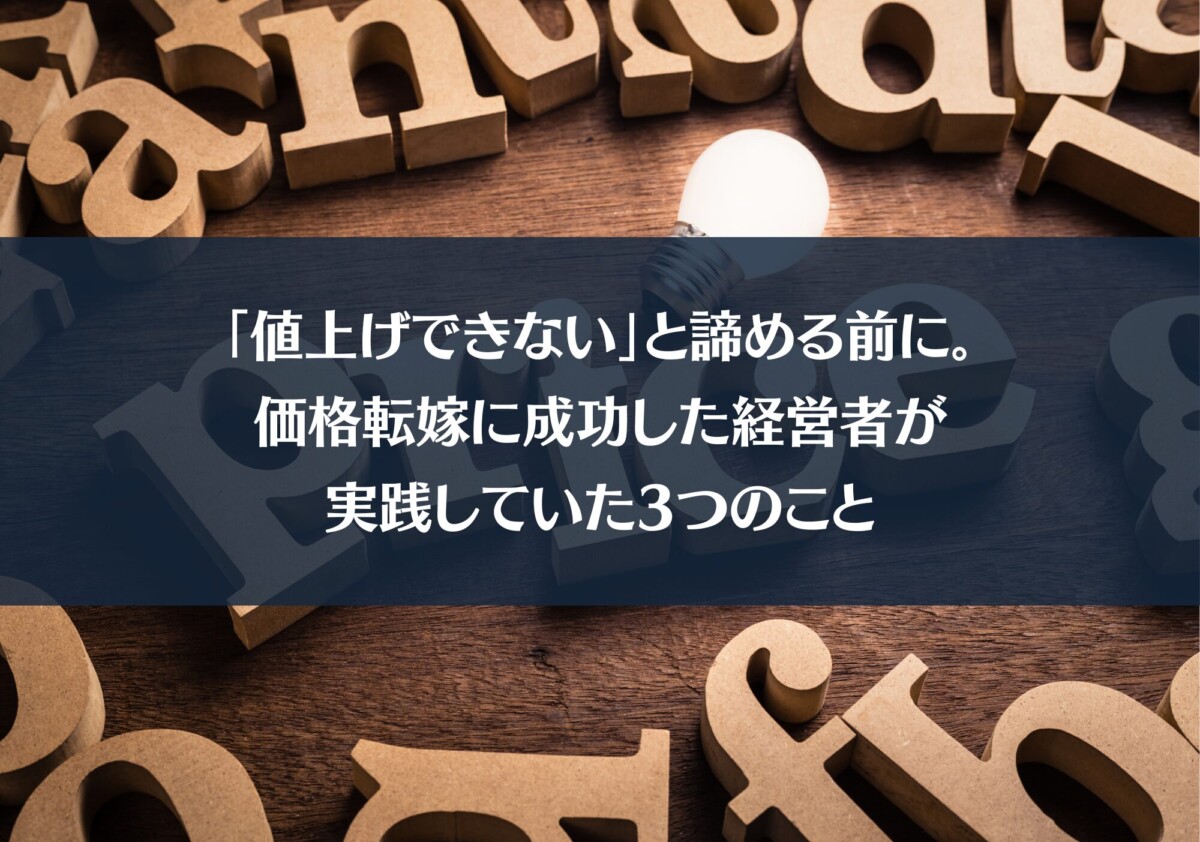
「値上げできない」と諦める前に。価格転嫁に成功した経営者が実践していた3つのこと
「原材料費も人件費も上がっているのに、取引先に値上げなんて言えない」——毎日、そんな想いを胸に会社の扉を開けている経営者の方も多いのではないでしょうか。中小企業白書2025によれば、価格転嫁率は5割近くまで上昇したものの、まだ道半ばの状況です。しかし同じ環境下でも、適切な価格転嫁を実現し、従業員の賃上げや設備投資につなげている企業が確実に存在します。その違いはどこにあるのか。価格転嫁に成功した経営者たちの実践から、明日への一歩を見つけていきましょう。
目次
あなただけではありません。多くの経営者が同じ悩みを抱えています
数字で見る、価格転嫁の現実
朝、会社に向かう足取りが重い日って、ありませんか。
電気代の請求書を見るたび、原材料の見積もりが届くたび、心の中で「どうしよう」とつぶやいてしまう瞬間。従業員の笑顔を見ると嬉しい反面、「この先、給料を上げてあげられるだろうか」という不安がよぎる。
そんな経営者の心の声が、中小企業白書2025の調査からも伝わってくるようです。
原材料・商品仕入単価の上昇は足下で落ち着いているものの高水準が続いており、売上単価との差は埋まっておらず、採算はおおむね横ばいとなっているという現実。多くの企業が、コスト上昇分を価格に転嫁しきれていない状況が続いているんですね。
でも、ここで知っていただきたい事実があります。
2024年9月の調査では、「発注側企業に価格交渉を申し入れて応じてもらえた」と「発注側企業からの声掛けで取引価格の話し合いができた」と回答した企業の割合は合算で約6割にのぼるということ。
つまり、価格交渉に踏み出した企業の多くが、何らかの形で前進を遂げているのです。
「業種のせい」ではなく「対応の差」
「うちの業界は厳しいから」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
サプライチェーンにおける取引段階が最終製品・サービスを提供する企業に近い「1次請け」から下流に行くほど、価格転嫁が進みづらい傾向があることは事実です。
しかし同時に、自社の製品・サービスの差別化や市場環境に対応した経営を行う会社ほど価格転嫁が進んでいるというデータもあります。
つまり、業種特性よりも「企業としてどう対応するか」が価格転嫁の成否を分けているんですね。
きっと多くの経営者の方が、同じような想いを抱いておられるのではないでしょうか。一人で悩んでいるのは、あなただけではないんです。
価格転嫁に成功した経営者が実践していた3つのこと
では、実際に価格転嫁を実現した経営者たちは、何をしていたのでしょうか。
各地の商工会議所や経済産業局が集めた成功事例から見えてきたのは、特別な裏技ではなく、誰にでもできる「地道な準備と誠実な姿勢」でした。
【実践①】数字で語れる準備をする
「なんとなく値上げ」では伝わらない
価格転嫁に成功した企業のうち「原価を示した価格交渉」が有効とする企業が45.1%と半数近くに上るという調査結果があります。
ある金属加工業の経営者の方は、こう語っておられました。
「以前は『コストが上がったので、なんとか…』とお願いするだけでした。でも、それでは取引先も困るんですよね。『どのコストがどれだけ上がったのか』を具体的に示せるようになってから、話が前に進むようになりました」
商品別・製品別の原価構成を把握している企業は、価格転嫁交渉において、高い価格転嫁を実現できているというデータが、この経営者の実感を裏付けています。
今すぐ始められる原価の「見える化」
原価計算と聞くと難しく感じるかもしれませんね。でも、完璧である必要はないんです。
まずは主要な製品やサービスについて、以下の項目を整理してみませんか。
原価の見える化チェックリスト
よろず支援拠点の価格転嫁サポート窓口では、原価計算に関する支援を受けられますし、中小機構が公表している「儲かる経営 キヅク君」は、簡易的に商品別の収支状況が把握できるツールで、登録不要、利用料は無料です。
一人で抱え込まず、こうした支援を活用しながら、「数字で語れる準備」を進めていきましょう。
過去2〜3年の推移をグラフ化すると、コスト上昇の深刻さが一目瞭然になります。エクセルやGoogleスプレッドシートで十分ですから、まずは簡単なものから始めてみてください。
【実践②】日常の関係性を大切にする
価格交渉は「交渉当日」ではなく「日常」で決まる
価格交渉に成功している企業の共通の特徴として、経営トップが社内や取引先に向けて高い発信力を持っているというヒアリング結果があります。
ある印刷会社の社長さんは、主要取引先5社に対して年4回の「経営報告会」を実施されているそうです。
「決算の数字だけでなく、紙やインクの市況、新しい設備の導入、業界のトレンドまで共有しています。価格改定が必要な局面でも『◯◯社の説明なら信頼できる』という関係ができていたので、初回交渉で8%の価格改定を承認していただけました」
この経営者の言葉から伝わってくるのは、取引先を「お客様」として大切にする想い。
値上げ交渉の前に、まず日頃から誠実な関係を築いておくことの大切さを、改めて感じさせられますね。
夜中にふと考え込んでしまう、そんな経営者の心の声が聞こえてくるようです。
「代替困難な存在」になる努力
価格交渉力を持つには、「替えが効かない存在」になることも重要です。
といっても、特別な技術が必要というわけではありません。
関係性を深める日常の実践
こうした日々の積み重ねが、「この会社とは長く付き合いたい」という想いを育てていくのではないでしょうか。
お客様に愛され続けている理由が、実はここにあったんですね。価格だけでなく、総合的な価値で選ばれる存在になること。それが価格交渉力の土台となるのです。
【実践③】段階的に、丁寧に進める
「いきなり値上げ」は関係を壊す
段ボール紙器製造と梱包資材を手がける企業は、取引先への深い理解とデータに基づく交渉戦略により、市場の供給力変化や地域別相場を考慮した上で、複数の値上げ案を提示することで、相手先が受け入れやすい条件を提案でき、価格転嫁を円滑に実現しました。
ある食品製造業の経営者は、小麦粉価格が20%上昇した際、こんなプロセスで価格転嫁を実現されたそうです。
段階的価格交渉の実例(6ヶ月プロセス)
6ヶ月前
「小麦相場の高騰が続いている」状況を経営層訪問で共有
4ヶ月前
「現行価格の維持が困難になる見通し」を非公式に伝達
3ヶ月前
正式な価格改定要請書を提出(10%値上げを提案)
2ヶ月前
取引先から「5%なら対応可能」との回答
→「8%で合意できないか」と再提案
1ヶ月前
「7%値上げ+一部製品は据え置き」で合意
実施
計画通りに価格改定を実行
「取引先にも予算があるし、社内での調整も必要。だから、できるだけ早めに情報を共有して、一緒に着地点を探すようにしています」
その経営者の言葉には、取引先への配慮と敬意が溢れていました。
相手に心の準備をさせず、選択肢も与えない交渉は失敗に終わります。段階的なアプローチこそが、双方が納得できる着地点への近道なんですね。
「留保価格」を決めておく柔軟さ
留保価格を設定している企業のほうが、価格転嫁に成功しているというデータもあります。
交渉ごとは相手があること。「10%値上げが理想だけど、最低でも7%は確保したい」といった幅を持たせておくことで、双方が納得できる着地点を見つけやすくなるんですね。
理想的な価格(提示価格)と、やむを得ない場合に譲歩できる価格(留保価格)を事前に決めておく。この準備が、交渉を成立させる大きな力になります。
あなたの会社にも、必ずヒントが隠されているはずです。小さな一歩かもしれませんが、それが未来を変える大きな力になるんです。
「できない理由」より「できる方法」を探す
恐怖心を乗り越えた先にあるもの
「値上げしたら取引が切られるのでは」
この恐怖心が、多くの経営者の足を止めていること、よくわかります。
でも、ニッチ分野で研究開発と競争力強化に取り組んできた企業は、値上げを行った結果、顧客離れも一部あったものの、販売単価上昇により売上げを維持し、かねてより取り組んできた原価低減の効果もあって利益率が改善し、継続的な賃上げを実施できるようになったという事例があります。
値上げせずに赤字で続けても、いずれ倒産してしまう。値上げして断られても、その取引は元々「続けられない取引」だったということ。
厳しい言い方かもしれませんが、これが現実ではないでしょうか。
経営の孤独感に押しつぶされそうになることって、ありますよね。従業員の将来を考えると、夜も眠れない日があるかもしれません。
でも、適切な価格転嫁ができなければ、企業は持続できません。従業員を守るためにも、勇気を持って一歩を踏み出す決断が必要なのです。
一人で悩まないで
全国47都道府県に「よろず支援拠点」の「価格転嫁サポート窓口」が設置されています。
原価計算の方法から、交渉の進め方、資料の作り方まで、専門スタッフが無料で何度でも相談に乗ってくれます。
経営の孤独感に押しつぶされそうになること、ありますよね。でも、あなたは一人じゃありません。支援を受けながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
中小企業庁の「価格交渉ハンドブック」には、実際の交渉事例や資料作成のテンプレートも掲載されています。まずはこうした資料に目を通すだけでも、「自分にもできるかもしれない」という希望が見えてくるはずです。
明日からできる3つのステップ
価格転嫁への道のりは、決して平坦ではありません。でも、一歩ずつ確実に進めば、必ず前進できます。
ステップ1:まずは「現状把握」から(今週中)
やるべきこと
完璧でなくて大丈夫。まずは現状を知ることから始めませんか。
税理士に相談したり、商工会議所の経営指導員に相談したりするのも良い方法です。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも大切なんですね。
ステップ2:取引先との「関係性」を確認する(今月中)
関係性チェックリスト
弱い部分があれば、今すぐ関係性強化のアクションを。定期訪問の設定や、情報提供の仕組み化から始めてみましょう。
取引先の決算期や予算編成の時期も確認しておくと、交渉のタイミングを計りやすくなります。相手の事情を理解することが、成功への第一歩なのです。
ステップ3:「ロードマップ」を描く(今月中)
交渉計画の立て方
最低でも3ヶ月の交渉期間を想定して、じっくり丁寧に進めていく計画を立ててみてください。
値上げ幅のシミュレーションも忘れずに。希望値(完全にコストを転嫁できる水準)、現実値(交渉で落としどころになりそうな水準)、最低値(これ以下では採算割れする水準)の3パターンを用意しておくと、交渉がスムーズになります。
よくある疑問にお答えします
Q1:「取引先から、他社は値上げしていないと言われたら?」
これこそ「データで語る」場面です。
業界団体の価格動向データを提示したり、公的機関の原材料価格統計を示したりすることで、客観的な根拠を示せます。
「他社の価格」ではなく「自社の原価と適正利益」を基準に交渉する姿勢が大切なんですね。他社が適正価格を提示できていない可能性もあるわけですから。
Q2:「大手取引先が全く聞く耳を持たない場合は?」
残念ながら、これは「力関係」の問題です。
しかし、取るべきステップはあります。下請法・独占禁止法の観点から、買いたたきや不当な値下げ要請に該当しないか検討してみましょう。下請かけこみ寺などへの相談も一つの方法です。
中長期的には、取引先の分散化を検討することも重要。一社依存度が高いほど交渉力は弱くなってしまいますから。
技術力、品質、対応力で「替えが効かない」存在になることも、交渉力を高める有効な手段なのです。
Q3:「値上げしたら取引が切られるのでは?」
この恐怖心、本当によくわかります。
でも、適切な説明と交渉プロセスを踏めば、取引先の約8割は理解を示すという調査結果があります。
重要なのは「値上げするかしないか」ではなく、「どう値上げを実現するか」。準備と誠意を持って臨めば、必ず道は開けるはずです。
まとめ:想いを形に、価値ある未来へ
円安・物価高の継続や賃上げ率の上昇によって、コストカット戦略は限界を迎えています。積極的な設備投資・デジタル化と、適切な価格設定・価格転嫁の推進が、今、強く求められているのです。
価格転嫁に成功した経営者たちの実践から見えてきた共通点。
3つの実践ポイント
- 数字で語れる準備をする — 原価を可視化し、客観的な根拠を持つこと
- 日常の関係性を大切にする — 信頼は一朝一夕には築けない
- 段階的に、丁寧に進める — 相手への配慮が成功への道
これらは決して特別なことではありません。むしろ、誠実に、地道に、相手を思いやりながら進めるという、日本の中小企業が本来持っている強みそのものではないでしょうか。
夜中にふと考え込んでしまう、そんな経営者の心の声が少しでも軽くなるように。従業員の笑顔をもっと増やせるように。
地域に根ざした中小企業だからこそできることが、確実にあるんです。あなたが築き上げてきたものの価値を、改めて見つめ直してみませんか。
今日という日が、新しいスタートの日になるかもしれません。
一人ひとりの経営者の想いが、きっと日本の未来を支えていくのだと、私たちは信じています。
明日からの経営に、少しでも新しい風を感じていただけたなら、これほど嬉しいことはありません。
【参考資料・相談窓口】
公的資料
相談窓口・支援ツール
- 価格転嫁サポート窓口(よろず支援拠点)全国47都道府県
- 儲かる経営 キヅク君(中小機構) – 無料・登録不要
- 価格転嫁検討ツール(中小機構) – 無料・登録不要
- 下請かけこみ寺(全国中小企業振興機関協会)
制度・施策