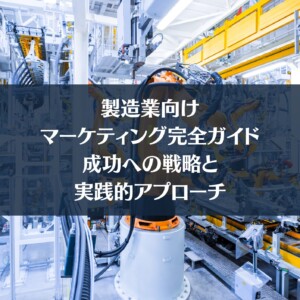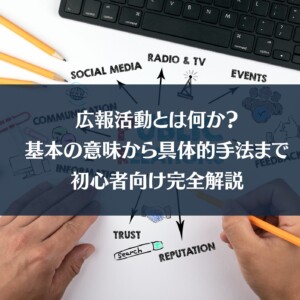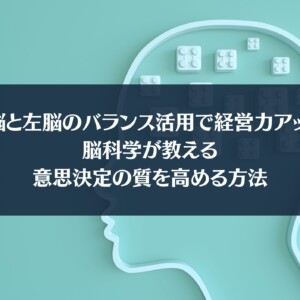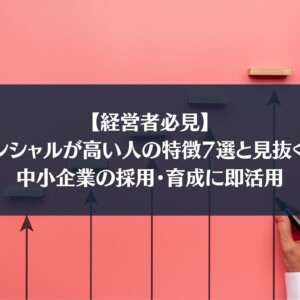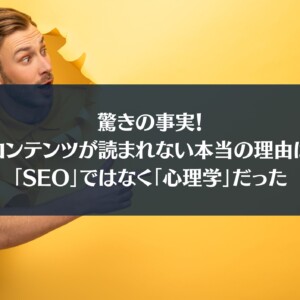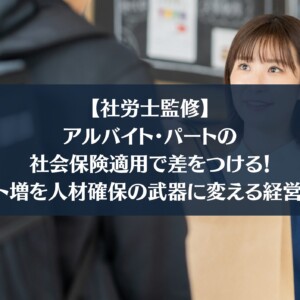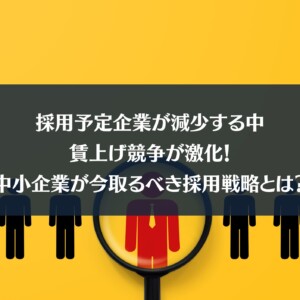経営者の想いを引き出すインタビュー記事の書き方|心に響く取材のコツと執筆テクニック
「自社の魅力を伝えたいけれど、どう表現すればいいかわからない」そんな悩みを抱えている経営者の方は少なくありません。
採用サイトや企業ホームページに経営者インタビューを掲載したい。社員の想いを形にして、求職者の心に届けたい。でも、ライターに外注する予算は限られているし、自分で書くにしても何から始めればいいのか分からない――。そんなお悩み、よくわかります。
この記事では、インタビュー記事の基本的な書き方から、相手の本音を引き出す質問テクニック、読者の心を動かす執筆のコツまで、実践的なノウハウをお伝えしていきます。インタビュー記事は、「費用対効果抜群!コンテンツマーケティング戦略を中小企業が取り組むべき理由」でも紹介している、効果的なコンテンツマーケティング手法の一つなんですね。完璧な記事を目指す必要はないんです。大切なのは、相手への誠実さと、想いを形にしようとする姿勢。この記事を読み終える頃には、「自分にもできるかもしれない」という前向きな気持ちになっていただけるはずです。
相手の本音を引き出す事前準備と質問設計
インタビューの成否を決めるのは、実は取材当日ではありません。相手との信頼関係を築き、本音を引き出せるかどうかは、事前準備の質にかかっているんです。
「何を聞けばいいのか分からない」「形式的な質問ばかりになってしまう」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。でも大丈夫。ここでご紹介する準備と質問設計のコツを実践すれば、相手の想いに寄り添った深いインタビューができるようになります。経営者の心に響く質問を用意することで、読者の心を動かすストーリーが自然と引き出せるようになるんですね。
取材対象者への敬意を示すリサーチ方法
相手の会社について徹底的に調べることが、信頼関係構築の第一歩になります。
企業のウェブサイトはもちろん、過去のインタビュー記事やプレスリリース、SNSでの発信内容まで、可能な限りの情報を収集してください。単なるデータ集めではなく、「この経営者はどんな価値観を大切にしているのか」「どんな想いで事業を運営されているのか」という視点でリサーチすることが何より大切なんです。
FacebookやX(旧Twitter)での日常的な投稿からは、経営者の人柄や関心事が見えてきます。地域のイベントへの参加状況、従業員との関係性、お客様への想いなど、公式サイトには載っていない生の情報が得られることも。「あなたのことを理解しようと努力している」という姿勢が相手に伝われば、取材当日の会話はぐっと深まるはずです。
リサーチで得た情報は、取材前に整理しておきましょう。「この点についてもっと詳しく聞きたい」「この発言の背景にある想いを知りたい」といったメモを作っておくと、質問設計がスムーズに進みます。
取材対象者のことを深く知ろうとする姿勢こそが、最も大切な敬意の表し方。その想いは必ず相手に届き、心を開いてもらえるきっかけになるでしょう。
取材対象者への敬意を示すために、以下の項目を確認しながら徹底的にリサーチを行いましょう。各項目をクリックするとチェックできます。
完了: 0 / 11
信頼関係を築く質問リストの作り方
質問リストは、固定的な台本ではなく、会話の流れに応じて選べる「質問の選択肢」として用意するのがコツです。この柔軟な対応力は、「インタビューとヒアリングの違いを徹底解説|中小企業経営者が知るべき効果的な使い分け術」でも解説しているように、相手から本質的な情報を引き出すために不可欠なスキルなんですね。
相手が話しやすいテーマから始めて、徐々に核心に迫っていく構成を意識してください。最初から重たい質問をぶつけるのではなく、「創業当時のエピソード」といった比較的答えやすい内容からスタートするといいでしょう。会話が温まってきたら、「最も困難だった時期」「経営者としての葛藤」といった深い質問へと移行していくわけです。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンのバランスも大切。「はい・いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンは、事実確認に便利ですが、それだけでは相手の想いは引き出せません。「どのようなお気持ちでしたか」「なぜそう判断されたのですか」といったオープンクエスチョンを織り交ぜることで、経営者ならではの深い洞察や感情が語られるようになります。
質問は、相手の回答を受けて柔軟に変えられるよう、テーマごとに複数パターン用意しておくのがおすすめ。例えば「創業のきっかけ」について聞く際も、「何がきっかけでしたか」という基本的な質問に加えて、「その決断をされた時、周囲の反応はいかがでしたか」「不安はありませんでしたか」といった派生質問も準備しておくんです。
事前に質問リストを相手に共有するかどうかは、状況に応じて判断してください。話すことに慣れていない経営者には事前共有が安心材料になりますが、自然な会話の流れを大切にしたい場合は、当日のやり取りを優先する方法もあるでしょう。
経営者の想いを深掘りする5つの質問パターン
相手の感情や価値観を引き出すには、質問の「型」を知っておくことが役立ちます。
創業のきっかけを探る質問では、単に「なぜ起業したのですか」と聞くのではなく、「起業を決意された瞬間のことを、今でも覚えていらっしゃいますか」と問いかけてみてください。その時の感情や情景を思い出してもらうことで、生き生きとしたエピソードが語られるようになるんですね。「どんな想いを胸に、最初の一歩を踏み出されたのでしょうか」という聞き方も効果的でしょう。
困難を乗り越えた経験については、「最も苦しかった時期はいつですか」だけでなく、「その困難を乗り越えられた原動力は何だったのでしょうか」と深掘りすることが大切。経営者の内面の強さや、支えてくれた人々への感謝の気持ちが引き出せます。「今振り返ると、その経験はどんな意味を持っていますか」という質問も、深い洞察を得られる問いかけです。
従業員への想いを聞く際は、「従業員の方々をどう思っていますか」という抽象的な質問より、「従業員の方の笑顔を見た時、どんな気持ちになりますか」「従業員の成長を感じる瞬間はありますか」といった具体的なシーンを思い浮かべてもらう質問が効果的。経営者の人間性や、チームへの愛情が自然と表現されるようになります。
地域への貢献というテーマでは、「地域にどう貢献していますか」ではなく、「この地域で事業を続けていく意味を、どう捉えていらっしゃいますか」と問いかけてみましょう。地域との絆や、地元への想いが言葉になって表れてくるはずです。
未来への展望については、「今後の目標は何ですか」という質問に加えて、「10年後、この会社がどうなっていたら嬉しいですか」「次世代に何を残したいと考えていらっしゃいますか」と聞くことで、経営者の本質的なビジョンが見えてきます。
これらの質問パターンを組み合わせることで、経営者の人となりや価値観が立体的に浮かび上がってくるんです。
それぞれの質問テーマにおいて、表面的な質問と深掘りする質問の違いを以下の比較表で確認してみましょう。この対比を意識することで、より深い対話が生まれるはずです。
| 質問テーマ | 表面的な質問例 | 深掘りする質問例 |
|---|---|---|
| 創業のきっかけ | なぜ起業したのですか | 起業を決意された瞬間のことを、今でも覚えていらっしゃいますか どんな想いを胸に、最初の一歩を踏み出されたのでしょうか |
| 困難の乗り越え | 最も苦しかった時期はいつですか | その困難を乗り越えられた原動力は何だったのでしょうか 今振り返ると、その経験はどんな意味を持っていますか |
| 従業員への想い | 従業員の方々をどう思っていますか | 従業員の方の笑顔を見た時、どんな気持ちになりますか 従業員の成長を感じる瞬間はありますか |
| 地域への貢献 | 地域にどう貢献していますか | この地域で事業を続けていく意味を、どう捉えていらっしゃいますか |
| 未来への展望 | 今後の目標は何ですか | 10年後、この会社がどうなっていたら嬉しいですか 次世代に何を残したいと考えていらっしゃいますか |
相手の心に響く質問を用意することで、読者の心をも動かすストーリーが自然と生まれてくるものです。
取材当日までに整えておく3つの準備
機材の動作確認は、プロとしての基本中の基本。
録音機器のバッテリー残量や空き容量を確認し、予備のバッテリーやメモリーカードも必ず用意してください。「機材トラブルで録音できなかった」という失敗は、相手に対して失礼なだけでなく、貴重な話を記録できないという致命的な損失につながります。スマートフォンでの録音を予定している場合も、専用の録音アプリをインストールし、事前にテスト録音をしておくと安心でしょう。
取材の流れを記したタイムスケジュールも作成しておきましょう。アイスブレイク5分、導入部の質問10分、本題30分、深掘り質問20分、クロージング5分といった具合に、大まかな時間配分を決めておくんです。もちろん、会話の流れを優先することが大切ですが、目安があることで時間を意識しながら進められます。
そして最も重要なのが、心の準備。相手の話を受け止める心構えを整えることが、何よりも大切な準備なんですね。「この経営者の想いを、丁寧に形にしよう」「読者に価値ある情報を届けよう」という使命感を持つことで、自然と真摯な姿勢でインタビューに臨めるようになります。
取材前夜は十分な睡眠を取り、余裕を持って会場に到着できるよう移動時間も計算しておきましょう。焦った気持ちで臨むインタビューでは、相手の本音を引き出すことは難しいもの。落ち着いて、相手に集中できる状態を作ることが、良いインタビューへの近道です。
完璧な準備など存在しません。でも、相手への敬意と誠実さを持って臨めば、きっと素晴らしいインタビューになるはず。あなたの真摯な姿勢が、経営者の心を開き、読者の心を動かす記事を生み出していくのです。実際のインタビュー記事の多様な形式や表現方法については、「2024年版|インタビュー記事の書き方・形式・準備の完全ガイド」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
取材当日に実践したい会話術と記録のコツ
どれだけ入念に準備をしていても、実際の取材では予想外のことが起こるもの。事前に用意した質問リストはあくまでガイドラインとして持ちながら、目の前の相手に集中して柔軟に対応することが何より大切です。相手の表情や声のトーン、ちょっとした言葉の選び方から感情を読み取る観察力を磨いていくことで、インタビューの質は飛躍的に高まっていくでしょう。
緊張をほぐして話しやすい空気を作る方法
取材の冒頭で相手の緊張をほぐせるかどうかが、その後の会話の深さを大きく左右します。
いきなり「それでは創業についてお聞かせください」と本題に入るのではなく、まずは自然な会話から始めてみてください。「今日はお時間をいただきありがとうございます。このオフィス、とても素敵な雰囲気ですね」といった言葉や、会議室に飾られている写真への言及、あるいは天気や季節の話題など、相手がリラックスできる話題を選ぶことがポイント。
形式的な質問から始めるより、まずは人と人としての自然なコミュニケーションを心がけることで、相手は「この人なら安心して話せそうだ」と感じてくださるはずです。アイスブレイクは5分から10分程度を目安に、相手の表情が柔らかくなってきたら、自然な流れで本題に入っていきましょう。
相手の感情を言葉にさせる質問テクニック
事実だけを聞き出すインタビューと、読者の心に響くインタビューの違いは何でしょうか。
それは、経営者が抱いた感情や想いを語ってもらえるかどうかにあるんです。「創業は何年ですか」という事実確認の質問も必要ですが、それだけでは記事に深みが生まれません。「創業を決意されたとき、どんなお気持ちでしたか」「何がいちばん大変でしたか」「そのとき支えになったものは何でしたか」といった、感情に焦点を当てた質問を投げかけてみてください。
相手が一瞬言葉に詰まったり、視線を遠くに向けたりする瞬間があったら、それは心の深いところに触れた証拠。そんなときこそ、じっくりと相手の言葉を待つ姿勢が大切なのです。
では、実際の質問テクニックを具体的に見ていきましょう。以下の表で、事実確認型の質問と感情を引き出す質問の違いを確認してみてください。
この表からも分かるように、少しの言い回しの工夫で、相手から引き出せる言葉の深さが大きく変わってくるものなんですね。
メモより大切な「聞く姿勢」の作り方
インタビュー中、メモを取ることに集中しすぎて相手の目を見られなくなっていませんか。
録音機器があるのですから、すべての言葉を書き留める必要はないんです。相手の目を見て、頷きながら話を聞く。それだけで「あなたの話を大切に聞いています」というメッセージが伝わり、信頼関係が深まっていきます。特に印象的な言葉や、相手の表情が変わった瞬間、強調された言葉だけをさっとメモする程度にとどめ、会話に集中することを優先してください。
「この人は本当に私の話を聞いてくれている」と感じたとき、経営者は心を開いてくださるもの。メモ帳ばかり見ているインタビュアーには、誰も本音を語りたいとは思わないでしょう。あなたの真摯な姿勢こそが、最高のインタビューを生み出す鍵になるのです。
印象的なエピソードを見逃さない聞き方
相手が何気なく語った一言の中に、実は記事の宝物が隠れていることがあります。
「そういえば、あのときはこんなこともありましてね」と、本題から少し逸れた話が出てきたとき。その瞬間を見逃さないことが、心に響く記事を書く秘訣なんです。「それ、もう少し詳しく聞かせていただけますか」「そのときのお気持ちを教えていただけますか」といったフォロー質問で掘り下げていくことで、予想もしなかった素晴らしいエピソードに出会えることがあるでしょう。
相手の表情が変わった瞬間、声のトーンが変わった瞬間を見逃さない観察力を磨いてください。準備した質問リストにない話題でも、相手が情熱を持って語り始めたら、その流れに乗ってみることも大切。計画通りに進めることより、相手の想いを引き出すことを優先する柔軟さが、結果的に読者の心を動かす記事につながっていくものなのです。
読者の心を動かす記事の書き方と仕上げ方
取材で得た貴重な情報を、どのように読者の心に届く記事へと昇華させるか。ここでは、文字起こしから完成までの執筆プロセスと、経営者の人柄や想いを正確に伝えるための実践的なテクニックをお伝えしていきます。
単なる情報の羅列ではなく、読者が「この経営者に会ってみたい」と感じられる記事を作ることで、あなたの会社の魅力はより深く伝わっていくはず。最後まで飽きさせない文章表現や、丁寧な確認作業の重要性についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
文字起こしから魅力的なストーリーを組み立てる手順
録音データを聞きながら文字起こしをする際、まず心がけたいのが「印をつける作業」です。
経営者が感情を込めて語った場面、声のトーンが変わった瞬間、印象的な言葉が飛び出した箇所には、忘れずにマーキングしておきましょう。これらは記事の核となる宝物なんですね。「えー」や「あのー」といったフィラーは整理しつつも、相手らしさが伝わる独特の言い回しは大切に残しておくことが何より大切です。なお、手作業での文字起こしには音声時間の4倍程度の時間がかかるといわれていますので、スケジュールには余裕を持って取り組みましょう。
文字起こしが完了したら、次は話の流れを整理してストーリーラインを作る段階。時系列で語られた内容を、テーマ別に再構成することで起承転結のある物語が生まれてきます。創業への想い、困難の乗り越え方、現在の取り組み、未来への展望という流れを意識すると、読者にとって理解しやすい構成になるでしょう。最も印象的なエピソードを冒頭に持ってくる構成も効果的ですね。
人柄が伝わる文章表現の工夫
経営者が実際に使った言葉を、できるだけそのまま活かすことが大切。
「私はこう思うんです」「本当にそうなんですよね」といった話し言葉のニュアンスを残すことで、その人らしさが自然と伝わってくるものです。過度に整えすぎて、教科書のような硬い文章になってしまうと、せっかくの温かみが失われてしまいます。経営者の想いや人柄を感じられる表現こそが、読者の心を動かす力を持っているのではないでしょうか。
語尾の選び方も、人柄を表現する重要な要素。「〜なんです」「〜ですよね」「〜だったりします」といった柔らかい語尾を適度に使うことで、親しみやすさが生まれます。一方で、「経営者としての覚悟。」といった体言止めを使えば、力強い決意が伝わってくるでしょう。
単調さを避けて最後まで読ませる文章リズム
同じ語尾が連続すると、どんなに良い内容でも読者は飽きてしまうもの。
「〜です。〜です。〜です。」という単調なリズムを避けるために、意識的に語尾を変化させていく工夫が必要なんですね。「〜ではないでしょうか」「〜かもしれません」「〜といえます」「〜なのです」といったバリエーションを織り交ぜることで、文章に自然なリズムが生まれてきます。短い文と長い文を組み合わせることも、読みやすさを高める効果的な手法です。
体言止めや疑問形、共感を誘う語尾なども積極的に活用していきましょう。「そんな想いを胸に、今日も前へ進み続ける経営者の姿。」といった体言止めは、読者の心に余韻を残します。「きっと多くの方が、同じような経験をされているのではないでしょうか。」という問いかけは、読者との対話を生み出すわけです。「そう思いませんか」「ということはありませんか」といった語尾も、共感を呼び起こす効果があります。
段落ごとに語尾のパターンを意識的に変えていくことで、最後まで飽きさせない記事に仕上がっていくはず。読み返した時に単調に感じる箇所があれば、そこが改善ポイントです。
経営者の想いを正確に伝えるための確認作業
記事が完成したら、必ず経営者本人に内容を確認してもらうことが何より大切です。
事実関係の誤りがないかをチェックするのはもちろんですが、それ以上に大切なのが「ニュアンスが正しく伝わっているか」という点。数字や固有名詞の正確性だけでなく、「自分が伝えたかった想いがきちんと表現されているか」という視点で読んでもらうことで、より良い記事へと磨き上げられていきます。
確認の際には、「この表現で違和感はありませんか」「ここはもう少し詳しく書いた方がよろしいでしょうか」といった丁寧なコミュニケーションを心がけてください。相手の想いを尊重しながら、読者にとって分かりやすい表現を一緒に探していく姿勢が大切なんですね。修正依頼があった場合も、それは記事をより良くするための貴重なフィードバック。何度でも誠実に対応していくことで、経営者との信頼関係も深まっていくはずです。
最終確認が終わったら、改めて全体を通して読み返してみましょう。誤字脱字がないか、文章のリズムは自然か、読者にとって価値のある内容になっているか――。そうした細やかなチェックを経て、ようやく一つの記事が完成するのです。
まとめ
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。インタビュー記事の書き方について、事前準備から取材当日の会話術、そして記事執筆のコツまで、実践的なノウハウをお伝えしてまいりました。最後に、この記事でお伝えした重要なポイントを改めて振り返っておきましょう。
- インタビューの成否は事前準備で決まり、相手への敬意を示すリサーチと質問設計が信頼関係構築の第一歩となる
- 取材当日は質問リストに固執せず、相手の感情や想いを引き出す柔軟な聞き方と、目を見て話を聞く真摯な姿勢が何より大切である
- 記事執筆では経営者の言葉をそのまま活かし、語尾を変化させて単調さを避け、最後まで飽きさせない文章リズムを意識することで読者の心を動かす
インタビュー記事は、単なる情報伝達のツールではありません。経営者の想いや従業員の声を丁寧に形にすることで、求職者の心に響き、顧客との信頼関係を深め、地域での存在感を高める力を持っています。完璧な記事を最初から目指す必要はないんです。大切なのは、相手への誠実な姿勢と、想いを大切にしようとする心。その姿勢があれば、技術は後からついてくるものです。あなたの会社にも、きっと素晴らしいストーリーが眠っているはず。この記事でお伝えしたテクニックを参考にしながら、まずは身近な誰かの話を聞くことから始めてみてください。一歩踏み出す勇気が、あなたの会社の魅力を多くの人に届ける第一歩になるでしょう。