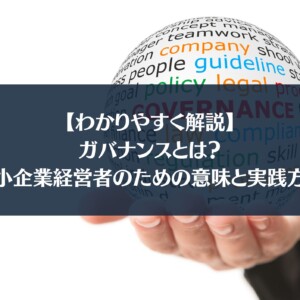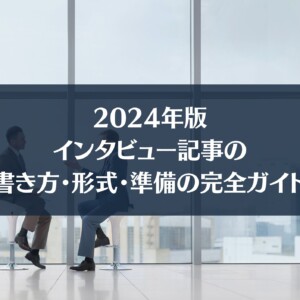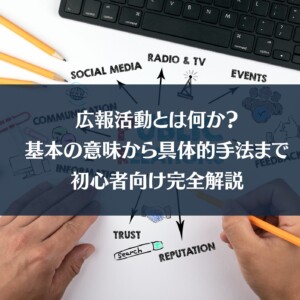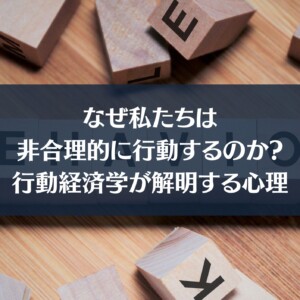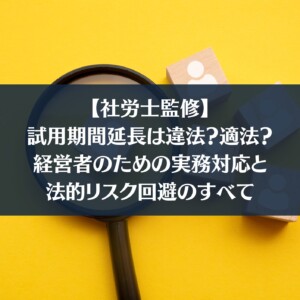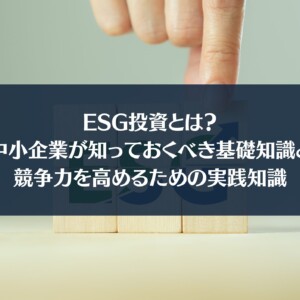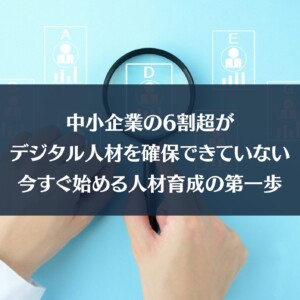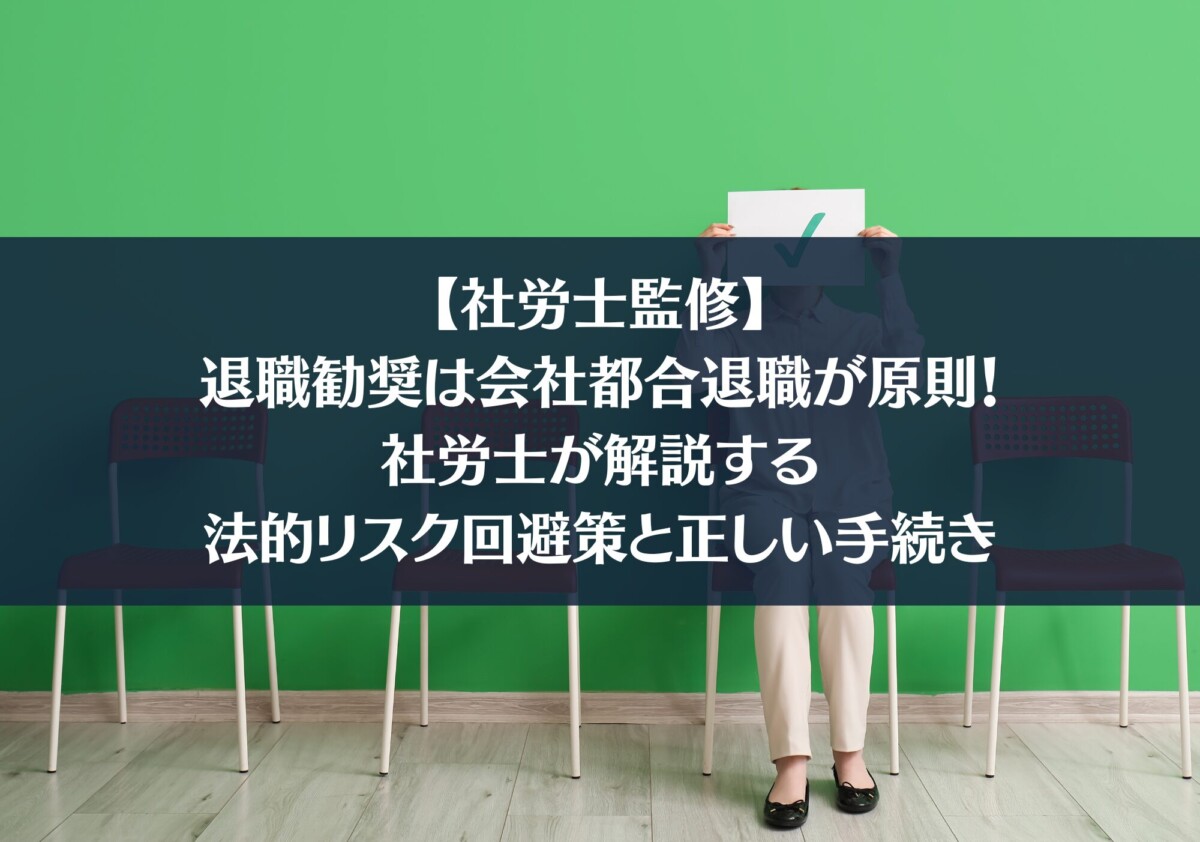
【社労士監修】退職勧奨は会社都合退職が原則!社労士が解説する法的リスク回避策と正しい手続き
「人員整理が必要だが、退職勧奨を会社都合にすべきか自己都合にすべきか悩んでいる」
このような課題を抱える経営者の方は少なくありません。実は退職勧奨は法的には「会社都合退職」として扱うのが原則なのです。なぜなら、退職の発意が会社側にあるからです。
本記事では社労士監修のもと、退職勧奨の法的位置づけから実務的な手続き方法、さらには起こりがちなトラブル事例まで網羅的に解説します。これにより、法的リスクを最小限に抑えながら、適切に退職勧奨を進めるための具体的な道筋が見えてくるでしょう。
退職勧奨の法的位置づけと会社都合退職の原則
ここでは、業績悪化や事業再編により人員整理を検討している経営者にとって重要な「退職勧奨」の法的位置づけについて解説します。退職勧奨を実施する際には、それが原則として「会社都合退職」に該当することを理解しておくことが不可欠です。この知識がないまま不適切な対応をすると、後々大きなトラブルを招く恐れがあるためです。法的根拠を押さえた上で、正しい手続きを踏むことで、企業と従業員双方にとって円満な退職プロセスを実現しましょう。

退職勧奨と解雇の法的な違いと実務上の区別
退職勧奨と解雇は明確に区別する必要があります。退職勧奨とは、会社側から従業員に対して退職を促し、従業員の同意を得て雇用契約を終了させる合意解約を目指すものです。一方、解雇は従業員の同意なく、会社からの一方的な通知により雇用契約を終了させることを意味します。
解雇は労働契約法第16条で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫用として無効」とされており、非常に厳格な要件が課されています。そのため、多くの企業は解雇よりも退職勧奨を選択する傾向にあるのです。
実務上の大きな違いは、解雇の場合は解雇予告手当の支払いが必要となる点、また退職勧奨では従業員との話し合いによって退職条件を交渉できる点にあります。退職勧奨では、退職金の上乗せなど、退職者への配慮も示しやすいでしょう。
退職勧奨が会社都合退職として扱われる法的根拠と判例
退職勧奨による退職が会社都合退職として扱われる根拠は、雇用保険法第23条2項及び雇用保険法施行規則第36条に基づいています。雇用保険法施行規則第36条では、「事業主から退職するよう勧告を受けた」者は特定受給資格者(会社都合退職)に該当すると明記されています。
厚生労働省の通達においても、退職勧奨に応じて退職した場合は、原則として雇用保険の特定受給資格者に該当するとされています。実際の判例でも、この原則は広く認められています。例えば、ゴムノイナキ事件(大阪地方裁判所判決平成19年6月15日)では、従業員に問題があったとしても、会社からの退職勧奨に応じて退職した場合は会社都合退職として扱うべきという判断が示されました。
退職の意思表示が従業員側からなされたとしても、その発意が会社側にある場合には、実質的に会社都合退職として取り扱うというのが確立した考え方なのです。これはハローワークでの実務運用においても一貫しています。
退職勧奨を自己都合扱いにすることのリスクと法的責任
退職勧奨を実施しながら自己都合退職として処理することは、非常に大きなリスクを伴います。まず、従業員は失業給付の待機期間や給付日数について不利益を被るため、その差額分について損害賠償を請求される可能性があります。実際に、ゴムノイナキ事件(大阪地方裁判所判決平成19年6月15日)では、退職勧奨を自己都合扱いにした会社に対し、会社都合退職であれば受け取れたはずの退職金と失業保険の差額として275万1200円の損害賠償が命じられています。
また、労働局から是正勧告を受けるリスクもあります。従業員が労働局に申立てを行い、実態調査が入った場合、退職勧奨の証拠(メールや録音など)が提示されれば、虚偽の離職票作成として指摘される恐れがあります。
さらに重大なのは、企業の信用問題です。こうした不適切な対応が明るみに出れば、残った従業員からの信頼も失い、採用活動にも悪影響を及ぼすでしょう。法的リスクだけでなく、人事労務管理全体の問題として捉える必要があります。退職金規程における割増支給や解決金の支払いを避けるために自己都合扱いにすることは、長期的に見て得策ではありません。
労働局や裁判所の見解:退職勧奨に関する最新の判断基準
労働局や裁判所は退職勧奨に関して、どのような行為が「退職強要」に当たるかという判断基準を示しています。代表的な判例として、下関商業高校事件(広島高判 昭和52年1月24日)では、1回目の退職勧奨から一貫して応じない意思を表明していた教員に対し、2〜4か月の間に11〜13回にわたり退職勧奨が繰り返された行為が「自発的な退職意思の形成を慫慂する限度を越え、心理的圧力を加えて退職を強要したもの」として違法と判断されました。
また、大和証券事件(平成27年4月24日大阪地裁判決)では、退職を目的とした不利益な配置転換が違法とされています。これらの判例から、退職勧奨の方法や頻度、内容に関する境界線が明確になっています。
最近の労働局の指導方針では、退職勧奨そのものは違法ではないものの、その進め方について厳格な視点を持っています。特に「パワハラ」との関連で、強圧的な言動や執拗な説得は問題視される傾向にあります。適切な退職勧奨とは、従業員の人格や尊厳を尊重した上で行うべきものと理解しましょう。
会社都合退職と自己都合退職の実務的な違いと影響
ここでは、退職勧奨を「会社都合退職」として扱うか「自己都合退職」として扱うかによって生じる実務上の違いと、企業・従業員双方への影響について解説します。この違いを正確に理解することで、退職手続きにおける不必要なトラブルを回避し、適切な対応ができるようになります。退職理由の区分は単なる形式的な問題ではなく、雇用保険の給付内容や企業の保険料率、退職金の支給額、さらには助成金の受給資格にまで影響を及ぼす重要な判断になるのです。

雇用保険における給付内容と受給期間の違い
会社都合退職と自己都合退職では、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の受給において大きな違いがあります。最も重要な違いは給付制限期間で、会社都合退職の場合は待機期間の7日間のみであるのに対し、自己都合退職では待機期間7日に加えて2カ月間の給付制限期間があります(過去5年以内に2回以上の自己都合退職を経験している場合は3カ月間)。
さらに、給付日数にも差があり、会社都合退職(特定受給資格者)の方が多く設定されています。会社都合退職の給付日数は90~330日であるのに対し、自己都合退職では90~150日となります。また、受給資格の条件も異なり、会社都合退職は離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あることが条件ですが、自己都合退職は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件です。
この違いは退職者の生活に直接影響するため、企業側が退職勧奨を行う際には、退職後の従業員の生活にも配慮して会社都合として適切に手続きを進めることが望ましいでしょう。退職者の状況によっては、この3カ月の待機期間が大きな生活上の問題となるケースもあります。
退職金規程の適用と割増支給に関する留意点
多くの企業の退職金規程では、会社都合退職と自己都合退職で支給額に差を設けています。一般的に会社都合退職の場合は100%支給となる一方、自己都合退職の場合は勤続年数に応じて減額率が適用されるケースが多いです。
退職勧奨を実施する際には、自社の退職金規程を事前に確認し、どのような取扱いになるかを把握しておく必要があります。規程上で会社都合退職に該当するにもかかわらず、自己都合として処理すれば、従業員から退職金の差額請求を受ける可能性が高くなります。
また、退職勧奨時には退職金の上乗せ交渉が行われることも珍しくありません。この場合、追加支給分を「解決金」として別途合意書に記載するなど、法的にも明確な形で対応することが望ましいでしょう。規程の見直しを検討する場合は、労働条件の不利益変更とならないよう慎重に進める必要があります。
助成金受給資格への影響と制限事項
会社都合退職者を出した企業は、一部の助成金の受給に制限を受けることがあります。
例えば、雇用調整助成金では、原則として支給申請日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請日の前日までの間に、会社都合退職者を出していないことが支給要件の一つとなっています。
ただし、助成金の種類によって制限の内容は異なり、例外規定も設けられていることがあります。人員調整と助成金活用の両立を図るためには、計画的な人事戦略が必要です。退職勧奨を検討する際には、活用している助成金や今後申請予定の助成金への影響も含めて検討することをお勧めします。
適法な退職勧奨の進め方と必要書類の作成
ここでは、退職勧奨を法的リスクを最小限に抑えながら進めるための具体的なステップと必要な書類作成について解説します。退職勧奨は慎重に進めなければ、「退職強要」とみなされてトラブルに発展する恐れがあります。適切な準備、面談の実施方法、各種書類の正確な作成を通じて、円満な形で退職プロセスを完了させましょう。手順を理解し、適切な書類を用意することで、従業員との信頼関係を保ちつつ、法的問題を回避できます。
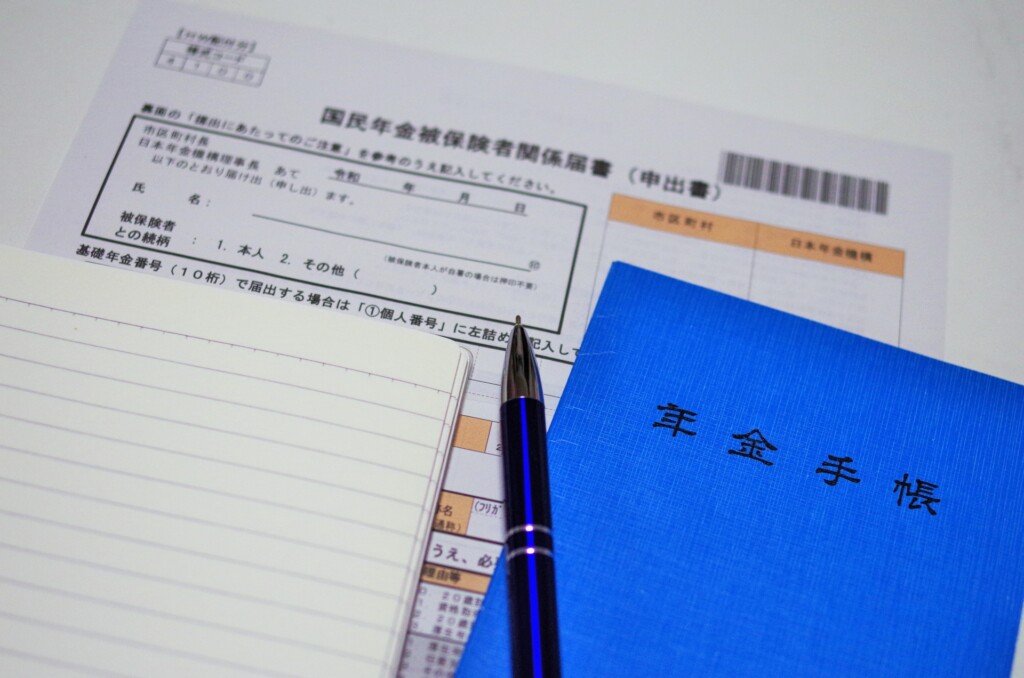
退職勧奨前の準備と社内での方針共有
退職勧奨を始める前の準備は、後のトラブル防止に大きく影響します。まず社内で退職勧奨の方針を決定し、対象者選定の基準を明確化することが重要です。「実際に起こったトラブル」など客観的な事実を資料で裏付けておきましょう。主観的な理由ではなく具体的な事実に基づく理由を整理することが必要です。
次に、経営陣や関係部署(人事、法務など)と方針を共有します。誰が、いつ、どのような形で退職勧奨を行うか、退職条件はどうするかなどを事前に決定しておくことが必要です。
また、就業規則や退職金規程を確認し、社内での前例も調査しておきましょう。同様のケースで異なる対応をすると、不公平感が生じてトラブルの原因となります。さらに、想定される質問への回答も準備しておくことで、面談時の対応がスムーズになります。
面談時の適切な伝え方とNGワード
退職勧奨の面談では、言葉遣いや伝え方が非常に重要です。強圧的な言動はパワハラとみなされる可能性があるため、相手の人格を尊重した丁寧な対応を心がけましょう。
絶対に避けるべきNGワードとしては、「明日から来なくていい」「解雇する」「辞めないなら左遷する」などがあります。これらは退職強要と判断される可能性が高く危険です。代わりに「会社の状況をご理解いただきたい」「退職について検討していただけないか」といった表現を使いましょう。
面談は、プライバシーに配慮した個室で行い、他の職員から見えない場所で実施することが重要です。長時間や連日の面談は圧力とみなされ違法な退職勧奨と判断される恐れがあります。また、面談内容は必ず録音をとっておくことが重要です。後に「解雇だった」などと主張され争われるケースに備えるためです。
離職票・雇用保険関連書類の正確な記入方法
退職勧奨に応じた従業員の離職票作成では、「4 事業主からの働きかけによるもの (3)希望退職の募集又は退職勧奨」にチェックを入れます。退職勧奨の理由が事業縮小の場合は①を選択し、その他の場合は②欄を選択します。具体的事情記載欄には「退職勧奨による合意退職」と記載すれば足ります。
離職票の「具体的事情記載欄」では、単に「会社都合による退職」だけでなく、「事業の縮小により退職勧奨を行い、合意に基づき退職」など、より具体的に状況を説明することが望ましいでしょう。
記入ミスがあった場合は、二重線で消して訂正印を押し、正しい内容を記入します。修正テープなどの使用は避けてください。ハローワークから問い合わせがあった場合は、事実に基づき誠実に回答することが重要です。離職証明書の記載内容と退職合意書や退職届の内容に矛盾がないよう、整合性も確認しましょう。
退職合意書の作成と重要記載事項
退職勧奨では、口頭の合意だけでなく必ず退職合意書を作成しましょう。合意書には以下の基本事項を記載します。
さらに、トラブル防止のために以下の特約条項も検討します。
合意書は2通作成し、会社と従業員が各1通保管します。作成前に従業員に十分な検討時間を与え、内容をしっかり理解した上で署名してもらうことが大切です。
退職届の取得と適切な文言
退職勧奨に応じた場合でも、退職届を提出してもらうことが望ましいです。退職届と退職合意書の違いは、退職届が従業員からの意思表示であるのに対し、合意書は双方の合意を示す文書であるという点です。
退職届は従業員の自筆で作成してもらうのが基本ですが、記載内容に問題がないよう事前に確認しておきましょう。特に注意すべきは退職理由の記載です。「一身上の都合により」という表現ではなく、「会社からの退職勧奨に応じて」と会社都合であることを明記してもらいます。
退職届の例文としては「私は、貴社からの退職勧奨に応じて、〇〇年〇〇月〇〇日をもって退職いたします」という形が考えられます。ただし、退職勧奨によって合意が得られたら、速やかに退職届の提出を求めるとともに、退職合意書に署名してもらうことが重要です。口頭での合意だけでは不十分です。
退職勧奨に関するトラブル事例と対応策
ここでは、退職勧奨に関連して実際に発生したトラブル事例とその対応策について解説します。適切な手続きを踏んだつもりでも、方法や言動によっては「違法な退職強要」と判断されるリスクがあります。実際の裁判例から何が問題とされたのかを学び、労働局への申立てへの対応方法、従業員から拒否された場合の次の一手まで、実践的な知識を身につけておきましょう。これらの事例から教訓を得ることで、法的リスクを最小化し、円満な人事施策を実行するための具体的なヒントが得られます。

違法な退職勧奨と判断された裁判例の分析
退職勧奨の方法によっては、裁判で違法と判断されるケースがあります。代表的な判例として「日本航空事件」(東京地判 平成23年10月31日)があります。この事件では、明確に自主退職しない意思を示したにもかかわらず強い直接的な表現を用いたり、懲戒免職の可能性を示唆したりする退職勧奨が違法と判断され、40万円の慰謝料の支払いが命じられました。
また「住友林業事件」(平成11年7月19日大阪地方裁判所決定)では、長期間業績のない従業員に対する退職勧奨は企業として当然のことであり、面談を重ねて最終的に退職勧奨に至ったことはやむを得ない措置と判断されています。これらの判例から、退職勧奨の方法や状況によって適法・違法の判断が分かれることがわかります。
これらの事例から学ぶべき教訓は、退職勧奨は「従業員の自由な意思決定を尊重」した形で行うべきということです。短期間での頻繁な面談、長時間の説得、不利益な処遇変更などは避け、十分な検討期間を与えることが重要です。また、面談内容を記録に残し、複数人で対応するなど、後々の証拠を確保する工夫も必要です。
労働局への申立てへの対応と解決アプローチ
退職勧奨を受けた従業員が労働局に「パワハラ」や「退職強要」として申立てを行うケースもあります。この場合、労働局から事情聴取の連絡が来ることがあるため、初期対応が非常に重要となります。
まず、申立てを受けた場合は、社内で事実関係を早急に整理しましょう。面談の記録、メールのやり取り、勤怠記録などの客観的資料を集め、時系列で整理します。言った・言わないの水掛け論を避けるためにも、文書による記録が重要な証拠となります。
労働局の調査に対しては、事実に基づき誠実に回答することが基本です。ただし、必要に応じて労働問題に詳しい弁護士に相談の上で対応することが望ましいでしょう。また、労働局のあっせんは強制力がないものの、解決の機会として前向きに捉えることも検討すべきです。和解金の支払いが必要になる場合もありますが、裁判に発展するよりも早期解決できるメリットもあります。
退職勧奨を拒否された場合の適切な対応
退職勧奨を従業員が拒否した場合、まず冷静に対応することが重要です。強引に勧奨を続けることは退職強要と判断されるリスクが高まるため避けましょう。下関商業高校事件の最高裁判決では、退職勧奨を拒否している従業員に対して短期間に多数回、長時間の退職勧奨を行ったことが違法と判断されています。一定の冷却期間を置いた後、状況に応じた次の対応を検討します。
対応策としては、まず改めて退職条件の見直しを検討します。特別退職金の上乗せや再就職支援、就職活動を見込んだ退職日の設定など、条件を改善することで合意に至るケースもあります。また、配置転換や業務内容の変更も選択肢ですが、嫌がらせ的な配置転換や仕事の取り上げは違法な退職勧奨と判断されるリスクがあるため避けるべきです。
どうしても合意に至らない場合で、正当な理由(能力不足など)がある場合は、解雇も最終手段として検討する場合もあります。ただし、解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要となり、高いハードルがあることを認識しておく必要があります。人事考課や指導記録など、解雇の合理性を裏付ける資料の蓄積も重要となるでしょう。
専門家への相談タイミングと選び方
退職勧奨に関しては、専門家への早期相談が問題回避の鍵となります。特に以下のようなケースでは専門家への相談を検討しましょう。
専門家としては、弁護士と社会保険労務士の両方の視点が有効です。弁護士は法的リスク評価や交渉戦略、トラブル発生時の対応に強みがある一方、社会保険労務士は雇用保険や離職票などの実務手続き、労働行政との調整に精通しています。特に労働問題を専門とする弁護士や、紛争解決業務に対応している特定社会保険労務士を選ぶことが望ましいでしょう。
相談する際は、就業規則、退職金規程、対象者の人事評価資料、過去の退職事例などの資料を準備しておくと、より具体的なアドバイスが得られます。初回相談は無料のところも多いので、複数の専門家に相談し、相性の良い専門家を見つけることも大切です。
まとめ
ここまで退職勧奨に関する法的位置づけや実務的な影響、適切な進め方、そしてトラブル事例と対応策について詳しく解説してきました。この記事がビジネスの現場で直面する人事施策の検討に役立てば幸いです。退職勧奨は従業員と企業の双方にとって大きな転機となるものであり、適切に実施することで互いの信頼関係を損なうことなく、次のステップへ進むことができます。改めて重要なポイントを確認しておきましょう。
- 退職勧奨は発意が会社側にあることから、法的には「会社都合退職」として扱うのが原則であり、自己都合扱いにすると損害賠償請求などのリスクが生じる
- 会社都合退職と自己都合退職では、雇用保険の給付制限期間や給付日数に大きな違いがあり、特に待機期間は会社都合が7日に対し自己都合は実質3カ月となる
- 適法な退職勧奨を実施するには事前の準備と方針共有、適切な言葉遣いでの面談、正確な書類作成が重要であり、「強要」と判断されない配慮が必要
- 違法な退職勧奨と判断された事例から学び、労働局への申立てや勧奨拒否時には冷静に対応し、必要に応じて専門家への相談を検討する
退職勧奨は、経営上の必要性から実施されることが多いものですが、その実施方法によっては法的リスクを招くこともあります。会社都合として適切に取り扱うことは、単なる法令遵守以上に、企業の社会的信頼や残留する従業員のモチベーションにも影響する重要な判断です。従業員の尊厳を尊重しながら、法的要件を満たす形で実施することで、企業と従業員の双方にとって納得のいく結果を目指しましょう。
●● この記事の監修者 ●●

田渕花純 – Kasumi Tabuchi –
KT社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士。国内・外資系航空会社を経て、化粧品販売業に従事。その後、大手社会保険労務士法人にてキャリアを積み、スタートアップ企業や建設業向けの労務手続きを専門的に担当。現在は「ヒトの力で企業の未来を切り開く」という理念のもと、会社設立時の労働保険・社会保険申請業務、建設業の労災保険手続きなど、事業主が安心して本業に専念できるよう丁寧かつスピーディなサポートを提供している。社会保険手続き、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングなど幅広い業務に精通。