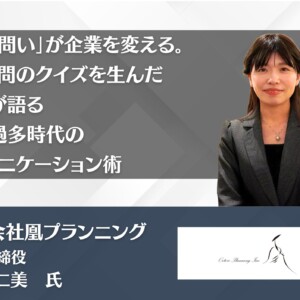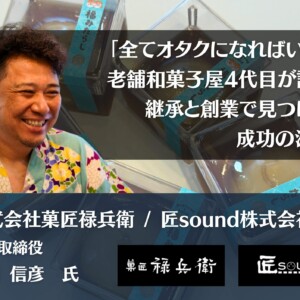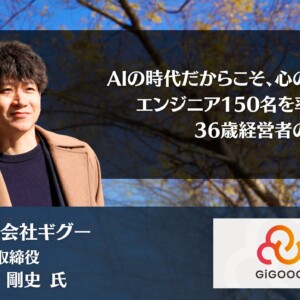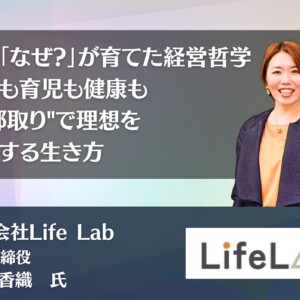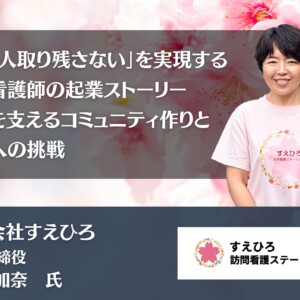自己犠牲ではなく、歓びの循環を──手動メール150通に込める、NPO代表の信念|NPO法人JOY GIFT
「一人ひとりとのつながりを『数字』ではなく、『顔』や『一人の人間』として感じていたいんです」——。
NPO法人JOY GIFT代表理事の下中恵さんは、穏やかな表情でそう語ります。インドの子どもたち208人の教育を支援する彼女は、150人の支援者への連絡を今も手動で行っています。効率化が叫ばれる時代に、あえて「温度感」を選ぶ経営判断。その背景には、13年間積み重ねてきた「歓びの循環」という揺るぎない信念がありました。
支援者150人へ、今日も手動でメールを送る理由
下中さんは年に2〜3回、子どもたちの通知表や写真、動画を届けるタイミングで、150人の支援者一人ひとりにメッセージを送っています。一斉送信メールのシステムを使えば数分で終わる作業を、あえて一通ずつ手作業で送り続けているのです。
「支援者の方はそれぞれに想いや背景があって、JOY GIFTに関わってくださっています。だからこそ、一斉送信ではなく、メッセージ一つひとつに心を込めたいんです」
下中さんが「効率化」だけを追い求めない理由は明確です。機械的な一斉送信では、支援者の心に届かない。そして、インドの子どもたちも「日本という遠い国から、自分たちを応援してくれている人がいる」と感じることができない。
実は、下中さん自身が他の団体に寄付をした経験があります。定型文のお礼メールが一通届いただけだった時と、電話で直接「本当にありがとうございます」と言われた時の感覚は、まったく違ったのです。
「いろんなところに寄付をした経験がありますが、定型メールでのお礼と、実際に電話で『本当にありがとうございます』と言われるのとでは、感じるものが全然違うんです」
感謝の気持ちがしっかり伝わることで、支援者は「応援できてよかった。また、来年も見守りたい」と思える。それが「歓びの循環」の一つです。
80人のシェアハウスで学んだ、多様性と信頼関係
下中さんが「つながり」を大切にするのには、理由があります。彼女が育った環境は、一般的な家庭とはまったく違っていました。
「父親はイギリス人で、私はシングルマザーの母に育てられ、3歳の時に父親と出会いました。そして6人兄弟の長女になったんです」
下中さんの「家族」は、最大80人が一緒に暮らす巨大なシェアハウスだったのです。
「家族だけっていうよりはコミュニティーでした。共同生活、今でいう巨大なシェアハウスみたいな感じで、多い時は80人とか、少ない時は20人とか30人とか。いくつかの家族が一緒に組んで、協力して子育てするような形だったんです」
教育も特徴的でした。日本の学校には小学4、5、6年生の3年間だけ通ったことありますが、それ以外は「ホームスクーリング」で英語で学びました。
毎日80人と顔を合わせる生活。当然、気が合わない人もいます。でも、逃げることはできません。
「一緒に住んでいるから、喧嘩をしても、気が合わない人がいても、話し合うしかないんです。毎日顔を合わせるから、コミュニケーションは身につきます」
この環境で下中さんが始めたのが、「チェックリスト」でした。80人もいれば、自分ではコントロールできないことばかり。そこで、小さな達成感を積み重ねることで、心のバランスを保っていたのです。この「スモールウィン」の習慣が、後にJOY GIFT運営の基盤になります。
さらに、共同生活を運営していたクリスチャンの団体では、奉仕活動が日常に組み込まれていました。老人ホームを訪問する、ホームレスの炊き出しに参加する——それは特別なことではなく、当たり前の日常でした。
「奉仕の考え方が、教育の基盤として自然に組み込まれていました。だから中学生の時にインドに行くことになった時も、とても自然な流れだったんです」

中学生のインドで見た笑顔が、すべての原点
下中さんが初めてインドを訪れたのは、中学生の時でした。
「ボランティア活動の一環で、トイレや電気すらない地域に学校を建てている団体に同行して、ある村で運動会を開催したんです」
最初は「助けてあげなきゃ」と思っていた下中さん。ところが、子どもたちと接するうちに、価値観は根底から揺さぶられます。
「彼らと目が合うと、純粋な瞳でこちらを見つめ、満面の笑顔を返してくれる子どもたちがいたんです。そして運動会が始まると、みんなが夢中になって走り、笑い、心から楽しんでいた」
トイレもない、電気もない。日本の基準で見れば「何もない」環境です。でも、その子どもたちの笑顔は、どこまでもまっすぐでした。
「『豊かさって何だろう』って考えさせられたんです。何も持っていないのに、こんなに純粋な笑顔を見せてくれる」
そして下中さんは、ある気づきを得ました。
「『与えているつもりでも、人の笑顔に関われると、自分の方が幸せになれるんだ』って」
13年間の「いつか」を「今」に変えた日
しかし、この体験の後すぐに活動を始めたわけではありません。下中さんは長い間、「いつか何かできたら」という想いを抱き続けていました。
転機が訪れたのは2012年。下中さんが20代前半の時、知り合いのアメリカ人起業家から声がかかりました。
「自分も支援活動をしたいけれど、大きな団体では信頼できない。メグは現地に知り合いがいるなら、一緒に見に行きたい」
13年ぶりにインドを訪れると、かつて訪れた幼稚園はしっかりと継続され、2、3校に増えていました。運営者の真剣な姿勢を目の当たりにして、下中さんの心が動きました。
「その時私も『今できることから始めよう』と決まったんです」
13年間抱き続けてきた「いつか」が、「今」になった瞬間でした。
「今できること」を、スモールウィンで積み重ねる
下中さんが最も大切にしているキーワード、それが「今できること」です。
「『いつか何かしたい』と思っているけど、今の状況だとやりにくいとか、どこから始めればいいかわからないとか、そういう悩みをすごく聞くんです」
完璧な計画を立てようとして、結局何も始められない。そんな人が多いのです。
下中さんが提案するのは、「完璧な構想がなくても、自分の心が動くことに対して『今できること』を実践する」という考え方。2012年、支援を始めた子どもは1人か2人でした。それが現在では208人になっています。
「本当に1人、2人から始まって、スケールが小さくても続けることだけを決めてスモールウィンを積み重ねてきた結果なんです」
一人の子どもを10年生まで継続支援するには、年間約9万円が必要です。これをプレッシャーに感じる人もいるため、月2,000円から参加できる別の仕組みも作りました。
「なるべくハードル低くしたかったんです。『今できること』っていうのがテーマだから」
周囲からクラウドファンディングを勧められたこともありましたが、下中さんは断りました。
「たくさん集めたいわけじゃなくて、想いを集めたいんです。一回限り大きく集まっても、継続しないと意味がない」
さらに、もう一つの理由がありました。
「クラウドファンディングって、準備も運営もすごく大変なんです。一人ではとてもできません」
自分の限界を知り、持続可能な範囲で活動する。この姿勢こそが、13年間の継続を可能にしてきたのです。

一対一のマッチングが生む、支援の循環
JOY GIFTの支援の仕組みは、極めてシンプルです。現地NGOが運営する幼稚園を卒業した子どもたちの中から、特にニーズのある子どもをピックアップしてもらい、日本の支援者とマッチングする。
「なんか一対一の方が親近感湧くし、私もそっちの方がいいなと思ったという単純な理由」
支援者には、子どもの写真、プロフィール、家族構成が届きます。さらに、お礼の写真や動画、年に2回の成績表まで。そして機会があれば、実際に会いに行くこともできます。
「マッチングして実際に会いに行けたりとかする時の瞬間が一番嬉しい」
この深いつながりを可能にしているのが、下中さんが徹底してきた「透明性」です。驚くべきことに、NPO法人化する前、150人規模になるまで、彼女は個人名義の口座で支援金を集めていました。
「組織の口座もなくて、個人名でやってた。下中恵の口座に振り込んでたわけだから。それは信頼ないとしないですよ」
年間9万円という金額を、個人口座に振り込み続ける人々。そこには圧倒的な信頼関係がありました。
見えない資産「信頼関係」を、どう築いてきたか
見えない資産は何かと尋ねると、下中さんは即座に答えました。
「信頼関係ですね。やっぱりお金を集めるのも、信頼がないと集められないですから」
しかし、この信頼関係は偶然ではありません。意図的な選択の積み重ねによって築かれてきたのです。
一つは、透明性の徹底です。もう一つは、「歓びの循環」を守るための選択です。
下中さんの周りには、ボランティア活動をしている人が多くいました。しかし、その中には辛そうな人、自分をすり減らしている人も少なくありませんでした。
「私はマザーテレサじゃないし、そこまでできないなと思って。でもできる範囲で何かしたい想いはあったから。それをいかに楽しくできるのか、ずっと考えていました」
だからこそ、下中さんは仕事を別に持ち、支援活動は人生の一部として位置づけました。そして、自分がやりたいと思ったこと以外は引き受けない。
NPO法人化が遅れたのも、この理由からでした。サポートできるメンバーが揃うまで待ち、自己犠牲にならないタイミングを選んだのです。
現地のパートナー選びも、信頼関係が最重視されます。下中さんは17歳の時から知り合っていた団体の創設者と、長年の関係を築いてきました。
その団体は、シンプルな言葉を基盤にすべての組織を作っています。
「Be kind, be gentle, be giving and forgiving」——優しく、親切に、与えて、許そう。
「それを基盤に組織を全部作っているんです。子どもたちもみんな、毎日『I am kind, I am gentle, I am giving and forgiving』って言っています」
下中さんは実感を込めて語ります。
「国境を越えても、やっぱり理念が大事なんですね」

これから目指す未来──教育から就職支援へ
活動開始から13年。最初に支援した子どもたちは、もう少しで就職を考える年齢になっています。
「今までは小中学校の10年間を支援するので精一杯でした。でも、もう13年も経っているんです。最初に支援した子たちはもう大人になって、就職を考える年齢です。だから次は、就職のサポートもできたらいいなと思っています」
インドには、日本と大きく異なる文化があります。
「インドには、学生がアルバイトをする文化がないんです。日本だと大学生が飲食店などでバイトするのは普通ですよね。でもインドでは、学費も生活費も卒業まで親が出すのが当たり前」
働いた経験がないまま卒業してしまうため、就職活動がうまくいかない。大学を出ても仕事が見つからない若者が増えているのです。
そこで構想しているのが、インドで展開している日本企業との連携です。
「インドで展開している日本企業に就職するきっかけを作れたらいいなと思っています」
ただし、下中さんは規模拡大よりも大切にしたいことがあります。
「やたら人数を増やすというよりは、ちゃんと最後まで丁寧にという方が強いですね。量より質です」
実は、下中さんが本当に実現したいことは、インドの子どもたちの数を増やすことではありません。もっと大きな目的があるのです。
「JOY GIFTは、『いつか何かしたい』と思っている人が、『今できること』を小さく積み重ねていく活動なんです。実は、インドの子どもたちを支援することと同じくらい、日本の人たちが一歩を踏み出すきっかけを作ることに意味があると思っています。それこそが、日本社会への貢献だと思っているんです」
日本では、多くの人が「周りの役に立つ何か」という想いを抱きながらも、一歩を踏み出せずにいます。しかし、下中さんは確信しています。
「世界で活躍している多くの人たちは、何も持っていない時期からすでに誰かに貢献していました。その姿勢こそが、結果的に成功へとつながっているように思います」
だからこそ、完璧な構想がなくても、自分の心が動くことに「今できること」を実践できるきっかけを届けていきたい。
「一人ひとりが小さな行動を通して、『自己犠牲ではなく、喜びから湧き上がる行動』の循環が広がっていく。そんな社会をつくっていけたらと思っています」
幸せとは、「自己実現」
最後に、下中さんに幸せとは何かを尋ねました。
「自己実現かな。思ったことを形にする。創造できる。それができることです」
やりたいのにできない——ちょっとずつでも想いを実現している実感を持つこと。それこそが幸せだと言います。
「自分だけの幸せは最初のステップだとしても、そこから周りの人、家族とか、自然と広がっていくわけですから」
下中さんが始めた小さな輪が、少しずつ、確実に広がっています。
コントリからのメッセージ
オートメーション化が進み、効率が追求される現代において、下中恵さんの選択は一見非合理的に見えるかもしれません。150通の手動メール、一対一のマッチング、個人口座での運営——。
しかし、その「非効率」の中にこそ、持続可能な支援の本質がありました。温度感、信頼関係、歓びの循環。これらの見えない資産は、効率化では決して得られないものです。
80人のシェアハウスで多様性を学び、インドで「与える喜び」に目覚め、スモールウィンを積み重ねてきた下中さん。彼女の13年間の歩みは、「今できること」を実践し続けることの力を証明しています。
自己犠牲ではなく、喜びから始まる支援。一人ひとりとのつながりを大切にする経営。そして、「いつか」ではなく「今」を生きる勇気。
下中さんの物語は、社会起業だけでなく、すべての経営者、すべてのビジネスパーソンに問いかけています。
「あなたの『今できること』は何ですか?」
その小さな一歩が、やがて大きな歓びの循環を生み出すかもしれません。
プロフィール

NPO法人JOY GIFT
代表理事
下中 恵 – Megumi Shimonaka –
イギリス人の父と日本人の母のもと、6人兄弟の長女として岐阜県で育つ。ホームスクーリングで英語を母語として学び、多文化環境で独自の感性を磨く。中学生の時に訪れたインドで「与える喜び」に目覚め、13年前に支援活動を開始。現在は同時通訳者として活動しながら、インドの子ども208人の教育支援を通じて「自己犠牲ではなく、歓びの循環」を広げている。
ギャラリー

















会社概要
| 設立 | 2025年8月 |
| 所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町川端4丁目8番10号 |
| 従業員数 | 10人 |
| 事業内容 | インドの子どもたちへの教育支援を軸に、与える歓びと受け取る歓びの循環を広げる活動。 |
| HP | https://joygift.org/ |
あわせて読みたい関連記事
御社の想いも、
このように語りませんか?
経営に対する熱い想いがある
この事業で成し遂げたいことがある
自分の経営哲学を言葉にしたい
そんな経営者の方を、コントリは探しています。
インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。
条件は「熱い想い」があることだけです。
経営者インタビューに応募する
御社の「想い」を聞かせてください。
- インタビュー・記事制作・公開すべて無料
- 3営業日以内に審査結果をご連絡
- 売上規模・業種・知名度は不問
※無理な営業は一切いたしません
発信を自社で続けられる
仕組みを作りたい方へ
発信を「外注」から「内製化」へ