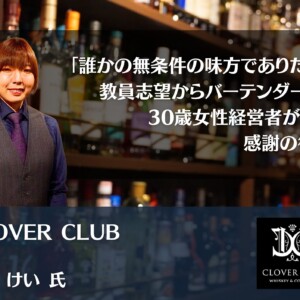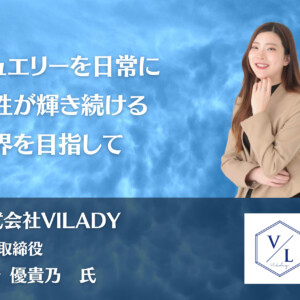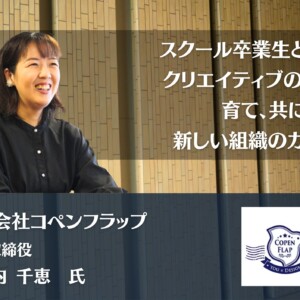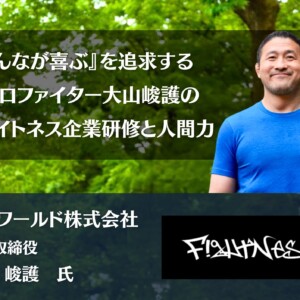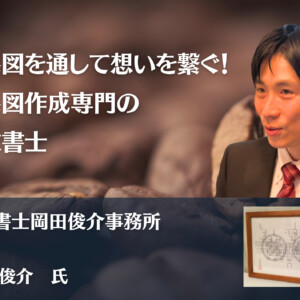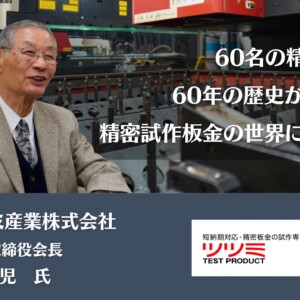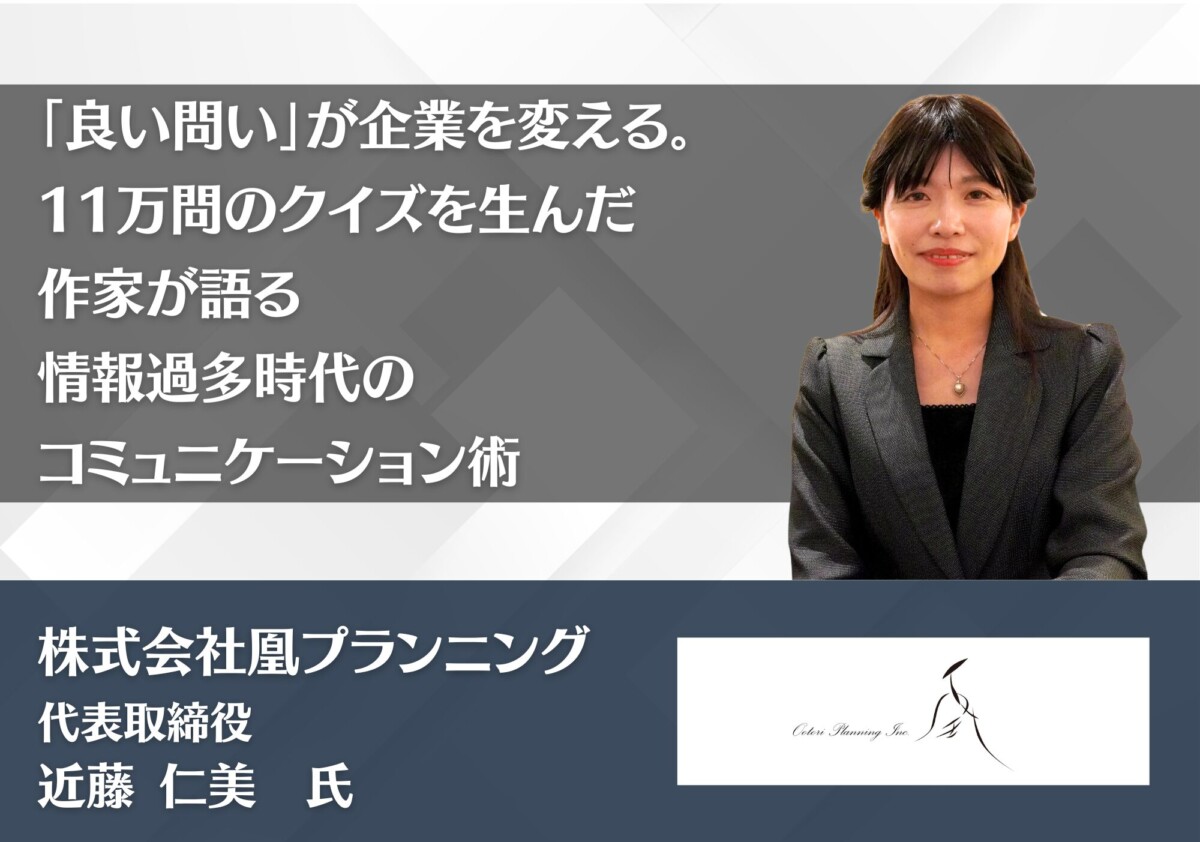
「良い問い」が企業を変える。11万問のクイズを生んだ作家が語る、情報過多時代のコミュニケーション術|株式会社凰プランニング
「私たちは1日に約3万5000回の意思決定をしています。その決定の前には、基本的に『問い』が存在するんです」——。
株式会社凰プランニング代表取締役の近藤仁美氏は、これまでに11万問以上のクイズを制作してきたクイズ作家として、独自の視点で企業のコミュニケーション課題解決に取り組んでいます。『高校生クイズ』『マジカル頭脳パワー!!2025』などの人気番組でクイズを手がけてきた一方で、企業研修や自治体イベントまで幅広く活動する近藤氏が語る「良い問い」の力とは。情報過多・AI時代だからこそ注目される、人間にしかできないコミュニケーション術をお聞きしました。
迷子から始まった「奇跡のキャリア」
近藤氏のクイズ作家としてのキャリアは、実は偶然の出会いから始まりました。三重県で育った近藤氏が大学進学で東京に出てきたとき、道に迷ってしまったのです。
「本当に迷子になってしまって」と当時を振り返る近藤氏。「そのとき助けてくれたのが、早稲田大学のクイズ研究会の人だったんです。助けてもらったお礼として『一度くらいはイベントに行かないと』と思って顔を出したのが、すべての始まりでした」
その時の様子を思い出すように、近藤氏は穏やかな表情で続けます。「当初は義理で参加したつもりだったんですが、実際にクイズの場に身を置いてみると、そこには想像以上の魅力がありました」
早稲田大学のクイズ研究会は、近藤氏のイメージを大きく覆すものでした。「クイズ研究会と聞くと、みんな真面目にクイズばかりやっているイメージがありますよね。でも実際は、クイズをやりたい人もいれば、スポーツ観戦や食べ歩きの方が好きな人もいる、色々な考え方の人が集まったサークルだったんです」
この環境が、近藤氏にとって理想的でした。教育学部で言葉について学んでいた近藤氏にとって、クイズは学問と実践の橋渡しとなる存在だったのです。
「大学2年生のとき、サークルの先輩の紹介でとある新聞のクイズ欄を担当しはじめました。これ自体は新聞の休刊ですぐに終わってしまったのですが、こうした案件に関わるうちにお客さんが私を覚えてくれて、個人あてにクイズの依頼が来るようになったんです」
学生時代から既に、近藤氏の作るクイズの品質が認められていたことがうかがえます。
11万問から見えてきた「明日話したくなる情報」の法則
これまでに制作したクイズは11万問以上。この膨大な経験から、近藤氏は「明日話したくなる情報」の法則を見出しました。
「情報を知ってもらうためには、『へえ』という感情を引き出すことが重要です」と近藤氏は力強く語ります。「基本的には、気持ちの温度が上がらないと、人は情報を記憶しませんし、話したくもなりません」
その具体例として、近藤氏は興味深い比較を示してくれました。
「例えば、『エベレストの標高は何メートルでしょう』と聞かれても、遠い土地の知らない数字が問われているため、あまりピンときません。でも『世界一高い山エベレストは、富士山いくつ分の高さでしょう』と聞かれると、急に興味が湧きませんか?」
確かに、同じ数字を聞いているにも関わらず、後者の方が圧倒的に興味をそそられます。
「知らない情報を、知っている情報と組み合わせて説明する。これが『明日話したくなる』情報作りの基本なんです」
さらに、近藤氏はもう一つの例を挙げました。
「『ブルターニュ地方で有名なお菓子の名前を当ててください』と言われても、全然興味が湧かないですよね。でも『フランス皇帝ナポレオンが毎年1年の運を占うために作っていたお菓子は何でしょう』と言われたら、急に知りたくなりませんか?」
答えはクレープ。フライパンでクレープをひっくり返し、うまくできると1年幸せになるという言い伝えがあり、ナポレオンもこれを行っていたそうです。
「生活に身近な情報と歴史上の人物を結びつけることで、同じ情報でも格段に興味深くなるんです」と、目を輝かせながら説明する近藤氏。このような工夫を11万問にわたって積み重ねてきた経験が、現在の事業の基盤となっています。

「良い問い」が企業の意思決定を変える瞬間
近藤氏が企業に提供する価値は、単なるクイズ作成にとどまりません。「良い問い」を立てることで、企業の意思決定そのものを変える支援を行っているのです。
「意思決定の前には、基本的に問いが発生しています」と近藤氏は説明します。「1日3万5000回の意思決定のうち、たとえ1割でも良い問いに変えることができれば、仕事や生活の質は大きく変わります」
その実例として、近藤氏は印象的なエピソードを語ってくれました。ある自治体からの依頼で、地元出身の歴史上の人物を大河ドラマの主人公にしたいという企画に関わったときのことです。
「この企画では、地元の歴史上の人物が10回以上大河ドラマに出ていることを確認する必要がありました。そこで、自治体の担当さんは、『この人物は何回大河ドラマに出ていますか』とNHKに問い合わせました。でも、NHKからは『大河ドラマは数多くあり、全て調査するのは困難です』とお断りの連絡が来てしまったんです」
表情を曇らせながら、近藤氏は続けます。「そこで、聞き方を変えることを提案しました」
「まず、ネットを使って、大河ドラマで対象の人物を演じた俳優を10人調べました。それをリストにし、『この人たちは、大河ドラマでこの役をやったことがありますか?』と質問したんです」
この問いの立て方の変更により、NHKからは「全員、その人物として出演したことがあります」という回答を得ることができました。
「相手の負担にならない聞き方をすることで、欲しい情報を引き出しやすくなるんです」と、近藤氏は力強い口調で語ります。「目的から逆算して、どう問うかを考える。これが『良い問い』の本質です」
現在では、このような質問力に関する研修依頼も増えており、近藤氏の活動は全国に広がっています。8月には大阪でも研修を実施するなど、精力的に活動を展開しています。
AI時代に人間だけができること:「間」の演出と感情の読み取り
情報過多・AI時代の現在、近藤氏はクイズの新たな価値を見出しています。
「クイズは『入口』のようなものです」と近藤氏は説明します。「歴史、科学、文化、スポーツなど、いろんな分野の『美味しいとこ取り』をしているんです。だから、情報が溢れすぎて何を調べていいかわからない今の時代に、『あ、これ面白そう』という自分の興味の方向性を見つけるのにぴったりなんです」
しかし、より重要なのは人間にしかできない領域だと近藤氏は強調します。
「クイズにおいては『間』の演出が重要です。この人はもう答えるか、まだ答えなさそうだからもう1つヒントを出すか。これは、データではなく経験を積んだ人間だからこその領域なんです」
実際に、クイズ番組の収録現場では、近藤氏自身が臨機応変な対応を行っています。
「収録中、私は問題を出している人と答えている人だけでなく、観客の反応も見ています。観客が盛り上がっているかも重要な要素の一つです。みんな『長いな』という雰囲気になっていたら、できるだけ展開を早くしますし、逆に盛り上がっている時は間を長めに取ったりします」
このような繊細な調整は、まさに人間にしかできない技術です。
「音楽とクイズは似ていると思うんです」と、近藤氏は興味深い比較をします。「どちらもエンターテイメントであり、理論はあるけれど、その理論を輝かせるかどうかはプレーヤーの経験と感性にかかっているんです」
AI技術の発達について問うと、近藤氏は冷静に分析します。
「AIは確かに優秀ですが、各情報を同じ重さで見てしまう傾向があります。でも、人間には思いやズレ、グレーな部分があって、それこそが面白さの源泉なんです。データから見れば単なるズレでも、その部分こそ特徴や感情が伝わるポイントになることが多いんです」

組織に「良い問い」の文化を根付かせる方法
近藤氏の支援は、個別のクイズ作成から組織文化の変革まで幅広く及んでいます。組織に「良い問い」の文化を根付かせるためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。
「まず大前提として、心理的安全性が高い環境が必要です」と近藤氏は断言します。「気軽に質問ができる環境でなければ、良い問いは生まれません」
そのために重要なのは、リーダーの姿勢だと近藤氏は説明します。
「特にトップに立つ人は、自分から『当たり前』を疑う質問をしていくことが大切です。前提とされてきたことは本当に正しいのか、今行っている業務にはどんな意義があるのか。そうした問いかけを率先して行う必要があります」
実際に、このような取り組みの効果は大きいと近藤氏は実感しています。
「組織の中で『そういえば、なぜこの作業をやっているんでしたっけ?』といった今更な質問ができるようになると、意外な発見があることが多いんです。同じ前提を共有していたはずが、実は個々の認識が違った、ということも珍しくありません」
穏やかな表情で、近藤氏は続けます。「形式的な質問ではなく、本当に疑問に思っていることを気軽に口にできる。そんな環境づくりが、組織の成長につながるんです」
情報過多時代のクイズの新たな価値
現代の情報過多社会において、クイズはコミュニケーションツールとして新たな価値を発揮しています。
「弊社では、クイズをコミュニケーションの手段と捉えています。届けたい情報を楽しく、明日人に話したくなる形で伝えるのが得意です」と近藤氏は説明します。
企業の周年行事や映画・アニメのプロモーションイベントなど、様々な場面でクイズが活用されている現状を見ると、その需要の高さがうかがえます。
「企業研修でも、情報を一方的に伝えるのではなく、クイズ形式にすることで参加者の興味を引き、記憶に残りやすくする効果があります」と近藤氏は実用的な活用例を挙げます。
現在では、宣伝や広報を目的とした企業と近藤氏は、まさにWin-Winの関係だと言えます。
「企業さんにとっては、クイズを媒介にして情報を広めるという目的を達成できる。私たちにとっては、情報の拡散を通してクイズの可能性を広げていける。お互いが望む目標に向かえるんです」
未来への挑戦:「問い」の力を社会に広める
最後に、今後のビジョンについて伺いました。近藤氏の表情に、強い使命感が浮かびます。
「今後は、仕事や生活に役立つ問いの在り方を、少しずつ伝えていければと思っています」
近藤氏が目指すのは、クイズの枠を超えた「問い」の普及です。
「これまでクイズや雑学を上手に使うことをやってきましたが、それ以外にも仕事や生活で使える『問い』のノウハウがたくさんあるんです。でも、それがまだ外に出ていない状態なんです」
実際に、質問力に関する研修依頼は増加傾向にあり、近藤氏の活動領域は着実に広がっています。
また、データや論理に頼りがちな現代において、近藤氏が大切にしているのは感情と直感の力です。
「感情が湧くかどうか、これは非常に大切だと思っています」と、真剣な表情で語る近藤氏。「データを信じたい瞬間は確かにあるけれど、飽和するデータのなかから選ばれるのは、多くの場合、受け取り手の感情が動いた情報です。また、ものごとを判断するとき、最初に「良い」と思ったものが結局最適解だった、ということはよくあります。論理を整えるために足踏みし続けるくらいなら、直感で「これだ」と思ったものに手を伸ばし、行動を蓄積する方が結果につながることが多いです」
この考え方は、近藤氏の経営哲学そのものでもあります。11万問を超えるクイズ制作という膨大な経験の中で培われた、人間への深い理解と信頼。それが、AI時代だからこそ輝く近藤氏の強みなのです。

コントリからのメッセージ
迷子から始まった偶然のキャリアを、自分らしい事業として昇華させた近藤仁美氏。彼女が語る「良い問い」の力は、単なるテクニックを超えて、人と人とのつながりを深める本質的なコミュニケーションの在り方を示しています。
情報が溢れ、AIが台頭する時代だからこそ、人間にしかできない「感情を動かす」「間を読む」「相手を思いやる」といった能力の価値が際立ちます。近藤氏の実践する「明日話したくなる情報」作りや「良い問い」の立て方は、どんな業界の経営者にとっても学びの多い示唆に富んでいます。
「データで説得するだけでなく、心を動かせるか」という近藤氏の言葉は、効率化や数値化が重視される現代のビジネスシーンにおいて、データ活用の本質的な目的を問い直すきっかけを与えてくれます。読者の皆様にとって、近藤氏との出会いが新たなコミュニケーションの可能性を開く契機となることを願っています。
プロフィール
株式会社凰プランニング
代表取締役
近藤 仁美 – Hitomi Kondo –
三重県出身。早稲田大学教育学部および同大学院修了。大学進学で上京した際に道に迷い、助けてくれたクイズ研究会のメンバーとの出会いがきっかけでクイズの世界に入る。大学2年生から企業案件を受注し始め、現在までに11万問以上のクイズを制作。『高校生クイズ』『マジカル頭脳パワー!!2025』『せっかち勉強』などの人気番組でクイズ・雑学を担当。著書7冊。
「クイズをコミュニケーションの手段」と捉え、企業研修、自治体イベント、プロモーション企画など幅広く活動。「届けたい情報を楽しく・明日人に話したくなる形で伝える」ことを得意とし、全国各地で質問力研修なども実施している。
ギャラリー









会社概要
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門三丁目18番6-614号 |
| 事業内容 | クイズの作成 各種イベント、セミナー等の企画、開催、運営及び管理 各種プランディング業務 各種プロモーション業務 各種リサーチ業務 |
| HP | https://www.ootori-p.jp/ |
関連記事
本記事で紹介した「良い問い」の力やコミュニケーション技術に関心のある経営者の方には、以下のインタビュー記事もおすすめです。
御社の想いも、
このように語りませんか?
経営に対する熱い想いがある
この事業で成し遂げたいことがある
自分の経営哲学を言葉にしたい
そんな経営者の方を、コントリは探しています。
インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。
条件は「熱い想い」があることだけです。
経営者インタビューに応募する
御社の「想い」を聞かせてください。
- インタビュー・記事制作・公開すべて無料
- 3営業日以内に審査結果をご連絡
- 売上規模・業種・知名度は不問
※無理な営業は一切いたしません
発信を自社で続けられる
仕組みを作りたい方へ
発信を「外注」から「内製化」へ