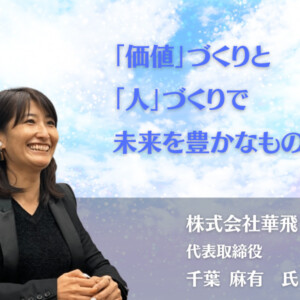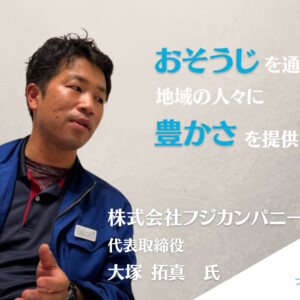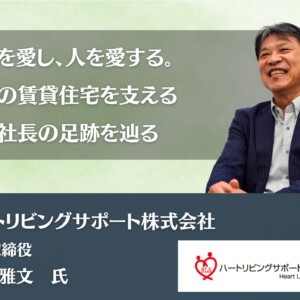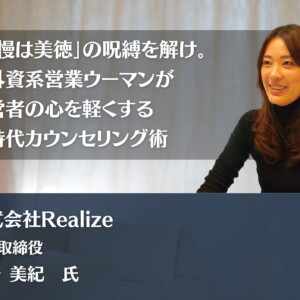47都道府県、すべてに生きる人を支える。「ケア」の光を灯し続ける経営哲学|株式会社土屋
株式会社土屋の高浜敏之社長が、介護福祉の現場からスタートし、経営者として事業を急成長させる中で貫いてきたのは、「持続させるための経済的センス」と「失ってはならない道徳の心」。
本インタビューでは、社名の由来から事業の成り立ち、そして社会的な責任まで、事業成長の各フェーズに焦点を当ててお話を伺いました。M&Aの本質や、福祉と経済のバランス、社会貢献の在り方に至るまで、高浜社長の言葉には、哲学的な思索と実践に基づく確かな信念が込められています。
目次
社名に込めた思いと出会い

本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速、会社名についておうかがいします。株式会社「土屋」というのは、社長のお名前ではありませんよね。社名の由来を教えてください。

もともと私は、約10年前に立ち上げメンバーとして参加した会社がありました。そこは介護系のスタートアップベンチャーで、その事業の始まりは東京都にある病院の空きスペースを活用する形でした。
病院の院長先生は産婦人科の医師でしたが、90歳を迎え、引退されることになったのです。その結果、病院の建物が空きスペースとなりました。当時の経営者がその空きスペースを借り受け、改修して高齢者向けのデイサービスセンターを開設したのが、そのベンチャーです。
私は施設の管理責任者を務めることになったのですが、その病院の名前が「土屋産婦人科」だったので、デイサービスの名称末に「土屋」を残した形で事業を開始しました。
このデイサービス事業が始まったのが2012年です。

社長ご自身は、それ以前も介護業界で働かれていたのですか。

その前の私の経歴としては、大学卒業後すぐに介護業界に入り、障害福祉、特に重度訪問介護のケアワーカーとしてキャリアをスタートさせました。そして2014年、障害福祉運動のパイオニア的存在だったリーダーが亡くなるなどの出来事をきっかけに、障害福祉事業を立ち上げたいと考えました
当時、私はデイサービスの管理者をしていましたが、その病院はスペースが広かったため、一部を重度訪問介護の事業部門として活用することにしました。結果的に、この新しい事業部門が大きなニーズを持ち、急速に拡大していきました。そして、このデイサービスが2014年に正式に障害福祉事業を展開する拠点となりました。
その後、2020年に現在の会社がスピンアウトして設立される際、それまでの事業を引き継ぐ形となり、社名も「土屋」をそのまま使用することになりました。これは単に名前を継承したということではありません。「土屋産婦人科」が地域医療において先駆的な取り組みをしていたこと、そして我々の現在の事業である地域医療・地域福祉と重なる部分があることが理由です。その記憶や理念を会社の名前に残すことに意味があると考えました。

創業者の名をつけるのではなく、土屋産婦人科の先生へのリスペクトを込められたのですね。

そうですね。創業者の名前を社名にするケースも多いですが、それはある意味で「創業者の自我の延長」になると思っています。私は自分の名前を前面に出すのではなく、より理念的なものを会社の軸に据えたかった。だからこそ、あえて自分とは関係のない名前を選びました。

特定の個人に依存しない企業文化が、社名を選ばれた理由からも感じられました。

もちろん、実際には会社を運営していく上で、人の存在は非常に大きな影響を持ちます。完全に匿名的な集団になることは難しいですが、「特定の個人ではなく理念を重視する」という方針には意味があると思っています。私は哲学科出身なので、こうした考え方を持つようになったのかもしれません。

他の名前の検討はされなかったのですか。

他の名前も考えてはいたのですが、最終的には「土屋」を選びました。
私たちの事業は、現場での支援が中心になります。急成長して社会的にも注目を集める中、カタカナやアルファベットの社名だと「イケてる」企業というイメージが先行し、現場のリアルな環境とのギャップに挫折する人が増える可能性がありました。そこで、「土屋」という漢字表記にすることで、本当にこの業界に関心がある人だけが集まるように、ある種のフィルターとして社名が機能することを狙いました。
実際に、以前の会社名はカタカナ表記でしたが、漢字表記に変更したことでスタッフの質が向上しました。面接のマッチングが良くなり、現場との適合性も高まったと感じています。

実際どのような良い変化があったのでしょうか。

「土屋」をアルファベットやカタカナ表記にすると、少し印象が変わってしまいます。カタカナ表記だと、ブランドイメージが先行しやすく、実際の業務内容とのギャップが生じることもあります。
以前は「給料が良さそう」「成長できそう」と思って入社するものの、実際の業務と合わずに挫折するケースがありました。カタカナ表記の社名は、見た目のかっこよさを重視する人を引きつけやすかったのですが、実際の業務はそうしたイメージとは異なり、地道な仕事が求められます。そのため、現場で挫折する人が多かったのです。
一方、「土屋」という名前は、見た目の印象よりも本質を重視する人が応募しやすくなる傾向がありました。その結果、応募数は減ったものの、より適した人材が集まりやすくなりました。
また、女性の応募が増えました。男性は仕事の見た目や世間体を気にする傾向があり、特に若い男性は「介護の仕事はかっこ悪いのでは」と迷うことが多いと感じています。一方で、女性は「利用者のために働きたい」という動機を持つ人が相対的に多く、結果として女性の応募が増えました。
結果的に、現場の実態にマッチした採用ができたのではないかと思っています。
「土屋」という社名に込めた実直で本質的な価値観が届いたようで嬉しく思います。
いずれ、事業承継のタイミングで社名を変更する可能性もありますが、それは後任の経営陣に委ねるつもりです。2020年に設立してから4年で、もうすぐ5年目になりますが、私自身は、あと数年で引退する予定です。

御社の事業内容について、他社との大きな違いはどこにありますか。

私たちは重度訪問介護を24時間、365日、47都道府県で提供しています。このような事業者は他にありません。それが大きな違いです。
また、高齢福祉分野においても、定期巡回型訪問介護・診察、通所介護、訪問介護、グループホームなど、事業を広げています。これが予定通りに拡大した場合、7年から10年で、障害者ケアと高齢者ケアのバランスが均衡すると考えています。このような企業はほぼ存在していません。日本の介護企業は、障害者向けなら障害者、高齢者向けなら高齢者と、特定の分野に特化しています。しかし、弊社は、障害者も高齢者も分けず、全国的に介護サービスを提供する「トータルケアカンパニー」を目指しています。
また、弊社の特徴として、経済的価値だけでなく、道徳的価値を重視した企業経営を実践している点があります。その一環として、「ウェルビーイング委員会」「貧困問題対策委員会」「平和活動委員会」など社会問題に反応する委員会を立ち上げており、これらの活動はすべて非営利で運営されています。
また、人口が少なく介護サービスが行き届かない地域でのケア提供も重視しています。たとえば、これは経済的には負担がありますが、社会的財として重要だと考えています。
目先の金銭だけではなく、社会問題に触れ、解決を目指す。それが根幹になっています。

急成長を牽引した思索を辿る

短期間で急成長し、従業員数が2800人以上というのは驚きです。本社と現場のスタッフの割合はどうなっていますか。

従業員の90%以上が現場で働いています。登録スタッフは現在800名近くになっており、本社スタッフは100名にも満たない規模です。つまり、ほぼ現場のスタッフで構成されている企業です。

急成長の背景について、どのようにお考えですか。

まず、急成長については反省している部分もあります。成長を目指して進めてきましたが、適正な成長速度について改めて考えさせられています。
私たちの業界は、需要が供給を大きく上回る状況にあります。社会的に必要とされているにもかかわらず、十分な人材が確保できていません。その結果、必要なケアが行き届かず、悲しい事件が起こることもあります。介護は非常に価値のある行為ですが、負担が大きくなると心身ともに疲弊してしまいます。そのため、介護を「家族だけの責任」にせず、社会全体で支えることが重要です。
そうした課題を解決するために、人材を増やし、必要なケアを提供できるよう努力してきました。その結果として急成長したわけですが、一方で、成長には財務的なリスクも伴います。

具体的にはどのようなリスクでしょうか。

急成長すると、財務状況が悪化しやすくなります。特に地方銀行は急成長を嫌う傾向があります。企業が黒字であっても、キャッシュフローや自己資本比率が悪化すると、融資が受けにくくなり、黒字倒産のリスクも出てきます。成長には適正な速度があり、それを見極めることの重要性を、経営者4年目にしてようやく実感しつつあります。

そういった中で、ご自身はこの4年をどう振り返られますか。

繰り返しになりますが、成長の速度が急すぎたと感じています。成長は身の丈に合った速度で進めるべきであり、我々は少し度を超えていたのではないかと感じるというのが、正直なところです。
外部資本を入れればさらに成長を加速できるかもしれませんが、当社は未上場のまま進む方針です。未上場企業にとって、外部資本の導入や資本の分散はガバナンス上のリスクが大きいため、資本は集約すべきだと考えています。ここからは社名の通り、じっくりどっしりとした成長を目指すべきだと考えています。
実は、2024年の年末にコロナに罹患しまして、その間は仕事から離れ、本を読む時間ができました。ご存じですか、「年輪経営」という言葉。以前、伊那食品工業の『年輪経営』を読んだことがありましたが、今回改めて読み直しました。その中で、長期的な視点で物事を捉えることの重要性を再認識しました。短期的な成長を焦るのではなく、持続的な成長を大切にすべきだといま改めて感じています。

この4年の急成長について、目指していたものなのか、それとも気づいたら成長していたのか、どちらでしたか。

後者です。もともと数字を目標にすることにはあまり関心がなく、結果的にそうなったというのが実情です。我々は「需要に応える」ことを第一に考えています。売上目標を設定してそれを達成するために動いたのではなく、必要とされることに応えていった結果、成長につながったのだと思います。どちらが先かという問題ではなく、組織としての意識形成において、そのような姿勢が重要だと考えています。

それは経済と道徳のバランスとも言い換えられるでしょうか。

そうですね。昨年、同規模のグループが不正によって廃業しましたが、これは経済が前面に出すぎた結果起きたモラルハザードの典型例だと感じています。経済を追求しすぎると、我々のような事業においては、内部から崩壊するリスクがあります。経営者の価値観が薄っぺらいと、長期的な経営は難しくなります。短期間で利益を上げること自体は否定しませんが、事業によってはそうした手法が適さないものもあります。
事業を持続させなければ、支えるべき人たちを守れません。会社そのものが安定していなければ、従業員やその先の顧客を守ることはできません。売上や利益を追うことと、需要やニーズに応えることは一見同じに見えますが、本質的には異なります。
たとえば、企業価値が高まった今が最も良いタイミングだとして、事業を売却する選択をする場合、数字を追い求めてきた経営者なら、最も高く買ってくれる企業に売るでしょう。しかし、社会課題の解決を目的として事業を続けてきた経営者なら、事業の理念を守れる買い手を選ぶはずです。どちらが正しいという話ではなく、この根本的な思想が、最終的な経営判断に大きな影響を与えると考えます。

そういった意識を企業としても経営者としても持ち続けるために、どのような工夫をされていますか。

会社を派手に見せたり、輝かせたりすることは簡単ですが、私は意図的に目立たないようにしています。従業員が過度な期待やプレッシャーを感じず、安定して働ける環境を作ることが、長期的に見て最善の戦略だと考えています。
この戦略を採用しているのは、私自身の経験によるところです。私は今でこそ経営者ですが、かつては従業員でした。共に働く人々の意識がどのように形作られるのかを観察する中で、トップの思想が与える影響は非常に大きいと実感しました。
トップが右へ進めば、従業員も意識せずに右へ進んでしまうものです。つまり、トップが悪いことをすれば、従業員もそれを悪いとは思わなくなる。これは企業文化の本質的な構造であり課題です。
トップ以外の、従業員や役員が自分の置かれた環境を客観的に振り返るのは難しいものです。なぜなら、給与をもらうために働いている以上、上司の承認を得ることが重要になるからです。上司が右に行けば、逆方向には進めない。この構造がある以上、トップの責任は大きいのです。
事業を生み出すだけでなく、それが本当に価値のあるものならば、しっかりと維持していかなければなりません。我々は、重度訪問介護における最大手の1社であり、日本で唯一、47都道府県すべてでサービスを提供しています。我々の存在があるからこそ、地域で生活できる人々がいる。これは事実であり、社員の努力の賜物です。だからこそ、次に我々がすべきことは、この価値を守り続けることです。

では、ご自身はどのようにして日々の思想・考えを整えていますか。

私は大学を2つ経験しました。最初は上智大学法学部に入学しましたが中退し、その後、慶應義塾大学文学部哲学科で学びました。この学びの中で、物事の本質を見極める習慣が身についたと思います。
現在もビジネス書や心理学の本を読みますが、それに加えて思想書も読むようにしています。考える時間を持つことが、自分の軸を保つために大切だと考えています。
もう1つ、自分を振り返る習慣として大きな影響を与えたのが、アルコール依存症の治療経験です。35歳のときにアルコール依存症を患い、生活保護を受けながらリハビリを続けました。同じ病気を経験した山口達也さんとも対談したことがあります。
自助グループでは、毎日、自分の言動を振り返り言語化する作業を行います。この習慣により、自分の考えや行動を振り返り、必要に応じて修正する癖がつきました。
また、社内ではオープンな対話を重視しています。事業承継や将来のビジョンについて、パワーポイントを用いてプレゼンを行い、従業員から意見を聞く機会を多く持っています。このような対話を通じて、自分の方向性を確認する時間を確保しています。
様々な形で常に振り返り、軌道修正を行うことが重要だと考えています。

社長が大切にされている言葉を教えてください。

いくつかありますが、3つ挙げます。
1つ目は、アルコール依存症の自助グループで毎日読まれる詩です。ラインホルト・ニーバーという牧師が書いたもので、「神よ、変えられないものを受け入れる落ち着きを、変えられるものを変える勇気を、そしてその違いを見分ける賢さをお与えください」という内容です。私はこの詩を3年間、毎日読み続けました。この言葉は今でも私の指針となっています。
2つ目は、二宮尊徳の「経済なき道徳は寝言であり、道徳なき経済は犯罪である」という言葉です。私は30代の頃、社会活動家として経済を度外視して活動していました。しかし、その限界に気付き、経済の重要性を学ぶようになりました。その一方で、経済ばかりを重視すると、今度はモラルハザードが生じることも経験しました。このバランスを取ることが、経営において非常に重要だと考えています。
3つ目は、「不易流行」という言葉です。変わらないものを大切にしながらも、変わるべきものは変えていく。このバランスが重要です。変化ばかりを重視すれば本質を見失い、変わらないことに固執すれば時代に適応できなくなる。何を守り、何を変えるべきかを常に見極めることが大切だと考えています。
企業が変化すべきかどうか、この点は常に問われ続ける問題です。何が絶対的な正解で、何が間違いかという明確な答えは存在しません。当社の名前『土屋』についても、「ダサい」「この名前では応募が少ない」「若い人が来ない」といった意見があります。それも一理あると思います。もしかしたらその意見の方が正しいかもしれませんし、今のままが正しいかもしれません。時代によって正解は変わるものです。今はこのやり方が正しくても、将来的には違う答えが出ることもあるでしょう。そう考えると、企業にとって変化は重要なポイントだと思います。
この3つの価値観は、私が大切にしているものです。

バランスと揺らぎというのが、重要なキーワードだと感じました。

実は、会社の創業記念イベントで毎年プレゼンをするのですが、その中で『動的平衡』という概念を紹介したことがあります。これは生物学者の福岡伸一さんが提唱した言葉で、著書『生物と無生物のあいだ』で語られています。
一言で言うと、「生命とは動きである」という考え方です。我々は生命を固定的に捉えがちですが、実際には生物は常に分子レベルで運動しています。それが完全にバランスが取れた瞬間、それは生命ではなく無生物になってしまう。生物は常に動き続けることで生命を維持するのです。
この考え方は、ビジネスにも通じるものがあると思います。企業も常に変化し続けることで存続し、成長できるのではないでしょうか。
止まった瞬間に無機質になってしまう。見た目には静止しているようでも、実は内部では動いている。これが、生きている限りの本質なのかもしれません。

その考えを社員の方々と共有されているのが、他の会社にはない面白さだと思います。

難しいことを言っていると思われるかもしれません。自己満足かもしれませんし、証拠はありませんしね。ただ、どんな企業も創業者の思いから始まったものです。そして、企業は変化を前面に押し出すことで、たとえば松下やホンダのような大きな存在になっていくのだと思います。
そして同時に、私はそういった大きなものとは少しずれた視点を持ちたいとも思っています。企業としてのアイデンティティを守りつつ、常に少しのズレを保ちたいという感覚があります。

社会に在り続けるための事業承継

今後の会社のビジョンについて、事業承継を予定されているとお聞きしました。それはなぜでしょうか。また、その間にどのようなことを成し遂げたいとお考えですか。

計画としては、5年後には経営の前線から退き、グループ企業全体の統括に移行したいと考えています。その後、10年後にはグループ企業の統括も別の人に委ね、私は相談役程度の立場になる予定です。
なぜそうしたいのかというと、私にはこの企業とその価値を守るというミッションがあるからです。ある種、この会社・事業は生命維持装置のようなもので、一部の人にとっては不可欠な存在です。この企業を永続させるために何が課題となるのか、企業が消えてしまう要因は何かを学んできました。書籍を読み、さまざまな経営者と出会い、事業承継のコンサルタントも入れて検討を重ねました。その中で明確になった課題の一つが、創業者の属人性です。
創業者には強い求心力があり、それは事業を成し遂げるためには必要ですが、あまりにも権限が集中しすぎると、創業者が不在になった際に企業の中枢が空洞化し、存続が危うくなります。創業者が突然病気で倒れたり、認知症になったりした場合、会社が機能不全に陥る可能性があります。
現時点で、私が突然亡くなったとき、この会社が確実に存続すると言い切れない不安があります。そのため、私の役割は、自分がいなくなった後でも企業が維持される仕組みを作ることです。一気に経営から退くのではなく、徐々に権限を移譲し、自然な形で引いていくのが最も安全だと考えています。現在52歳ですが、今後10〜15年をかけてこの計画を実行するつもりです。

事業承継について、事業を承継した側が語ることは多くても、バトンを渡す側が語ることはほとんどありません。実際に経営者に引退後の計画を尋ねると、多くが「特に考えていない」と答えます。まるで自分が不死身であるかのように考えているように感じることもあります。

創業者が事業承継について真剣に考えにくい背景には、事業の動機が関係しているのかもしれません。創業者は自分の理想を実現するために経営していることが多く、事業承継が重要なテーマにはなりにくい。一方で、社会的責任や共同体の運命に対する責任を考えると、事業承継は避けて通れない課題になります。
先日、インタビューを受けた際に「承継後、どのように幸せな人生を送るのですか」と聞かれましたが、正直に言うと、それにはあまり関心がありません。経営を続けていた方が発言力もあり、充実感があるかもしれません。しかし、事業承継とは自己を超えることでもあります。座禅や祈りのように、経営者が本気で向き合うべき課題でしょう。
また、私は事業承継の方法としてM&Aも一つの選択肢だと考えています。現在は世代間継承を優先していますが、M&Aによって同じ価値を維持できるのであれば、それも有効な手段です。資産の継承ではなく、価値の継承が目的であるため、手段は柔軟に考えるべきだと思います。ただ総合的に考えると、当社にとってはM&AやIPOよりも、世代間継承が最適だと判断しています。

現在、次の経営者として考えている方はいますか。

すでにストーリーはできています。エンディングノートを作成し、弁護士とともに会社の将来の人員体制を記しています。これは定期的に更新しており、必要に応じて修正しながら、私が不在になっても会社が安定して存続できるよう準備を進めています。

なるほど。話が戻りますが、大学を卒業するときには、今のような社会活動をすることを決めておられましたか。それとも、解決したい問題を見つけた結果、自然と活動家になったのでしょうか。

社会活動家になったのは後からのことです。大学で哲学を学び、「これをやるぞ」と思ったのがケアの仕事でした。珍しい選択だったと思います。社会活動家には高学歴の人もいますが、東大、早稲田、慶應などの卒業生でケアワーカーになった人には、私の知る限りあまり出会いません。
私は現場一筋でやってきましたが、同じ大学を出た同僚に会ったことがありません。

その強い原動力は何だったのでしょうか。

哲学や文学の影響が大きいですね。特に、大学卒業後に読んだ『聞くことの力』(鷲田清一著)がきっかけでした。鷲田先生はフランスの現象学、特にメルロ=ポンティの研究者で、その本を読んだことが大きな転機となりました。「大学を出て何をするか」と考えたときに、「ケアをやろう」と思ったんです。

現実的な問題として、生活や収入については考えませんでしたか。

もちろん、道徳と経済のバランスは考えました。ただ、私は「最低賃金で十分」と思っていました。経済的な豊かさを求める気持ちはなく、「食べていければいい」という考えでした。最初の給料は15万円ほどでしたが、それで十分でした。
正直に言うと、今は当時の10倍以上の収入がありますが、幸福度はほとんど変わりません。15万円の頃も、今も、幸せの感じ方は大きく変わらないですね。特に名誉や地位を求めたこともありません。それらは自然とついてきましたが、欲しいと思ったことはなかったです。手に入れたというより、流れの中でそうなったという感覚ですね。

食事などの嗜好に変化はありましたか。

全くないですね。昨日近くの料亭ですき焼きを食べましたが、普段食べる唐揚げ定食の方が好きです。高級な食事に特別な感動はありません。
車もそうです。現在はエルグランドに乗っていますが、以前はN-BOXでした。乗り換えたのも、従業員から「安全のためにもう少し大きな車にしたほうがいい」と言われたからです。自分から高級車に乗りたいと思ったことは一度もありません。

幼少期はどのような環境で育ちましたか。

4畳半一間で家族4人暮らし、風呂なしで銭湯通い。典型的な貧困層でした。友人の中には反社会的勢力の一員になった人もいました。当時は「どうすればお金持ちになれるのか」と考えていましたが、哲学や文学にのめり込むうちに価値観が変わり、消費に喜びを見出さなくなりました。
消費が幸福につながるのではなく、むしろ、不幸のきっかけになりかねない。今でも、娘と100円ショップでおもちゃを選ぶ際、「3つにするか5つにするか」くらいの小さなやりとりを大切にしています。

新しい時代を作る経営者ファンド

経営者の中には、財産を失ったときに命を絶つほどに失望する人もいますね。

私は仮に自己破産しても「ゼロになって終わり」と思えるので、問題ではないと考えています。きっと多くの人は、今の生活と理想の生活のギャップに耐えられないのだと思います。だからこそ、初めから低い生活レベルに慣れておくのも一つの考え方かもしれません。
世界的な大経営者の中には、私のような価値観を持つ人も意外と多いです。ウォーレン・バフェットさんもその一例でしょう。ただ、中小企業の経営者の多くは、欲を持つことが多いですね。欲に目がくらんで失敗し、そこから学んで成長する人も多いと思います。

確かに「経営者」とひとくくりにしても、色々な考え・価値観があります。どういった方と出会うことが多いですか。

私自身、以前は経営者に対してあまり良いイメージを持っていませんでした。しかし、経営者向けの勉強会に参加するようになり、考えが変わりました。当社ではすでにカンパニー制を導入していますが、さらにホールディングス化を進めようと考えています。そのために研究会に参加したのですが、まず規模の大きさに驚きました。当社のグループ全体の年商は約80億円ですが、同規模の企業が多く集まっていました。また、初代でホールディングス化するのは珍しく、通常は2代目や3代目が行うことが多いようです。
そこに集まった、中堅企業の経営者たちは皆、真面目で地味な印象を受けました。公務員のような実直なタイプが多く、以前持っていた「成金」のような経営者のイメージとは異なっていました。そのギャップは、私にとって良い意味での驚きでした。

参加されている経営者の集まりや取り組みについて、お聞かせください。

私も今度参画するのですが、上場企業の経営者たちがNPOに寄付するためのプラットフォーム「ソイルアンドポリシーファンド」が設立されました。このファンドでは、上場企業の経営者が自身の資産の一部を寄付し、それをファンド化して投資ではなく寄付として活用する仕組みです。
先日、そのファンドのイベントに参加したのですが、そこには「ニューリッチ」と呼ばれるIT企業の若手上場経営者が多くいました。彼らは20代後半から30代で、すでに上場を果たし、個人資産の総額が10人で約2000億円、つまり一人当たり200億円を持っているという規模でした。彼らは私が普段参加している研究会の経営者とは全く異なり、華やかでキラキラした雰囲気を持っていました。
そんな彼らがプレゼンの中で語っていたのは、前澤友作さんのように「お金を使ってできることはすべてやり尽くした」ということでした。そんな「餓え」から、新たな挑戦としてこのファンドに参加することを決めたそうです。一般の人からすると贅沢な悩みに思えるかもしれませんが、急成長する企業の経営者にとっては、それほどの短期間で次のステージを模索するものなのかもしれません。
彼らが抱える虚しさは、私が大学時代に哲学を学ぶ中で考えていたことと通じる部分があると感じました。彼らは「すべてをやり尽くし」、私は「まだやったことがない」だけで、根本的な悩みの構造は似ているのかもしれません。

先ほどおっしゃったファンドは、これから設立されるものですか。

いいえ、すでに設立されており、2・3回の活動実績があります。次回は、大手クラウドファンディング会社の創業者や私、その他のIT企業の経営者数名で運営する予定です。以前は「Chatwork」を創業した社長や他のIT企業の経営者が関わっていました。毎年新しいファンドを立ち上げ、NPOに公募を募る形を取っています。現在は、若者支援に取り組むNPOと連携しています。彼らが寄付を受ける側で、私たちは寄付をする側という関係が成り立っています。

このファンドでは、重度障害者や高齢者向けの支援事業も対象になるのでしょうか。

現時点では、手を挙げるNPOの多くが社会的にマネタイズが難しい事業を行っている法人です。一方で、高齢者支援事業は既に制度が確立されており、ビジネスとして成立しているため、ファンドの支援対象にはなりにくいのが現状です。
現在の支援の多くは若者支援や新しいテーマに焦点を当てています。東洋の貧困層の支援や、若者が反社会的勢力や半グレ組織に巻き込まれないようにするためのサポートが行われています。

社会的に影響力のある経営者が新しい事業に投資できるのは素晴らしいことですね。

私自身、若い頃はマネタイズができない事業も行っていました。今は、経済とモラルのバランスを取りながら事業を運営していますが、かつてはホームレス支援や難民支援をすべてボランティアで行っていました。利益が生まれない事業でも、価値がないわけではないと実感しています。
このファンドを設立した経営者の中には、NPOでの活動経験がある人はほとんどいないと思います。私はかつて支援を受ける側として活動していた経験があるので、寄付をする側に回った今、その意味を深く理解しているつもりです。今回の参加は一度限りのつもりですが、この経験を通じてどのような影響が生まれるかを見てみたいと考えています。

NPOは数多くありますが、本当に志を持って価値ある活動をしている団体もあれば、残念ながらそうではない団体もあると考えます。その見極めはどのように行われていますか。

このプラットフォームには、NPOの活動を評価する専門家が関わっており、寄付に値するかどうかを審査しています。また、寄付する側も自分の関心に基づいて選択できます。ただ単に「困っているから寄付してほしい」という形ではなく、より価値のある活動に寄付が行われる仕組みになっています。その点が、このプラットフォームの優れた点だと思います。

社会課題を解決するためのM&A

ここからは、御社のM&Aについて触れていきます。同じ事業でも、事業者ごとに志や理念が異なります。たとえば、高齢者福祉を「儲かるから」といった理由で行っている事業者もあるかと思います。そういった場合、どのように線引きをされていますか。

まず、「儲かるからやる」という考え方自体が悪いとは思いません。ただし、利益を追求するあまり持続できない事業が出てくることもあります。そうした事業を私たちが引き継ぐことで、単なる利益追求ではなく「価値を生む事業」として再生できる可能性があると考えています。そのため、事業を始めた動機よりも、どのように運営されているかを重視しています。
基準としては、まず事業シナジーがあるかどうかを考えます。多くの事業は地域密着型の中小企業ですので、その地域で必要とされている事業かどうかを判断します。次に、経営人材の育成という観点です。当社ではホールディングス化の中で経営人材を育成することに力を入れており、その一環として「社長を経験する」という機会を提供しています。そのため、特定の地域で経営を学びたい人材がいるかどうかも重要な要素です。
ある地域から事業の引き継ぎ依頼があった場合、その地域に適任の経営者候補がいるかを考えます。経験を積ませることで成長できる人材がいる場合、その事業を引き継ぐ選択肢が生まれます。最後に財務状況も慎重に確認します。過去数年間の財務諸表(BS・PL)を分析し、当社全体に大きなマイナス影響を及ぼさないかどうかを見極めます。これらの条件をクリアした場合、事業の引き継ぎを決定するという流れです。

これからも相性の良い事業があれば、一緒に取り組んでいく方針でしょうか。

はい。現在、2030年までにグループ企業20社体制を目指しています。昨日、鳥取県米子市最大手の介護事業者が当社グループに加わりました。これでグループ企業は10社になり、20社という目標もほぼ達成できる見込みです。
20社あるということは、20人が社長を経験できる機会があるということです。これが30社になれば30人、50社になれば50人と、より多くの人に経営経験を提供できます。こうした取り組みは「インキュベーションホールディングス」と呼ばれ、私たちの事業の重要な軸の一つになっています。

私の生まれは鳥取県の米子市なんです。

そうなのですね。米子市は過疎化が進んでいますよね。訪問介護も人手不足が深刻な地域です。

おっしゃる通りです。祖父母も介護を受けていますが、自宅だけでは対応が難しく、さまざまな施設のお世話になっています。人手不足を実感します。

今回、弊社が米子市の事業を引き継いだ背景にも、そのような事情があります。事業がなくなると、多くの利用者が困ることになりますので、当社が受け皿となることを決めました。M&Aと聞くと、いわゆる「ハゲタカファンド」のようなイメージを持たれることもありますが、私たちのM&Aはそれとは異なります。むしろ、経営体力のある介護事業者こそ、地域のためにこのような役割を果たすべきだと考えています。
介護サービスがなくなれば、地域住民は困り果てます。そのような社会課題や利用者の視点を重視することが、当社のM&Aの根幹にあります。

御社のM&Aが単なる買収ではなく、社会的な事業としての意味を持つことがよくわかりました。

こうしたメディアの取材は、私たちの意図を正しく伝える良い機会になります。どうしても表面的な情報だけで判断されることが多いですが、それが誤解を生んでしまうこともあります。私たちのM&Aが社会的意義を持つものであることを伝えることができれば、誤解や偏見を払拭する手助けになるかもしれません。
また、社内ではこうした話をじっくりする機会が少ないですが、M&Aに対して不安を持っている社員がいても、記事を通して実はこういう背景があると知れば、見方が変わるかもしれません。
世間的には、M&Aを頻繁に行っていると「イケイケ企業」のように見られがちですが、実際は行政からの依頼を受けて事業を引き継ぐケースも多く、単なる企業買収とは異なります。こうした点を理解してもらえれば、社員にとっても誇りを持てる取り組みになると思います。
会社の未来を、社会の未来へと拓く

今後のビジョンについてもお聞かせください。

直近の取り組みとして、2025年4月に公益財団法人を立ち上げ、奨学金や文化振興事業を開始する予定です。医学を学びたいが経済的に困難な学生や、ヤングケアラーとして学業に専念できない若者に奨学金を提供するなど、社会貢献に資する取り組みを行っていきます。
また、2025年6月には在宅医療クリニックを開設する予定です。医療法人が介護事業を併設するケースは多いですが、介護事業者が医療サービスを提供するのは珍しい。私たちは在宅福祉の分野で培ったノウハウを生かし、在宅医療との連携を強化することで、地域医療と福祉の発展に貢献したいと考えています。
中期的には、重度訪問介護が中心だった障害福祉事業において、グループホームの運営にも力を入れていきます。これまで最重度の方を中心に支援してきましたが、今後は中軽度の方々の支援にも取り組みます。また、高齢者福祉とのバランスを取りながら、必要とされるサービスを提供していきたいと考えています。
これらの取り組みが順調に進めば、2030年には年商200億円規模の企業になる見込みです。その頃には、私自身の引退を見据え、次世代へのバトンタッチを考えています。

現在、障害福祉分野の業界団体を立ち上げ、組成中とのことですが、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。

業界団体として、政治や行政へのロビー活動を行い、現場の声を届ける取り組みを進めています。これは、会社のフロント業務から引退するタイミングと合わせて、将来的には誰かに引き継ぎたいと考えています。ただ、まずは初期の仕組みを整え、次世代につなげていくことが私の役割です。事業の脱属人化を進め、私の手を離れても円滑に運営できる形を作ることが重要だと考えています。
また、経営そのものだけでなく、外部向けの発信の役割も次第に別の人に任せる必要があると考えています。そうなると、自分が徐々に表舞台から退いていくことになります。それが本当に幸せなのかはまだ分かりません。ただ、これをしっかりとやり遂げることが、私の最大のビジョンです。

そういった取り組みが進むことで、日本社会はどのように変わっていくと思いますか。

「脱施設・脱病院・在宅重視」という方向性は、経済と道徳のバランスが取れていると考えています。サービスを利用する方々に聞くと、病院や施設よりも自宅で暮らしたいという声が圧倒的に多いです。その願いが叶うことが一つの大きなポイントです。
もう一つは、社会保障費や医療費の増大という課題への対応です。病院や施設といった「箱もの」に依存せず、在宅での支援を拡充することで、社会保障費の抑制につながる可能性があります。利用者にとっても、社会全体にとってもプラスになる方向だと思います。その中で、私たちが担う役割は小さいかもしれませんが、少しでも社会に貢献できればと考えています。
私自身、長年福祉の分野に携わってきましたが、福祉や医療も経済と切り離せない関係にあります。結局、福祉や医療の財源は税金であり、その税金の大部分は所得税・消費税・法人税から成り立っています。つまり、国民経済がうまく回らなければ、福祉も医療も持続できません。
少子化や高齢化の問題もあり、税収の確保は喫緊の課題です。しかし、私たちの立場では、税収そのものを増やすことはできません。もちろん、法人税や所得税は適正に納めていますが、それは企業として当然のことです。それよりも、経済が活性化し、持続可能な社会システムが構築されることが重要だと考えています。

日本全体が持続可能な形で発展するためには、何がポイントになるとお考えですか。

元気に働ける人を増やすことが重要だと思います。私は個人的に、税金が高くても医療・福祉・教育が充実している社会の方が、幸福度が高いと考えています。私は単なるサービスプロバイダーではなく、一市民としてもそのような社会を望んでいます。
今、103万円の壁の問題が話題になっていますが、これは増税の議論ではなく、実際には減税の話です。上限を引き上げることで本来入ってくるはずの税収が減少する側面もありますが、それによって労働参加が促進されるという意図があります。

資産課税や相続税についても、いろいろな議論がありますが、考えを聞かせていただけますか。

資産課税や相続税を逃れるため、富裕層がさまざまな方法を駆使して節税している現状があります。多くの資産家が節税の対策を取ることで、本来国に入るはずの税収が逃げているわけです。
税収の機会損失は年間400億円に上ると言われています。重度訪問介護の事業全体の年間予算が1000億円だとすれば、その約半分が資産家の節税対策によって失われている計算になります。こうした状況を放置せず、きちんとした税の徴収が行われるべきだと思います。
私は現在、テレビドラマ『プライベートバンカー』を楽しみに観ていますが、そこでも「100億円持っている人が50億円になったら困るのか?」「1000億円持っている人が500億円になって何が困るのか?」という疑問が描かれています。私自身、個人的には「困ることはない」と思っています。私はワンコインの牛丼で十分満足できるタイプですから(笑)。
ただ、資産家の中には、少しでも税金を減らそうと必死になっている人も多い。会社を存続させるため適切な対策は必要ですが、行き過ぎた節税策を行えば国の体力は衰え、為そうとしている社会貢献に対して本末転倒なことになりかねません。
少子高齢化が問題視されていますが、極端な話、富裕層が「10分の1」ではなく「10分の2」の税負担をするだけで、多くの問題が解決するかもしれません。社会保障の課題において、結局、問題は資産家たちの意識の向け方です。自分の利益だけでなく、社会全体の視点を持つことが求められます。私は政治家になるつもりはまったくありませんが、政治の影響力が大きいことは理解しています。社会をより良くするためには、富裕層のモラルと、制度設計の両方が重要だと感じます。

ぜひ、そうした意識が広がり、社会のモラルが向上する仕組みができると良いですね。

本当にそうですね。モラルや意識が変われば、社会も変わる可能性があります。お金の問題についても同様で、私たち自身が明るい未来を描きながら、自分の心を磨くことが大切だと思いました。
特にリーダーの影響は大きいです。企業にはリーダーがいるように、国や国際社会にもリーダーが存在します。リーダーが少しでも変われば、それに伴って多くの人が変わる。世界のリーダー10人が変わるだけで、15億人が変わるのと同じくらいのインパクトを生み出せるかもしれません。
私自身がそのような大きなことを成し遂げられるわけではありませんから、これは独り言のようなものです。しかし、こうしてメディアを通じて発信することで、誰かの意識が少しでも変わるきっかけになれば、何かしらの変化が生まれるかもしれません。そうした希望は持ち続けたいと思います。

今日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。御社の事業を飛び越えて、国の、そして人々の生活に思いを馳せるインタビューとなり、会社の志がどこにあるのか深く響きました。これから続く御社の道行きを応援しております。
コントリ編集部からひとこと

今回、高浜社長とお会いしたのは障害者を雇用されているお気に入りのカフェでした。店内はレトロで温かな感じで、スタッフの方々の笑顔と丁寧な接客が印象的でした。インタビュー後にいただいたオムライスの優しい味わいも、この場所の雰囲気と見事に調和していました。
取材を通じて感じたのは、経済と道徳のバランスを重視する経営哲学の真摯さです。社名の由来から事業承継の展望まで、その言葉の端々に「利益」と「価値」の両立を目指す強い意志が込められていました。特に印象的だったのは、全国47都道府県でケアを提供する使命感と、次世代に向けた具体的な展望です。
高浜社長の「動的平衡」という言葉が象徴するように、変化と不変のバランスを取りながら、社会課題の解決に取り組む姿勢は、これからの企業経営のモデルになるのではないでしょうか。
コントリ株式会社
代表取締役
飯塚 昭博
ギャラリー










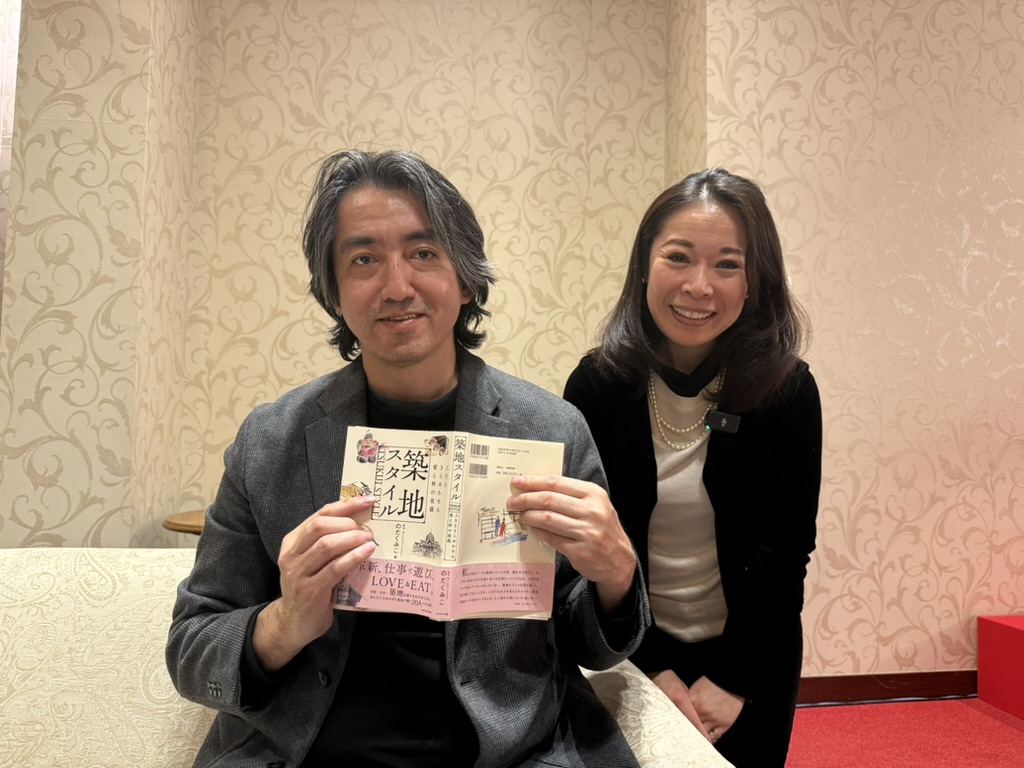


プロフィール
株式会社土屋
代表取締役
高浜 敏之
慶應義塾大学文学部哲学科(美学美術史学専攻)を卒業後、介護福祉の世界に身を投じる。自立障害者の介助者として活動を開始し、障害者運動やホームレス支援活動に携わりながら、現場での経験を積む。その後、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参画し、デイサービスの管理者や事業統括、新規事業の企画立案など、幅広い実務を経験。
2020年8月、株式会社土屋を設立し、代表取締役CEOに就任。「探し求める 小さな声を ありったけの誇らしさと共に」を企業ミッションに掲げ、介護難民問題の解決に取り組む。病院や施設ではなく、地域での共生社会の実現を目指し、全国47都道府県での介護サービス提供を実現。障害や難病を抱える人々が地域で自分らしく生きられる社会づくりに尽力している。
会社概要
| 設立 | 2020年8月19日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 所在地 | 岡山県井原市井原町192-2 久安セントラルビル2F |
| 従業員数 | 2646名(2024年3月末現在) |
| 事業内容 | 障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業、 介護保険法に基づく居宅サービス事業 訪問看護事業 研修事業 シンクタンク 出版事業 |
| HP | https://tcy.co.jp/ |
・自分らしく生き抜くことを見つめて。超高齢化社会に真に必要なサービスとは|株式会社Red Bear
・演劇メソッドを通して知る、「自分の本質」と「心を繋ぐ感動」|美鶴ヒューマンラボ株式会社
・心と体にアプローチする、ボディケアから目指す、人が輝くための時間|株式会社K-Dream1
御社の想いも、
このように語りませんか?
経営に対する熱い想いがある
この事業で成し遂げたいことがある
自分の経営哲学を言葉にしたい
そんな経営者の方を、コントリは探しています。
インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。
条件は「熱い想い」があることだけです。
経営者インタビューに応募する
御社の「想い」を聞かせてください。
- インタビュー・記事制作・公開すべて無料
- 3営業日以内に審査結果をご連絡
- 売上規模・業種・知名度は不問
※無理な営業は一切いたしません
発信を自社で続けられる
仕組みを作りたい方へ
発信を「外注」から「内製化」へ