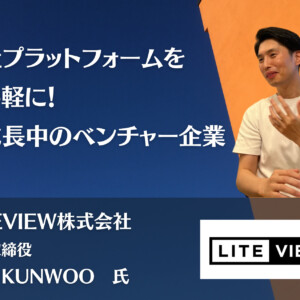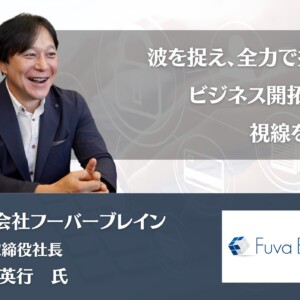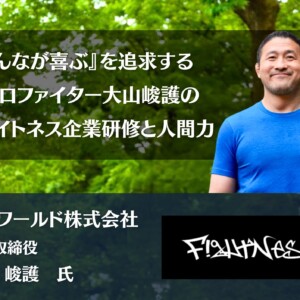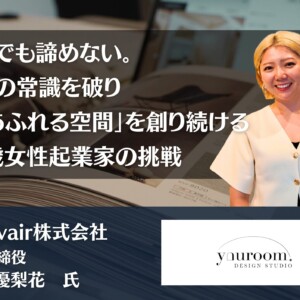「誰と世界を変えるか」を重視する経営者が挑む、ゴミゼロ社会への革命|株式会社Ripples
「これ見たときに、あれ何でこれ流行ってないんだろうって思ったんですよ」——。
株式会社Ripples代表取締役の荒裕太氏は、初めて「剥がせる容器」と出会った瞬間を振り返ります。30年前に開発されながら世に出ることのなかった技術に可能性を見出し、環境・福祉・教育・防災という4つの社会課題を同時解決するビジネスモデルを構築。人事一筋20年のキャリアを活かし、「何をするかより誰と世界を変えるか」を重視する経営哲学で、ゴミゼロ社会の実現に挑んでいます。
人事一筋20年から一転、「剥がせる容器」に賭けた理由
44歳の荒氏は、生まれも育ちも東京。現在は4人の子どもを持つ父親として、渋谷区で家族と暮らしています。「上から高校生、中学生、小学生、幼稚園と、今全カテゴリーいるんですよ」と笑顔で話す荒氏の表情からは、家族を大切にする温かい人柄が伝わってきます。
荒氏のキャリアは、新卒から人事職一筋でした。最初は労務ポジションからスタートし、給与計算や社会保険業務を担当。しかし、「とにかく面白くないというか、答えが決まってる仕事って僕あんまり好きじゃない」と感じ、キャリアチェンジを決意します。
その後、オランダの監査法人、アメリカの保険会社、食品会社と外資系企業を渡り歩き、人事の専門性を高めていきました。「アメリカの保険会社では部門付人事として、数千人規模の組織を担当していました。一つの会社みたいな規模でしたね」と振り返ります。
転機となったのは、IT企業での勤務経験でした。「エンジニアという人たちに初めて人生で触れて、考え方が全然違うんだなと思いました」。合理的な働き方や、30分以上の会議は行わない効率性に感銘を受けた荒氏。しかし、その後ITスタートアップ企業を経て、転職した新素材系のスタートアップ企業で大きな挫折を経験します。
「めちゃめちゃ体質が古くて、昭和みたいな会社でした。リモートワークなんてコロナだろうが何だろうが絶対認めないみたいな」。働きやすい環境を作るために入社したにも関わらず、提案はことごとく却下される日々。この経験が、荒氏に独立への決意を固めさせました。
「私は自分で会社を作れば自分でルールを作れるじゃんって思って。そのときには何をやるかって何も決めてないで、とりあえず会社だけ作ったんです」

30年前の技術が日の目を見なかった理由と、Ripplesの戦略
渋谷区の創業支援セミナーを受けながら事業を模索していた荒氏が、運命的に出会ったのが「剥がせる容器」でした。容器に貼られたフィルムを剥がすことで、使い捨て容器が洗って再利用できるようになる革新的な技術です。
この技術は30年前、阪神淡路大震災でお皿の上にラップをかけて食べている人々を見て着想を得て開発されました。しかし、なぜ30年間も世に出なかったのでしょうか。
「メーカーであるヨコタ東北は技術開発に集中されており、営業面では受け身のスタイルでした」と荒氏は説明します。優れた技術を持つメーカーとして、品質向上と製品開発に注力してきた結果、市場開拓の部分で課題があったのです。
荒氏が革新的だったのは、単に営業代行をするのではなく、明確な基準を設けたことでした。「回収率6割以上は担保するというのを一つ基準にしました。パリ協定で日本は2030年までにCO2を46%削減すると宣言していますが、6割回収できるとCO2を46%削減できるというエビデンスがあったんです」
この6割回収という明確な目標設定により、環境効果を数値化。メーカーとの包括提携を実現し、お互いに株を交換する強固なパートナーシップを構築しました。
技術の価値を世に知らしめた転機は、東京オリンピックでした。新潟中越地震での寄付実績が評価され、新潟大学での採用を皮切りに東京大学、そして全国の国立大学へと拡がりました。小池都知事が「世界で唯一ゴミにならない容器」として採用を決定。オリンピック期間中、ボランティアスタッフ数万人の弁当容器として使用され、回収率100%を達成しました。

はがせるトレーP&Pリ・リパック
一石四鳥のビジネスモデル「環境×福祉×教育×防災」
荒氏が構築したビジネスモデルの真価は、4つの社会課題を同時解決する点にあります。
環境面では、剥がせる容器により劇的なゴミ削減を実現します。「ラーメンのイベントとかで10万食とか使ってもらって、8割以上が回収できるんですよ。ゴミが出ないんです」。しかも、回収した容器は「水平リサイクル」により再び容器として生まれ変わります。油汚れがないため、容器から容器への再生が可能なのです。
福祉面では、障害者雇用の創出に貢献しています。「この赤いフィルムの部分は全部障害者の方々が手で貼っていただいてるんです」。B型雇用と呼ばれる精神障害者の方々が、集中力の高さを活かして1日3000枚の貼り付け作業を行います。「1枚当たりの工賃をお支払いしているので、作業量に応じて収入向上に直結するんです」。従来の月収水準を大幅に上回る収入機会を提供しています。
教育面では、全国の子ども食堂への寄付モデルを展開中です。「子ども食堂50ヶ所ぐらいにこれを今寄付するモデルを作ってます」。むすびえという子ども食堂を全国展開している組織と連携し、まずは規模の大きな50ヶ所からスタート。将来的には全国1万7000ヶ所への展開を構想しています。
防災面では、災害時の衛生環境改善に貢献します。「災害の時は水が出なかったりするんですよね。洗わなくていいので食べて剥がして、最悪2回使ってもいいわけですよ」。各自治体に防災備蓄用品としての採用を働きかけており、子ども食堂を備蓄拠点とする構想も進めています。

IVS2025 in KYOTOので登壇風景
179大学が採用、学生認知度の高さが生む事業拡大
現在、179の大学でこの容器が採用されています。「国公立とか慶応とかそういったとこ入れてですね、179で使ってもらって、プラス学園祭とか入れるともう数百校」と荒氏は説明します。
学生の認知度の高さは、予想外のビジネス拡大をもたらしました。「先月京都のイベントに行ったとき、学生の方が『これうちの大学で使ってますよ』ってすぐに声をかけてくれました」。学生が大手テーマパークに就職後、この容器を提案。テーマパークでの採用につながりました。
テーマパークでは、人気キャラクターなど5パターンの特別なデザインを刻印した特別仕様を制作。「〇〇周年と書いてある、すごくかわいいフィルム」を作成しました。しかし予想外の展開が待っていました。
「みんな持って帰っちゃうんすよ。回収できなくて」と苦笑いする荒氏。「綺麗な状態のキャラクターのお皿がもうすぐ出来上がるので、記念に持って帰ろうって家で使っているという」。回収率は6割程度でしたが、ゴミが出なければよいというテーマパーク側の判断で、現在も使用されています。
万博での導入では、興味深い「抜け道」戦略を展開しました。万博の規定では「リユースしか駄目」とされていましたが、道頓堀商店街が借りているエリアは万博の規則から外れていました。「商店街の会長さんが万博の出店者に対してこの容器を提案したら『全然こっちの方がいいじゃん』って」。リユース容器に比べて剥がせる容器は大幅に安価で、コスト面でも圧倒的な優位性を示しました。
PTA会長経験が生んだ意外なビジネスチャンス
荒氏の特徴的な経営スタイルの一つが、地域活動への積極的な参加です。現在、幼稚園と小学校のPTA会長、渋谷区PTA連合会副会長を務めています。「なんか断れないタイプというか、お願いされたら名誉なことだなと思ってまして」と照れながら話します。
この地域活動が、意外なビジネスチャンスを生みました。教育関連イベントで知り合ったIT企業役員との出会いが、同じ環境・SDGs分野で活動する企業との協業につながったのです。
その企業は、AIを活用したスマートゴミ箱を開発する企業。「ゴミを入れていくと自動で圧縮してくれて、容量5分の1まで減らしてくれる」革新的な製品です。同じ環境やSDGsを扱う企業として、お互いの事業拡大をサポートし合う関係を構築しました。
「お互いに環境問題に取り組む企業として、協力できる部分で一緒に活動しています」。持ちつ持たれつの関係性により、両社の事業拡大を実現。現在は、大学生協への営業でも協力関係を続けています。
「なんか議員さんになりませんかとかってすごい言われるんですけど、そこだけは絶対お断りしてもらう。それだけはやりたくない」と笑いながら話す荒氏。政治家ではなく、事業を通じた社会貢献を選択し続けています。

「何をするかより誰と世界を変えるか」の経営哲学
荒氏の経営哲学の核心は、「何をするかより誰と世界を変えるか」というメッセージに集約されています。この考え方の背景には、これまでの会社経験での気づきがありました。
「以前の会社では伝統的な組織文化が根強く、新しい提案がなかなか受け入れられない環境でした」。階層的な組織文化への違和感から、フラットな組織づくりへのこだわりが生まれました。
「僕はどんな偉くなったとしても、社員と机を並べて一緒の場所で働きたいなと思うんですよ」。権威主義を排し、同じ価値観を持つ仲間との協働を重視する姿勢。「社長というのも、多分役割でしかないと僕は思っているので」という言葉からは、謙虚でありながら芯の強い人柄が伝わってきます。
この哲学は、事業パートナーとの関係性にも反映されています。メーカーとの株式交換による強固な提携、同じ環境・SDGs分野の企業との相互協力、むすびえとの連携契約など、全て「誰と」という視点を重視した関係構築です。
2年以内の日本全国認知、そして世界展開への野望
荒氏の野望は壮大です。「日本中で、誰もが知っている状況に2年以内に持っていきたいです。その後は世界をターゲットに、水が貴重な国や飲める水がない国に持っていきたいと考えています」
具体的には、大手コンビニエンスストアとの協業プロジェクトが年内実現予定です。「特定の商品の容器を今後作っていく。そこからスタートして、他の商品の剥がせる容器も一緒に作っていこう」。回収した容器を原料として新しい容器を製造する完全循環型のモデルです。
海外展開では、水が貴重な砂漠地域やアフリカでの活用を構想しています。「砂漠など水が貴重な地域では、洗わなくても済むこの容器が役立ちます。そこで循環システムを構築できれば、とても有効だと思います」
さらに壮大なビジョンとして、ドイツ・ブンデスリーガでの活用を描いています。「数万人が入るようなスタジアムで、1試合あたりどれだけのゴミが出るか。それがなくなれば、環境への貢献度は非常に大きいと思います」。ドイツの強豪チームのロゴが入った容器での活用を夢見ています。
コントリからのメッセージ
人事一筋20年のキャリアから一転し、30年眠っていた技術に新たな価値を見出した荒裕太氏。環境・福祉・教育・防災という4つの社会課題を同時解決するビジネスモデルは、単なる営業代行を超えた社会変革への挑戦です。
特に印象的なのは、「何をするかより誰と世界を変えるか」を重視する経営哲学。PTA活動から生まれたビジネスチャンス、フラットな組織づくりへのこだわり、そしてパートナー企業との信頼関係構築。すべてが「誰と」という視点から生まれています。
中小企業の経営者にとって、荒氏の事例は多くの示唆を与えてくれます。既存技術への新しい視点、社会課題の統合的解決、地域活動の意外な効果、そして何より人とのつながりを大切にする姿勢。これらは業種を問わず応用できる普遍的な経営の知恵です。
2年以内の全国認知、そして世界展開という大きな目標に向かって歩み続ける荒氏。その真摯で温かい人柄と革新的な事業への情熱に、きっと多くの経営者が「一度お会いしてみたい」と感じるでしょう。ゴミゼロ社会の実現という壮大な挑戦は、まだ始まったばかりです。
ギャラリー

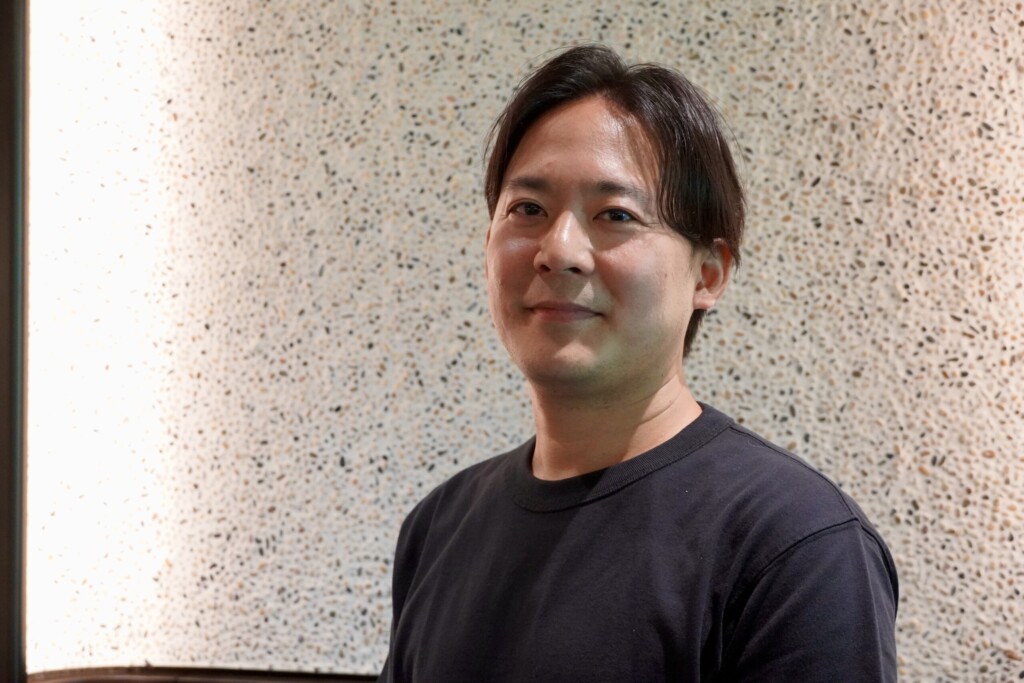

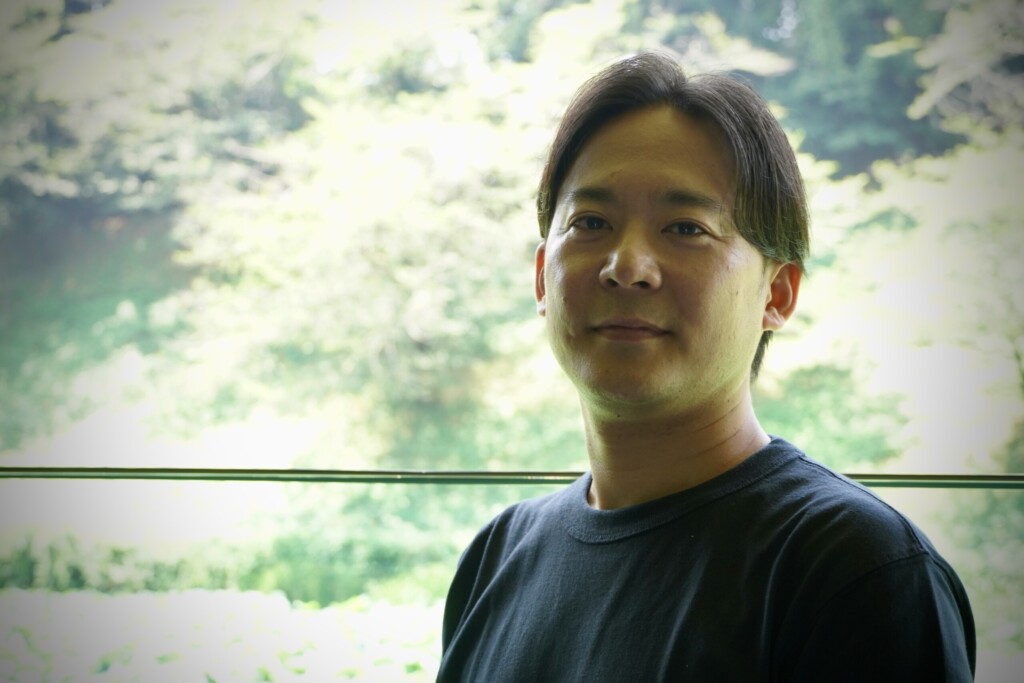




プロフィール
株式会社Ripples
代表取締役
荒 裕太
2023年7月、「誰と世界を変える取り組みができるか」という理念のもと同社を設立。水平リサイクル容器「P&Pリ・リパック」の普及事業を展開し、特殊フィルムを剥がすだけでリサイクル可能な画期的な容器により、重量比97%のゴミ削減を実現。大学の学食や学園祭、テーマパークなど様々な場所で導入が進む。社名「Ripples(波紋)」には、幸せや成功体験が広がり続けるという想いを込める。環境・福祉・防災・教育の観点から社会課題解決に取り組む。
会社概要
| 設立 | 2023年7月 |
| 資本金 | 100万円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-18-1-107 |
| 従業員数 | 3人 |
| 事業内容 | 水平リサイクル容器「P&Pリ・リパック」の企画・販売・回収システム構築 |
| HP | https://ripples-ekth.com/ |
関連記事
御社の想いも、
このように語りませんか?
経営に対する熱い想いがある
この事業で成し遂げたいことがある
自分の経営哲学を言葉にしたい
そんな経営者の方を、コントリは探しています。
インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。
条件は「熱い想い」があることだけです。
経営者インタビューに応募する
御社の「想い」を聞かせてください。
- インタビュー・記事制作・公開すべて無料
- 3営業日以内に審査結果をご連絡
- 売上規模・業種・知名度は不問
※無理な営業は一切いたしません
発信を自社で続けられる
仕組みを作りたい方へ
発信を「外注」から「内製化」へ