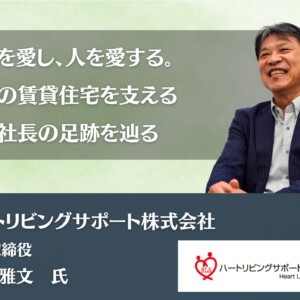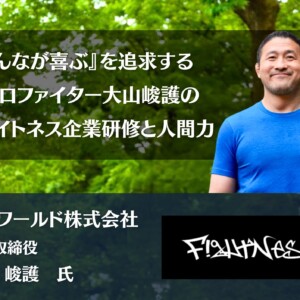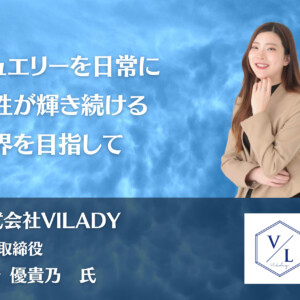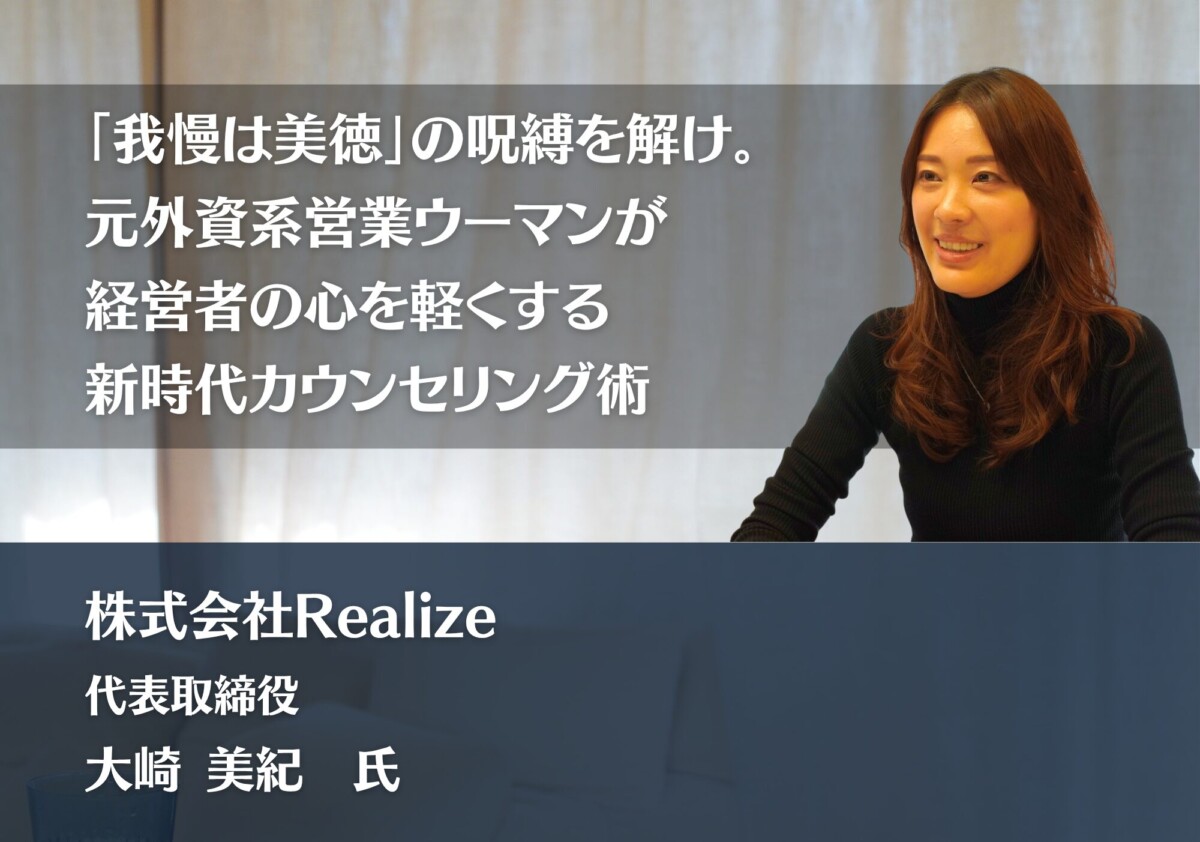
「我慢は美徳」の呪縛を解け。元外資系営業ウーマンが経営者の心を軽くする新時代カウンセリング術|株式会社Realize
「感情って、エネルギーなんです。その感情を止めるということは、外側の世界も連動して滞ってしまう。だから感情を解放して緩めてあげると、外側の世界も循環・拡大して力まなくてもパフォーマンスが上がっていく」——。
株式会社Realize代表取締役の大崎美紀氏は、穏やかな表情でこう語ります。心理カウンセリング、講座、アドバイザー業務、企画を手がける同社で、「経営者向けカウンセリング」という新分野を開拓している大崎氏。顧客の9割が経営者で、その8割が紹介によるという実績の背景には、ITベンチャー、大手米国企業で培った富裕層ビジネス営業経験と、産後うつ体験から得た心理学的洞察がありました。
この記事では、日本の経営者が抱える感情抑圧の問題と、それを解決する新しいアプローチについて、大崎氏のキャリア転身エピソードとともにお伝えします。
美食家や富裕層向け高級レストラン開拓の営業ウーマンが、なぜ心理カウンセラーに?
「大好きだったキャビアやトリュフが食べられなくなった時期がある」——大崎氏は苦笑いを浮かべながら、営業時代を振り返ります。
富裕層向けの飲食店サービス向上のため、予約困難店の新規開拓や席数確保の交渉を担当していました。毎日高級レストランでの食事が続き、時にはシャンパン4本を1人で飲む日もあったといいます。
「元々食べることが好きだったので、趣味と実益を兼ねたいい仕事でした。でも最後の方は毎日外食で、朝昼晩とフルコースが何年も続き、体調を崩しがちになり健康診断でひっかかる項目が増えたり結構しんどくなってきて」
転機は2023年、産後でした。金融ベンチャーでの復職を検討していたタイミングで、カウンセラーの資格を取得したことを知ったママ友や営業時代のお客様である経営者の方から相談の依頼を受けるようになります。
「妊娠中から産後にかけて、子育てと自分自身のために心理学の資格を取得していました。前職に復職するか迷っていたタイミングで、カウンセリングの依頼を受けるようになり、そのままカウンセラーとして活動することになりました」
しかし、その背景には深刻な体験がありました。
「営業時代は何か悩みがあっても、思考で軌道修正できていた。『こんなことでくよくよしちゃいけない』とか根性論的な価値観で軌道修正できていたんです。でも産後のカラダやココロは、今までのように言うことを聞いてくれない。ホルモンがこんなにも人の肉体や感情に影響を与えるのかと、今までの思考で何とかコントロールするというやり方が通用しなくなった」
大崎氏の表情が少し曇ります。
「産後数ヶ月して、可愛い我が子が目の前にいて幸せなはずなのに何故か涙があふれて止まらない。睡眠不足で疲れているはずなのに眠れない。今まで仕事をする上で感情や感覚は評価されず、働く上でこれらは不要だと誤認していて、いかにネガティブな感情を押し殺し、一喜一憂せず、淡々と数字や事実、結果で対話をするか。著名なビジネスリーダー、職場、ビジネス書からそのように学び、それが評価に繋がるので感情より論理的思考こそが正しく重要だと思ってました。そのため、マインドセット(思考術)はそこそこ得意だと思ってたけど、思考に振り切って感情や感覚を蔑ろにしすぎたが故に、真実の自分と向き合うことは全くできなくなっていた。押さえて蓋をしていただけだったので、その負担と綻びが産後うつとして肉体やメンタルの不調として姿を表してきたのだと思います」
この体験が、心理学を本格的に学ぶきっかけとなりました。
「息子に対して最適な状態で愛情を注ぎたい。最適な教育環境を提供したい。どんなに最適な関わり方や環境などの外側の状態を与えたとしても、ママの内側がうつの状態や暗い状態だと、必ずそれは子供に何かしらの心理的影響を与えてしまう。私がハッピーになることが、結果、息子にとってもハッピーなんだということがわかったんです」
産後、子供が3時間4時間まとめて寝てくれるようになった生後半年以降は集中して毎日1〜2時間コツコツと勉強出来るようになり、3〜4ヶ月で複数の心理学の資格を取得しました。
「基本息子は2時間ぐらいで目が覚めてたので、3〜4時間で眠ってくれるってなったら、自分の時間ができるようになってすごく嬉しくて。次起きるまでに今やっとかないと、次いつ起きるかわからないから今しかない、という感じで勉強しました」

「感情を殺して成功する」日本の経営者が抱える深刻な問題
「日本人は、忍耐や我慢が美徳とされていたり、同調や協調することが良しとされる文化が根付いており、自身の思いや感情を表現することに慣れていない」——大崎氏は、日本の経営者が抱える根深い問題を指摘します。
欧米諸国では経営者向けカウンセリングが一般的な中、日本での普及が遅れている理由について、大崎氏は分析します。
「島国であることや、農耕民族として歩んできた背景、武士の文化や、これら歴史的背景などが要因として考えられます。感情的になるのは未熟とか、余計なことは言わない方がスマートだとか、自己主張が強すぎては協調性が足りないとか、、、カウンセリングというと、相当心を病んだ人が通う場所とか、精神疾患とか発達障害とか、ちょっと重たく捉えられているのもあります。正確に言うと、感情は感じてもいいのですが、感情を他者にぶつけて攻撃的になったり傷つけたりするのは良くない」ということなんです。でもそれが誤った認識の中で子供から大人に育ってしまい、感情的=悪みたいな、こういった人たちを面倒な人と捉えて嫌厭してしまうが故に、自分はそうなってはならないと、感情を表現することだけでなく、感じることすら止めてしまいます。
興味深いのは、大崎氏が指摘する経営者の感情解放の実態です。
「経営者の皆さんが銀座のクラブなどに行くのはなぜか。仕事のお付き合いでとか仰ってますが、結論、楽しいとか癒されたとか解放感を感じているからなんです。日頃抱えてるストレスや常識やルール、肩書きを気にしないでどんな話でも否定せず聞いてもらえたり、心の拠り所になるからなんです。本来受け止めて欲しかった気持ちを、誰かに受け止めてもらいたい、理解してもらいたいと言う気持ちから人は癒しを求めるんです。お酒を飲んで人が変わる人っていうのは、大体は日頃から自分を抑え込んでいる人ですね。それだけ抑圧や我慢、自己犠牲している証拠なんです」
大崎氏は外資系企業での経験と対比します。
「外資系企業に移ってから、会議では積極的に発言することが求められていました。発言しない人の方が『やる気がない』と見なされてしまう文化で、もし発言したことで上司から報復を受けるようなことがあれば、会社がしっかりと社員を守ってくれる体制も整っており、ここでの環境は大きな気づきと成長があり今でも感謝しています。自己肯定感が低かった私は、「こんな私の意見や発言も受け止めてくれる環境があるんだ」と感動し、チームのメンバーに対する敬意が生まれました。」
一方で日本企業の現実は異なります。
「日本企業では、会議で意見を言うと『生意気だ』と思われたり、出過ぎる杭は打たれる風潮で、評価が下がったりするのではないかと心配して発言を控える人が多いなと感じました。協調性がネガティブな方向に向かうとそうなってしまう。私自身がまさにそうでした。でも本当は、社員が会社の発展になりそうな考えを自由に言える環境の方が、会社にとってもプラスになるはずなんです。そして、どちらにもメリットデメリットがあり、どちらが良い悪いではなくバランスが大事なんです」
大崎氏は力強い口調で続けます。
「多くの人は感情を表に出すことを良くないことだと思っています。ネガティブな感情は特に縁起を大切にする人たちから運気が下がりそうとか言われてとにかく煙たがられる。しかし自分を守るための防衛システムが働いている証拠でもあります。怒りは挑戦や革命のエネルギーに転換できるし、不安は予防や対策、存続や守ることに繋げることができます。大切なのはネガティブ感情を持ち続けずにその都度解放して必要なものを取り入れていくことです。
ネガティブな感情を煙たがるあまり、反射的に蓋をして見えないようにするのですが、実は無意識に持ち続けていることに本人は気づいてないんですよね。更に、感情は喜びや幸せなどのポジティブなものもあります。ところが日本では、嬉しいことがあっても『周りから嫉妬されたり、足を引っ張られてしまうかもしれないとか、周囲の人を差し置いて自分だけ喜んでるのは何か悪い気がしてしまう』という心配から、そうした良い感情すら表現することを自分で許可しない人が多いんです。でも人は、ネガティブもポジティブな感情も溜めてしまうと滞ります。そうなると、バランスを取ろうとして、過度な承認欲求や飲酒、ショッピング、異性関係など、酷くなると依存症に発展してしまうんですね。他にも、SNSでの匿名投稿やネットでのアンチ行為も、日常生活の中で感情を上手に解放できない、表現できない(癒されていない)ことで、歪んだ形で表現してしまうのです。」
手紙営業と人脈構築術ー「断られても5回アプローチ」の営業哲学
現在の信頼関係構築力は、営業時代に培われました。特に京都での営業経験は、大崎氏の人脈構築術の基礎となっています。
「京都は東京とは全く違って、より丁寧で繊細なアプローチが必要でした。個人的感覚としては名古屋と似ている部分もあるのですが、そもそも『一見さんお断り』のお店が多くて、紹介がないと相手にしてもらえないんです」
京都転勤時、大崎氏は徹底的な事前準備を行いました。
「会社には京都に詳しい人がいなかったので、転勤が決まった時に、東京で知り合った京都出身の方々に相談しました。老舗和菓子店の跡継ぎの方や、お土産屋さんの若旦那、歴史あるお寺の住職など、現地の人脈を紹介していただいたんです」
特に重要だったのは「白足袋族」との関係構築です。
「京都では『白足袋族』と呼ばれる方々が最も影響力を持っているとアドバイスされました。華道や日本舞踊の先生、お寺の住職などの文化人の方々ですね。『まずは白足袋族と仲良くなるといいよ』と言われて、お寺の住職と知り合いになることができました」
営業手法も独特でした。レストランのシェフがどこで修行していて、その師匠がまたさらにどこで修業していたかという系譜も全部ノートにまとめて調べ、手書きの手紙を継続的に送ります。
「お店に伺った後は必ず手書きでお礼状を書いていました。断られても、何度でも心を込めて手紙を送り続けました」
断られても3回、4回、5回とアプローチを続ける理由について、大崎氏は説明します。
「料理人の方は職人気質の方が多いので、デジタル全盛の時代でも、手書きの手紙のような昔ながらの誠実なアプローチに心を動かされることが多いのかなと感じました。何度断られても諦めずに3回、4回、5回とアプローチを続けていると、タイミングが合った時に話を聞いてくれるようになり、後に契約をいただけることがよくありました」
鬱陶しがられる場合への対処法も心得ていました。
「上司の教えを参考にしつつ、相手の反応を見ながら、3ヶ月後に再アプローチするか、1年後まで待つかを判断していました。他の新規営業を回っている間に半年から1年が経つので、『そろそろ頃合いかな』というタイミングを見て再挑戦してたんです」
最終的には人脈が鍵となります。
「直接アプローチして契約が取れない場合は、その方と親しい人やキーパーソンとのつながりがないということなんです。『この方の料理仲間はどなたですか』『よく行かれるお店はどちらですか』と聞いて、そのお店に通ってシェフと親しくなり、そのシェフから紹介していただくという方法を取ったりもしていました」

紹介だけで顧客を獲得する「経営者専門カウンセラー」の実力
現在の事業で最も特筆すべきは、顧客の9割が経営者、紹介率8割という実績です。この転換点には、運命的な出会いがありました。
去年の夏、パートナーと別れて心身ともに疲弊していた時期に、3〜4年ぶりに大山峻護さんからLINEが届きました。
「『お茶会があるんですが、参加されませんか』というお誘いをいただいて、すぐに『参加します』とお返事しました」
大崎氏は当時を振り返ります。
「お茶会で自己紹介をする時も、当時はメンタルが不安定だったので、話している途中やその場にいる人たちの優しさや強さに触れる度に泣いてしまいました。他の参加者の方で壮絶な人生経験を話されるのを聞いていたら、その方の辛い体験に共感して、涙が止まらなくなってしまったんです」
そこからの展開が転機となりました。
「大山さんがその後もいろいろな集まりに誘ってくださって、何人かの方からセッションを受ける機会もいただきました。その時に『あなたは女性をターゲットにするより、経営者向けの方が向いている。それがあなたの役割だから受け入れなさい』とアドバイスをいただいたんです」
最初は女性向けを想定していた大崎氏でしたが、アドバイス通り経営者にフォーカス。すると大山さんからの紹介で顧客が繋がり始めました。
経営者特有の課題にも対応しています。
「カウンセリングをしていると、経営者の方は大きく二つのタイプに分かれることが分かりました。特に成功している男性経営者の方は、論理的思考が得意で、それで成功を掴んでいる方が多いんです。ただ、その一方で感情を抑え込むことで成功してきた方も多く、長年感情を無視し続けた結果、自分の気持ちを感じにくくなっている状態の方が少なくありません」
具体的には、感情カードを使ったセッションで問題が明らかになります。
「様々な感情が書かれたカードの中から、今の気持ちに近いものを選んでもらうのですが、選べない方がいらっしゃるんです。厳しい家庭環境で育って感情表現を我慢してきた方や、子供の頃に厳しい環境や、泣いたら叱られるような環境にいた方は、男女問わず感情を表に出すこと自体が難しくなっています」
一方で、改善事例も生まれています。
「奥様の行動が理解できずにイライラしてしまうけれど、それを伝えることができずに我慢していた経営者の方がいました。カウンセリングを通して、なぜイライラするのかという自分の感情に向き合い、『自分の感情に責任を持つ』ということの意味が分かったそうです。その結果、家庭でのコミュニケーションやパートナーシップが大きく改善したという事例をいただいています」
「感情はエネルギー」ー経営者の心を軽くする新時代のリーダーシップ論
大崎氏が提唱するのは、従来のコントロール型リーダーシップからの脱却です。
「経営者は組織をまとめる責任があります。でも本来は、部下を支配するようなネガティブな方法を取らなくても、上手にその人をリードすることはできるはずなんです」
多くの経営者が陥る問題について説明します。
「多くの経営者がコントロールしようとしてしまうんです。コントロールに走ると、今度は不信感が生まれて『指示したことをやってくれない、この人は信頼できない』となってしまいます。でも実は、相手の行動が原因で信頼できないのではなく、その人自身の中に『信頼できない』という観念があるから、信頼できないような出来事が起こっているんです」
特に有能な経営者が陥りやすい罠も指摘します。
「能力の高い経営者ほど良くも悪くも自己責任の感覚が強く『自分が変われば解決する』と考えます。確かにその通りなのですが、責任を通り越して、自分を責めすぎてしまったり、自分で負担を抱え込みすぎてしまうんです。『この人に言っても聞いてくれないだろうから、自分がやった方が早い』と考えて、必要以上の業務を引き受けてしまい、自分と他者の境界線が分からず曖昧になり、結果的に負担が増えたり自己犠牲がいきすぎて体調を崩したり何かしらの不具合や不調和を生じてしまいます」
解決の鍵は「課題の分離」にあると大崎氏は説明します。
「『部下ができないから自分がやる』というのは、実は相手の課題を不必要に引き受けていることになります。部下を信頼して仕事を任せ、その結果を信頼して待つ——ここが多くの経営者にとって難しいポイントなんです。でも、この壁を乗り越えることができれば、部下の成長を実感できるようになります」
そして確信を込めて言います。
「思い切って本気で任せてしまえば、相手は意外とちゃんとやってくれるものです。もちろんそうじゃない場合もありますが、その場合はいくつもの問題やトラウマなどが複雑に絡んでいるケースもあるため単純なものではありませんが、大体こういったケースは信頼して待つということが、問題を感じている側の課題でもあったりします」
この考え方は子育てにも通じると大崎氏は語ります。
「子育ても同じで、親が心配しすぎて何でも与えてしまうと、子供は自立できなくなってしまいます。子供が自分で立ち上がる力を身につけるためには、自分で考えて行動する機会を与えて、親はそれを見守って待つことが大切です。この『待つ』ということも、愛情や信頼の一つの形なんです」

タイ移住で実現する「海外×日本」のグローバルカウンセリング戦略
大崎氏は今後、タイ移住を決断。その背景には明確なビジョンがあります。
「一番の理由は、息子にいろいろな世界を見せて多様な経験をしてもらいたいという思いです。それと同時に、私自身も異なる文化や様々な人種の方々と交流することで、学びを深めて人生を楽しみたいと考えました」
タイとの縁は偶然から生まれました。
「実は一度も行ったことがない国だったのですが、なぜかとてもワクワクしたんです。物事が自然な流れで決まっていったので、これは縁があるに違いないと直感で決めました」
具体的なきっかけは、大山さんの知り合いが関わるイギリスの名門校でした。
「大山さんの知り合いに、タイにあるイギリスの名門校の分校で最高顧問をされている方がいらっしゃいます。その方のインスタグラムをフォローしていたら、2月に学校説明会を兼ねたツアーがあることを知りました。『ちょっと面白そうだな』と思って、旅行も兼ねて見聞を広げるために参加してみることにしたんです」
今後のビジョンについて、大崎氏は明確に語ります。
「海外と日本の二拠点生活、そしてキャリアと子育ての両立を目指しています。短期・中期的には、経営者の方々の心の状態を最適に整えることで、企業としてより良い発展をしていただけるようなサポートを続けていきたいと思います」
そして長期的な社会貢献への想いも明かします。
「長期的には、心に傷を抱えた子供たちや児童養護施設の子供たちのケアに携わる活動ができればと考えています」
大崎氏は力強く宣言します。
「中小企業では経営者のコンディションが会社の業績に直結します。日本企業の90数パーセントが中小企業ですから、そこが改善されれば日本全体が変わると本気で思っているんです」
感情解放が拓く、日本の経営者と企業の新たな可能性

大崎美紀氏との対話を通じて浮き彫りになったのは、日本の経営者が長年抱え続けてきた「感情抑圧」という根深い課題と、それを根本から変革する革新的なアプローチでした。
営業時代に磨き上げた人脈構築術、産後うつという人生の試練から得た深い心理学的洞察、そして外資系企業で体感した自由な発言文化——これら異なる経験の全てが一つに結実し、「経営者向けカウンセリング」という前例のない分野を切り拓いたのです。顧客の9割が経営者、紹介率8割という圧倒的な実績は、潜在的なニーズの大きさを如実に示しています。
大崎氏が提案するのは、「我慢は美徳」という日本社会に深く根ざした価値観からの解放です。感情を抑え込むのではなく、それをエネルギー源として活用する——この新時代のリーダーシップ論は、単なる個人の変化を超えて、組織風土の変革、ひいては日本経済全体の底上げという壮大なビジョンを描いています。
タイでの国際的な展開という新章も含め、大崎氏の今後の活動は多方面から注目を集めています。日本企業が長年求め続けてきた真の「心理的安全性」を実現する組織づくり——その答えの一端が、ここにあるのかもしれません。
ギャラリー














プロフィール
株式会社Realize
代表取締役
大崎 美紀
愛知県出身の心理カウンセラー。ITベンチャー企業での営業を経て、大手米国企業では富裕層向け飲食店サービスを担当。その後、金融ベンチャーで富裕層向けマーケティングに携わる。産後の心の変化をきっかけに心理学を学び始め、2021年に株式会社Realizeを設立。
現在は経営者を中心に心理カウンセリングや講座を提供し、紹介を中心に事業を展開。座右の銘は「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから」「日日是好日」。趣味はワイン、ゴルフ、インテリア。
2025年8月にはタイへの移住を予定しており、国内外での活動を通じて経営者の心の状態を整え、より良い企業へと発展するサポートを目指している。
会社概要
| 設立 | 2021年 |
| 資本金 | 800万円 |
| 所在地 | 東京都港区三田2-4-3-310 |
| 事業内容 | 心理カウンセリング、講座、アドバイザー業務、企画 |
| HP | – |
御社の想いも、
このように語りませんか?
経営に対する熱い想いがある
この事業で成し遂げたいことがある
自分の経営哲学を言葉にしたい
そんな経営者の方を、コントリは探しています。
インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。
条件は「熱い想い」があることだけです。
経営者インタビューに応募する
御社の「想い」を聞かせてください。
- インタビュー・記事制作・公開すべて無料
- 3営業日以内に審査結果をご連絡
- 売上規模・業種・知名度は不問
※無理な営業は一切いたしません
発信を自社で続けられる
仕組みを作りたい方へ
発信を「外注」から「内製化」へ